橋梁点検ロボット
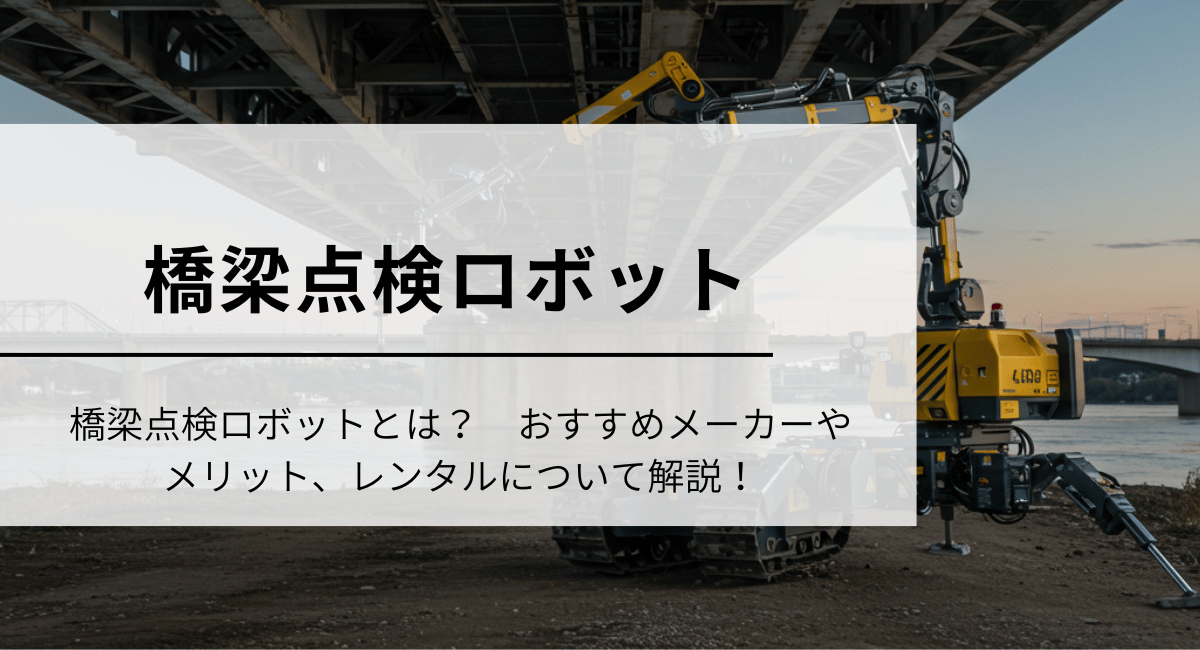
近年、インフラの老朽化が進む中で、橋梁の安全性を確保する点検業務の重要性が高まっています。その中でも注目を集めているのが、最新技術を駆使した「橋梁点検ロボット」です。
「作業員の安全が心配」「点検コストがかさむ」「点検の質を維持できるか不安」といった悩みを抱える自治体や企業にとって、橋梁点検ロボットは解決策となり得ます。
この記事では、橋梁点検ロボットの特徴や仕組み、種類ごとの違い、導入によるメリットと課題、おすすめのメーカーまで包括的に解説しています。
また、レンタルについても解説しているので、橋梁点検ロボットの導入を検討中の方はぜひご参考にしてください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
目次
最近の更新内容
2026/1/23更新 企業情報の更新
橋梁点検ロボットとは? 仕組みや注目されている理由を解説

この章では、橋梁点検ロボットの定義や、仕組み、近年注目されている理由を解説します。
橋梁点検ロボットの基本的な情報を確認したい方は、是非ご一読ください。
橋梁点検ロボットの定義と目的
橋梁点検ロボットとは、橋の桁下・側面・橋脚など、人が立ち入りにくい部位を安全かつ効率的に調査するために設計された自律または遠隔操作型のロボットシステムです。
走行型(地上・下面)、吸着型、ドローン型、伸縮アーム型、水中ROVなど、多様な移動機構を備え、4K/8KカメラやLiDAR、赤外線、超音波などのセンサーを組み合わせることで、ひび割れ幅 0.1mm 前後の微細欠陥や腐食、変形といった劣化サインを定量的に検出します。
橋梁点検ロボットは安全性の向上(高所・狭隘部での作業リスクを低減)、効率化とコスト削減(足場や交通規制を最小化し短時間で広範囲を調査)、そしてデータの高度化(AI解析や経年比較で早期劣化を把握し計画的補修を支援)を目的としており、橋梁の長寿命化と維持管理の最適化を図ることにあります。
橋梁点検ロボットの主な構造と仕組み
橋梁点検ロボットは、さまざまな機能を持つ高度な技術を搭載しています。
主な構成要素は以下になります。
- カメラ – 高解像度カメラを使い、橋梁の状態を視覚的に確認し、ひび割れや腐食などの兆候を検出
- センサー – ひび割れ、腐食、ゆるみなどの物理的な変化を検出するセンサー(例:音波センサー、温度センサー)
- マニピュレーター(作業アーム) – 高精度で操作可能なアームを使い、細かな作業や部材の動かし作業を行う
- 自走機構 – ロボットの移動を担当し、橋梁の下面や支柱、難アクセスの場所に自在に移動
- 画像解析技術 – 撮影した画像を解析し、ひび割れや腐食などの劣化を自動で識別
- AI(人工知能) – 画像解析を通じて、点検結果をリアルタイムで解析し、劣化部分を自動的に判別
橋梁点検ロボットが注目される理由
日本には橋長2m以上の道路橋が約73万橋あり、そのうち建設後50年以上の橋は2030年に54%、2040年には75%に達すると国土交通省が推計しています。
さらに、2014年の道路法施行規則改正により5年ごとの近接目視点検が義務化され、点検件数は増加しています。
一方で、建設業界は2025年に約90万人の労働力不足に直面すると国交省の試算が示しており、点検作業の担い手確保が課題です。
この需要ギャップを埋める手段として、短時間で安全かつ高精度にデータ取得ができる橋梁点検ロボットが注目されています。
実際の導入例として、NEXCO東日本は2024年3月27日のプレスリリースで、ドローンによる鋼橋動画点検を正式運用し、複数の高速道路路線で活用を開始したと発表しました。
また、日鉄エンジニアリングの「橋梁点検ロボット(KK-240062-A)」はNETIS登録技術として近畿地方整備局の国道橋点検で採用され、橋梁点検車と比べて人員・交通規制日数を削減した効果が報告されています。
さらに首都高速道路は2024年1月25日、小松川斜張橋・五色桜大橋・レインボーブリッジでドローンポートを用いた自動飛行点検の実証を行い、遠隔地からリアルタイムで橋梁状況を把握できることを確認しました。
このように導入事例が各地で増え続けており、橋梁点検ロボットは老朽化インフラ維持管理の実戦ツールとして定着しつつあります。
種類ごとに橋梁点検ロボットを解説

橋梁点検ロボットにはいくつかのタイプが存在し、それぞれの特性に応じて適した場面があります。ここでは主要な種類とその特徴について詳しく見ていきましょう。
走行型(地上・下面走行タイプ)
走行型は橋梁の桁下や下面をレールや磁石、吸着機構などを用いて移動するタイプです。
狭小空間での運用に適しており、実績が豊富です。このタイプの橋梁点検ロボットは、通常、高解像度カメラや赤外線カメラを搭載し、ひび割れや腐食などを視覚的に高精度で捉えます。
ドローン型
空中を自由に飛行して橋梁全体を撮影・点検できるのがドローン型です。
GPSやセンサーを組み合わせ、安定飛行を実現しています。このタイプのロボットも高解像度カメラを搭載し、広範囲の検査を短時間で行い、視覚的な情報を得ることが可能です。
赤外線カメラを利用して目視では確認できない異常を検出することができます。
アーム型(高所伸縮・多関節タイプ)
橋の側面や桁下に向けて伸縮可能なアームを持つタイプで、複雑な構造や多関節の動きが可能な橋梁点検ロボットも登場しています。
このタイプも高精度なカメラを搭載し、定点観測や高精度な接写点検に適しています。
種類によって適性が異なるため、導入前には目的や現場環境をよく見極めることが大切です。次は、導入によって得られるメリットについて詳しく見ていきましょう。
橋梁点検ロボットのメリット・課題を解説

橋梁点検ロボットの導入にはいくつかのメリットがありますが、同時に課題も存在します。ここでは、メリットと課題をそれぞれ解説します。
次に橋梁点検ロボットの課題を解説します。
これらのメリットと課題を踏まえ、橋梁点検ロボットの導入はインフラ維持管理の効率化や安全性向上に貢献する可能性がある一方で、実際に導入する際の検討事項や課題もあります。
次に、これらの課題に対する解決策として「レンタル」の選択肢について解説します。
橋梁点検ロボットのレンタルについて
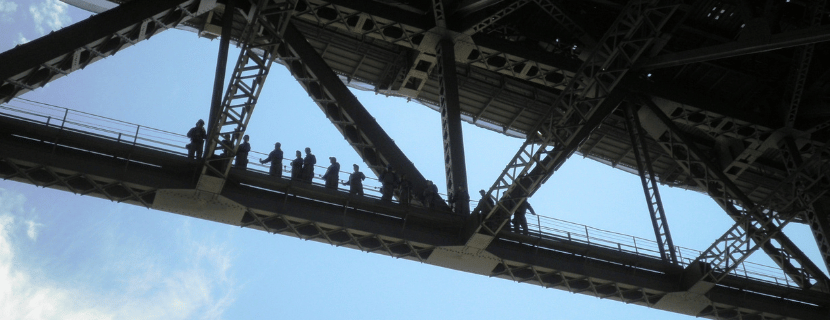
橋梁点検ロボットは高価で専門的な機材が多いため、特に小規模な自治体や企業では、導入に際しての予算の問題が課題となることがあります。
しかし、近年、レンタルサービスの提供もあり、これを利用することで、コストを抑えつつ最先端の技術を活用することが可能となります。
レンタルのメリット
橋梁点検ロボットをレンタルする利点は、まず高額な本体を購入せずに済むため初期投資を抑えられる点です。
さらに、点検の予定やプロジェクト期間に合わせて必要なときだけ借りられるので、使用頻度に応じて最適なコスト管理が可能になります。
加えて、保守や修理はレンタル会社が一括して対応してくれるため、ユーザーは煩雑なメンテナンス業務から解放され、橋梁点検そのものに集中できます。
レンタルのデメリット
レンタルは短期利用なら経済的ですが、長期契約になると総費用が購入額を上回る恐れがあります。
加えて契約期間や使用回数に上限があるため、急な延長や追加点検に柔軟に対応しにくい点が問題です。
さらにレンタル会社が保有する機材には限りがあり、特殊な機能や最新モデルを選べない場合もあります。
レンタルを活用する際のポイントを解説
橋梁点検ロボットをレンタルする際は、使用目的や頻度に応じて、最適な機材を選定することが重要です。また、レンタル会社のサービス内容やサポート体制を確認し、万が一の故障やトラブルに備えることが大切です。
レンタル期間や料金体系を事前にしっかりと把握し、計画的に利用することで、効率よくインフラ点検を進めることができます。
橋梁点検ロボットのレンタルは、特に限られた予算内で高性能なロボットを活用したい場合や、必要な時にだけ専門的な機材を使用したい場合に有効な選択肢となります。
次の章では、橋梁点検ロボットを導入する際の選び方のポイントを解説します。
選び方を解説! 橋梁点検ロボットの選定ポイントを解説

橋梁点検ロボットを導入する際には、性能や価格だけでなく、現場条件や運用目的に適した選定が求められます。ここでは、3つの選び方の観点から、選定ポイントを解説します。
移動/固定方式が橋梁の形状・材質に合うか
1つ目の橋梁点検ロボットの選定ポイントは、橋面上・側面・桁下など点検対象部位に合わせて磁力吸着走行型・吸盤型・ドローン型などロボットの「移動/固定方式」が自社橋梁の形状と材質に適合するかを確認することです。
橋梁の材質(鋼・RC・PC)や桁下空間の高さ、付属物との干渉、交通規制の可否といった現地条件によって、この方式の適合性は左右されます。
もし方式が橋梁に適していなければ、橋梁点検ロボットが点検エリアに到達できず、作業漏れや追加の足場設置によるコストが発生する可能性があります。
高架道路や河川をまたぐ橋など、足場の設置が難しくコストが高騰しやすい現場では、この選定はとくに重要です。
適合方式を選べば足場不要で全域を一度にカバーでき、点検時間を短縮できるというメリットが期待できます。
点検したいポイントに適したセンサーを搭載しているかどうか
点検を成功させるには、「どこを、何を見たいか」という目的に合ったセンサーを搭載しているかが重要です。
例えば、「髪の毛1本分(0.1mm)ほどの細かなひび割れ」を見つけたいなら高性能なカメラ、「橋全体の形の歪み」を調べたいならLiDAR(レーザースキャナー)や電磁波センサーといったように、目的に応じて最適なものを選ぶ必要があります。
センサーを選ぶ際は、自社の点検ルール、点検の頻度、過去の損傷データ、そして橋の種類による劣化の仕方の違いなどを考慮しましょう。
センサの性能が不足していると、重要な劣化サインを見落とすことにつながり、結果として重大な構造損傷や高額な補修費用が発生するリスクを高めます。
特に老朽化が進んでいる橋梁や、微細なひび割れ進行の監視が求められる長寿命化計画においては、この観点が重要です。
適切なセンサを搭載すれば、目視より早期に微細欠陥を定量化でき、保全計画を先取りできるという点は、長期維持管理の観点から利点となります。
データ連携・処理プラットフォームが整っているか
最後に検討すべきは、取得した3D点群や画像をBIM/CIMや橋梁管理DBに自動同期しAI解析できる「データ連携・処理プラットフォーム」の有無を確認することです。
既存の資産管理システムとのAPI互換性やクラウド環境の有無、社内のITセキュリティ規程といった要因が、スムーズなデータ連携を実現できるかどうかを左右します。
もしデータの自動連携ができなければ、手動で整理・転送する必要があり、その結果として報告書作成の遅延や再点検の発生といった非効率な運用につながる可能性があります。
特に自治体や道路会社のように多数の橋を一元管理し、年次で大量の点検データを更新していく体制では、この要素は欠かせません。
データ連携により進行性損傷の時系列比較や補修優先度AI判定が即座に実行でき、意思決定が迅速化するというメリットは、管理部門にとって魅力的な成果です。
ここまで橋梁点検ロボットを選ぶうえで重要な観点を3つ紹介しました。続いては、具体的にどのメーカーがどのような製品を提供しているのかを見ていきましょう。
おすすめの橋梁点検ロボットメーカーを紹介

ここでは、橋梁点検ロボットを検討するうえでJETGlobalが選んだおすすめメーカーを厳選し、それぞれの技術や導入実績などの観点から詳しく紹介します。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- イクシス / iXs
- 日立産業制御ソリューションズ / Hitachi Industrial Control Solutions
- 大林組 / Obayashi
- 日鉄エンジニアリング / Nippon Steel Engineering
※クリックすると該当箇所まで飛びます
イクシス / iXs
自社開発によるワイヤ吊り下げ・磁着走行などの多様な移動機構に加え、AIによる画像解析を組み合わせた技術力が特徴の企業です。代表的な橋梁点検ロボットは「Rope Stroller」で、支間60 mのワイヤ上を安定して走行しながら、0.1 mm幅のひび割れを風雨の中でも撮影ができます。 常に正対姿勢を保つセンサー機構により、天候や構造条件に左右されず高精度の目視点検を実現できる点が強みです。首都高速道路、複数自治体の橋梁床版裏面点検などで実運用されています。
日立産業制御ソリューションズ / Hitachi Industrial Control Solutions
OTとITを組み合わせ、現場の画像取得からクラウドによる解析まで一気通貫で対応できる総合力が魅力の企業です。同社の橋梁点検ロボットカメラ「HV-HT3000TB-U/D」は、橋面上から10.5 m伸びるポールと30倍ズーム機能により、橋脚や桁下面を地上から近接目視レベルで点検できます。通行規制の大幅削減と安全性の両立を図りながら高精度な画像を取得できる点が強みです。国土交通省山口河川国道事務所や各地方自治体の定期点検で実績があります。
大林組 / Obayashi
インフラ点検分野においては、独自の姿勢制御技術「アクアジャスター」を搭載した水中・海上ROVの開発に注力しています。代表的な機種には、海上桟橋下面点検用の「ピアグ®」があります。波浪や濁水中でも安定姿勢を維持しながら、24時間連続で深度150mの高解像度映像取得を可能にする点が強みです。東京港桟橋や各地のダム堤体で活用され、国交省インフラメンテナンス大賞の受賞実績も誇ります。
日鉄エンジニアリング / Nippon Steel Engineering
鋼橋製造の豊富な経験を活かし、AI画像解析と融合した橋梁点検ロボットを自社開発しています。主力製品は橋梁点検ロボット「KK-240062-A」で、橋面上から小型台車に搭載したアームを伸ばし、桁下を4Kカメラで高解像度撮影します。交通規制を最小限に抑えながら0.1mm幅のひび割れを高精度で検出可能な点が強みです。近畿地方整備局の連続鈑桁橋や複数自治体の道路橋における NETIS 活用事例として広く導入されています。
