陳列ロボット
陳列ロボットとは? おすすめのメーカーや事例、選定ポイントを解説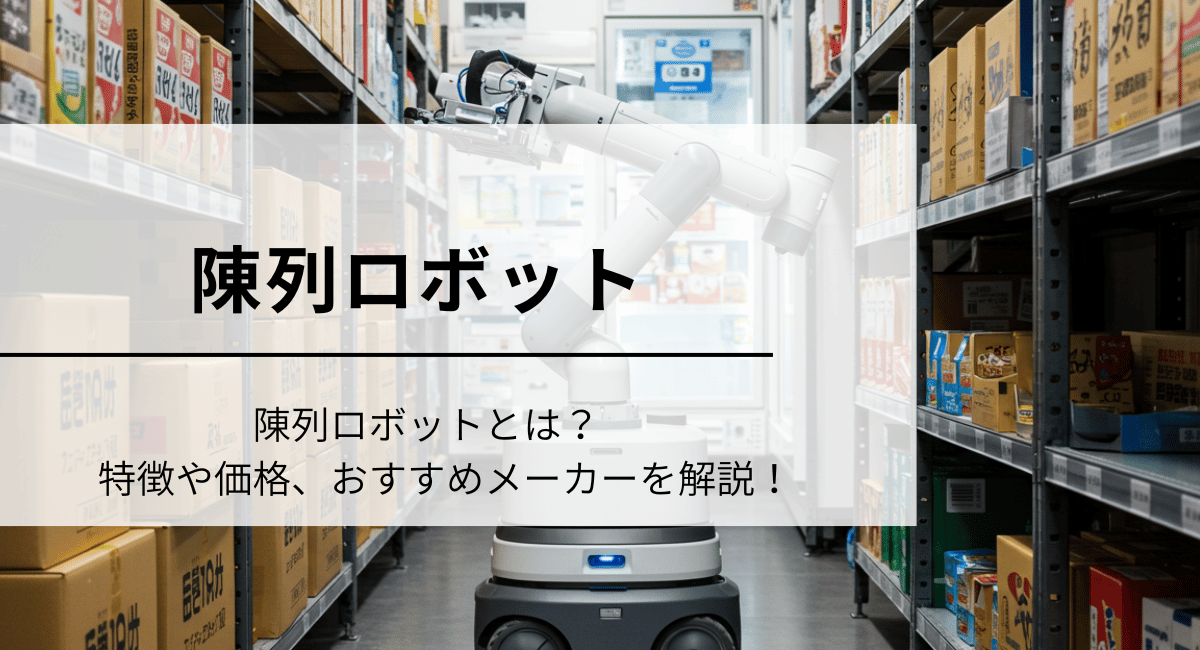
小売業界の人手不足を背景に、品出しや前出しといった従業員の負担を軽減する「陳列ロボット」が、解決策として注目されています。
「補充作業に人が取られて接客がおろそかになる」「深夜帯の人件費がかさんで利益が出ない」といった悩みに心当たりはありませんか。
本記事では、陳列ロボットの基本情報から種類・価格・メリット・デメリット、さらには選定ポイントとおすすめメーカーまで体系的に解説します。
読み進めることで、自社に最適な陳列ロボットを見極める視点が身に付き、導入後の運用トラブルを未然に防げるでしょう。
まずは概要を押さえ、実際の選定に役立つ具体的な情報を手に入れてください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
また、JET-Roboticsでは、陳列ロボット以外にも小売業界で役立つさまざまな小売ロボットを解説しています。小売ロボットの全体像について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
陳列ロボットとは? 基本情報や実際の事例も紹介

陳列ロボットとは、店舗や倉庫で商品を棚に補充・整列させる自律型または遠隔操作型のロボットを指します。
このロボットの特徴は、AIやセンサーを駆使した高度な自動化機能です。
AIカメラで棚の欠品や乱れを瞬時に把握すると、センサーで障害物を避けながら自律走行して商品を補充・整頓します。これにより、煩雑な在庫確認から重労働の品出しまで、一連の作業が自動化されます。
そして、高性能なロボットアームが商品を正確に補充・整頓するため、煩雑な在庫確認から重労働となる品出しまでを一貫して自動化することが可能です。
近年は労働力不足や24時間営業の増加を背景に、実運用の事例が急速に拡大しています。また、バックヤードの作業効率を高めるだけでなく、欠品防止による売上機会の創出や、スタッフが接客に集中できる環境づくりにも寄与します。
活用事例:コンビニなどで活用される陳列ロボット
大手コンビニチェーンでは、深夜帯の人員不足を補うために冷蔵飲料・菓子パンの自動補充へロボットを活用しています。
遠隔操作により一人のオペレーターが複数店舗を担当し、AI画像分析が売れ筋を把握して補充優先度を判断します。
スーパーやドラッグストアでも、AGV(無人搬送車)型ロボットがバックヤードから商品を運び店頭棚に自動陳列する試みが進んでいます。
FamilyMartが2022年より導入を進めるTelexistenceの「TX SCARA」は、冷蔵ケースの飲料を最大1,000本/日補充できる遠隔操作ハイブリッド型のロボットです。
陳列ロボットの基本情報と活用事例を把握したところで、次は「どんな種類があるのか」を確認しましょう。
主要な3種類の陳列ロボットを解説

この章では、陳列ロボットの主要3タイプを取り上げ、それぞれの特徴と他方式と比較した際のメリット・デメリットを整理します。
定点アーム型
バックヤードや冷蔵ケース裏側に据え置いたロボットアームが、コンベヤーで供給された商品を棚越しに補充する方式です。設置場所が限られるため省スペースであり、冷蔵・冷凍帯商品に強い点が評価されています。
AGV/AMR移動型
AGV/MRの上部にロボットアームや昇降機構を搭載し、店内通路を自律走行して複数棚に商品を補充する方式です。バックヤードと売り場が離れていても自走で搬送できるため、大型スーパーでの採用が進んでいます。
天井走行レール型
天井に敷設したレールをロボットユニットが走行し、真下の棚へ垂直移載機構で商品を投入する方式です。倉庫のオートストアに近いイメージで、店舗床を占有しないため動線確保に優れています。
以上が代表的な3方式です。続いて、それらを導入した際に得られるメリットを具体的に見ていきましょう。
陳列ロボットの導入メリットを解説

陳列ロボットを導入する利点は、人件費の削減と店舗オペレーションの質向上を同時に実現できる点です。
次に、陳列ロボット導入の際のデメリットを解説します。
※参考:
TEC TiMES 「Japanese Stores Deploy A Fleet of ‘AI-Driven Robots’ To Replace Shelf Stockers」
MathCo 「Out of Stock No More: Ensuring Effective Stocking for Retail」
PatentPC 「Robotics Maintenance Costs: Operating Efficiency Data」
陳列ロボットの導入デメリットを解説

陳列ロボットは生産性向上に貢献しますが、導入後の後悔を避けるため、事前にデメリットを理解しておくことが重要です。
これらの課題を事前に検討し、対策を講じることが、陳列ロボット導入を成功に導く鍵となります。
次の章では、陳列ロボットの選定ポイントを解説します。
陳列ロボットの選定ポイントを解説

多種多様な陳列ロボットの中から最適な一台を見極めるには、機能面と運用面の両方から判断基準を整理する必要があります。ここでは専門家視点で必ず押さえたい三つのポイントを紹介します。
店舗の棚割りデータをリアルタイムで取り込み反映できるソフトウェア連携機能の有無
陳列ロボットが正確に商品を補充するには、店舗の設計図である「棚割り(プラノグラム)」のデータとロボットシステムが連携することが不可欠です。
具体的には、自社で利用している棚割管理システムで作成された、JCA手順などの標準フォーマットのデータをロボット側が直接読み込めるか、あるいは※APIを介してシステム連携できるかを確認します。
例えば、小売業界で広く導入されている特定の棚割管理システムとの連携実績が公表されていれば、それは信頼性の高い判断材料となります。
この連携の更新頻度も重要です。クラウド経由で数分おきに棚割りデータが同期される陳列ロボットであれば、現場での急な特売やレイアウト変更にも即座に対応できます。
この機能がなければ、陳列ロボットは古い情報で作業を続け、補充ミスや機会損失に繋がるため、特に棚の変更が頻繁なスーパーマーケットなどでは必須の機能と言えます。
- ※API(Application Programming Interface):異なるソフトウェア同士が情報をやり取りするための「窓口」となる規約や仕様
多様な商品の形状・重量に1台で対応できるか
商品を掴む「ハンド(グリッパー)」部分の性能は、ロボットの対応力を直接左右します。ハンドには、ポンプで商品を吸い付ける「真空吸着式」と、指で商品を掴む「電動フィンガー式」などがあり、それぞれ得意な商品が異なります。
-
真空吸着式
ポテトチップスの袋や平らな箱など、表面が平滑な商品の扱いに適しています。 -
電動フィンガー式
ペットボトルやパウチ飲料、不定形な商品など、様々な形状を掴むことに適しています。
扱う商品が多岐にわたるドラッグストアやスーパーでは、アタッチメントを交換して両方の方式に対応できる「モジュール式」の陳列ロボットが有効です。
さらに近年では、AIカメラが商品の形状や素材を瞬時に認識し、掴む力や角度を自動で最適化する高度なハンドも登場しています。
米国のRightHand Robotics社などが開発したAIピッキング技術がその代表例であり、このようなロボットは、従来は難しかった多種多様な商品を一つのハンドで扱うことを可能にします。
お客様や従業員と安全に共存できるか
お客様や従業員が働く店内でロボットを安全に稼働させるには、高度なナビゲーション技術が不可欠です。
その鍵となるのが、複数のセンサー情報を統合して判断する「センサーフュージョン」技術です。
例えば、広範囲を検知する3D-LiDAR(レーザースキャナー)で人や台車の位置を大まかに把握し、ステレオカメラでその形状や移動方向を立体的に予測、さらに足元の死角を超音波センサーで補う、といった多層的な検知システムが実装されているかを確認します。
また、安全性を客観的に評価する指標として挙げられるのは、国際安全規格「ISO 3691-4」への準拠です。
これは、無人産業車両(陳列ロボットも含まれる)が人と共存する環境での安全性を定めたもので、この認証を取得しているモデルは、第三者機関により安全性が担保されていることを意味します。
これらの選定ポイントを押さえることで導入後のトラブルを未然に防ぎ、最適な機種選定へ近づけます。次は、これらの基準を満たす信頼できる陳列ロボットのおすすめメーカーを確認しましょう。
陳列ロボットのおすすめメーカーを紹介

陳列ロボットの性能を最大限に引き出すには、豊富な実績と技術開発力を備えたメーカー選定が重要です。ここでは導入支援まで一気通貫で任せられる企業を厳選して紹介します。
また、陳列ロボット導入の際に補助金を活用することで導入のコストを軽減できる可能性もあります。詳しく知りたい方は以下からお気軽にお問い合わせください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- テレイグジスタンス / Telexistence
- 川崎重工業 / Kawasaki Heavy Industries
- マガジーノ / Magazino
※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。
テレイグジスタンス / Telexistence
| 会社名 | テレイグジスタンス / Telexistence |
| 設立年 | 2017年 |
| 本社 | 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター物流ビルA棟 AE3-3 |
| 概要 | 小売バックヤード向け遠隔・AI陳列ロボット専業 |
テレイグジスタンスは、小売店舗の冷蔵飲料棚を対象に、AI制御「GORDON」と異常時に即時切替できるVR遠隔操作(Telexistence mode)を組み合わせた陳列ロボットを開発しています。
テレイグジスタンスの陳列ロボットである「TX SCARA」は据え置き型アームのみでピッキングとフェイスアップを行い、什器改装なしで導入できる設計です。
24時間運用を前提に量産され、2022年8月からファミリーマート300店舗へ順次配備された。先行機「Model-T」は2020年よりローソン東京ポートシティ竹芝店で実証稼働しています。
川崎重工業 / Kawasaki Heavy Industries
| 会社名 | 川崎重工業 / Kawasaki Heavy Industries |
| 設立年 | 1896年 |
| 本社 | 東京都港区海岸1丁目14-5(東京本社) 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー(神戸本社) |
| 概要 | 重工業・産業用ロボットの大手メーカー |
川崎重工業は、小型6軸ロボット「RS003N」を中核に、搬送ユニット・保管棚・陳列棚を一体化した「飲料自動陳列ロボットシステム」を開発しています。
RS003Nのハンドには350mL缶やPETボトルを把持できるグリッパと距離センサーを搭載し、在庫棚から商品を取り出してラベルを正面に向けた状態で売場へ補充する一連の動きを自動で行う点が特徴です。
導入先として想定されているのはスーパーマーケットやコンビニエンスストアなど飲料売場を持つ小売業界で、2019年の国際ロボット展(iREX 2019)で実機デモが披露されたほか、システムインテグレーターHCIと共同でスーパー店頭での実証が行われています。
マガジーノ / Magazino
| 会社名 | マガジーノ / Magazino |
| 設立年 | 2014年 |
| 本社 | ドイツ ミュンヘン |
| 概要 | 物流ロボット専業メーカー |
マガジーノは、倉庫内のピースピッキングや補充工程を知覚駆動型ロボットで自動化しています。
同社が陳列(棚入れ・棚出し)用途で主力とするのが、自律走行ピッキングロボット「TORU」です。人と並走しながら最大20時間/日の長時間稼働が可能で、Wi-Fi経由でWMSと連携しつつフリート間でナレッジを共有できる設計です。
導入業界は欧州のファッションEC倉庫を中心に拡大しており、Zalandoの物流センター(ドイツ・イタリア)では57台規模で稼働するほか、FIEGE LogistikやGaborのシューズ倉庫でも実運用されています。
これらの現場では、返品の再棚入れやピーク時のピッキング負荷平準化に貢献し、人と協働しながら省人化を実現しています。
導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
陳列ロボットの製品はまだありません。

