鉄筋結束ロボット
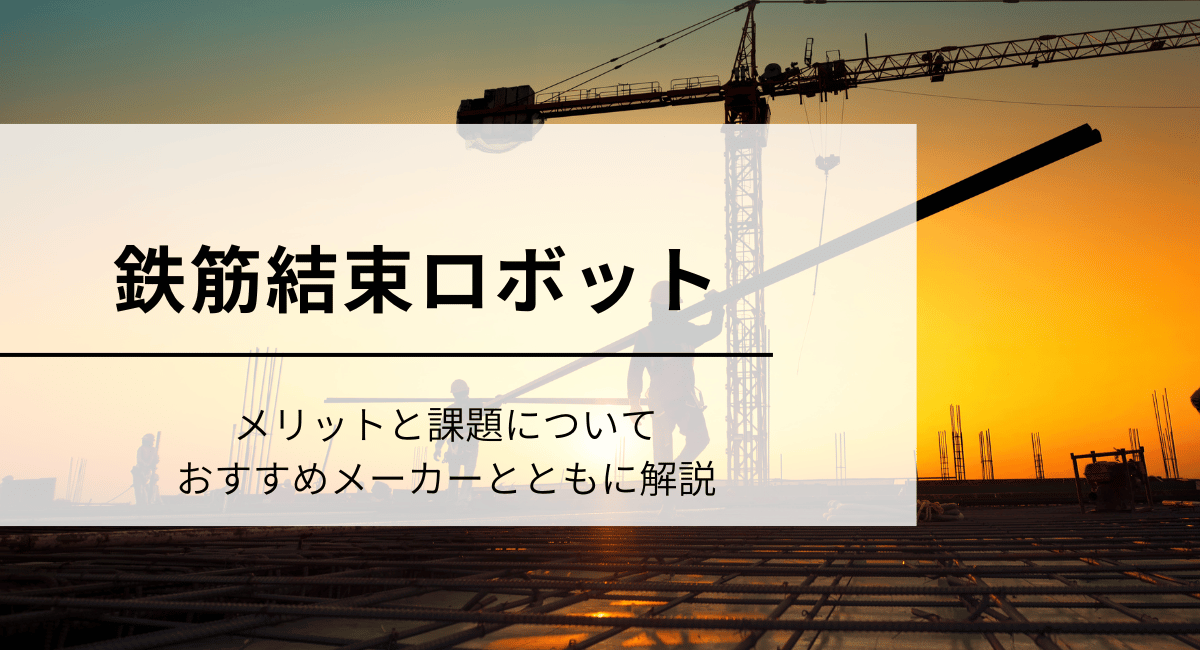
建築業における鉄筋結節作業は、単純作業でありながら時間がかかる作業のため、長時間しゃがみ姿勢を取ることの腰への負担が大きく、代替が期待されています。
こうした背景の中で注目されているのが鉄筋結束作業を自動化する鉄筋結束ロボットです。
しかし、「本当に使えるのか」「どれを選べばいいのか」といった疑問を抱える方も少なくありません。
現場で本当に役立つ1台を見つけるために必要な情報をお届けしますので、導入を検討している企業・担当者の方々は参考にしてみていただけると幸いです。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
また、JET-Roboticsでは、鉄筋結束ロボット以外にもさまざまな建設ロボットを解説しています。建設ロボット全体について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
最近の更新内容
2026/1/22更新 企業情報の更新
鉄筋結束ロボットとは? 仕組みや自動化の原理を紹介

鉄筋結束ロボットとは、建設現場で鉄筋同士を結束する作業を自動で行う機械のことです。鉄筋工の負担を軽減し、作業の効率化や品質の均一化を実現するために開発されました。
建築現場では、基礎・柱・梁などのコンクリート構造物を形成するために多くの鉄筋が使われますが、その接合作業はこれまで人手によって行われてきました。
バッテリー駆動や電動モーターを搭載し、位置認識センサーやAI技術を活用することで、人手に頼らない正確な結束が可能になります。
また、作業員がロボットを補助的に操作するセミオート型と、完全に無人で動作するフルオート型が存在し、現場のニーズに応じて使い分けられます。
従来の鉄筋結束作業では、姿勢の維持や繰り返し動作による腰痛・腱鞘炎などの身体的負担が問題でした。
次は、鉄筋結束ロボットの具体的なメリットについて詳しく解説していきましょう。
鉄筋結束ロボットのメリットを解説! 手作業とどちらが早い?
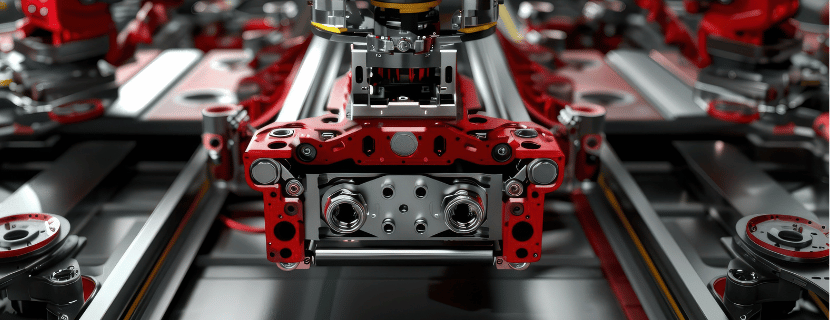
鉄筋結束作業において、ロボットを使用するとさまざまなメリットがあります。
この章では、鉄筋結束ロボットを導入した際に何に効果があるかを解説します。
また、「導入した場合、実際の作業はどのくらい早くなるの?」という疑問にもお答えして、手作業と比べた鉄筋結束ロボットの作業速度の違いにも注目しますのでぜひご確認ください。
人件費削減においては、一度設定すれば作業員の手を借りずに、または部分的なサポートのみで連続して稼働できるため、長時間の作業における人件費の圧縮が可能となり、深夜・休日・危険区域でも安定して作業を続けられる点が利点です。
品質の均質化においては、画像認識やセンサーによって鉄筋の位置やサイズを高精度に把握し、常に一定の締め付け強度で結束できるため、品質のバラつきがなくなり、仕上がり精度が向上します。
施工スピードの向上においては、人手作業と比較して同一時間内に処理できる結束数が増加することから、大規模工事では工程全体の短縮が見込まれ、特に遅れが出やすい基礎・構造フェーズにおいて効果を発揮します。
現場の可視化においては、最新のフルオート型が作業データをログとして記録し、施工管理ソフトと連携することで進捗や作業品質の見える化が実現され、管理者の負担軽減とともに現場全体のPDCAサイクルを効率的に回すことが可能になるでしょう。
鉄筋結束ロボットによって速度はどのくらい向上するのか
鉄筋結束ロボット「トモロボ」を製造する建ロボテックのデータでは、自動ロボットでは3秒弱と言われています。
また、日経クロステックの記事によると、1日あたりの結束数は人間より3割ほど多いとされており、少なくとも人間の1.3倍の速度があります。
実際に人間が行う場合は、休憩や食事、睡眠時間などを取らなくてはいけないと考えると、もっと人間の速度は落ちるでしょう。
1日にどのくらい結束できるかという点からみると、相対的な生産性の差はもっと大きいと考えられます。
次に、普及が進まない背景や技術的な課題などのデメリットについても解説していきましょう。
普及を妨げる鉄筋結束ロボットの課題

鉄筋結束ロボットは、作業の自動化によるメリットがある一方で、導入・運用に関していくつかの課題も存在します。
この章では、鉄筋結束ロボットが普及に至るまでの障壁となっている代表的な課題を3つに整理して解説します。
また、「なぜ便利なロボットがなかなか現場に入ってこないの?」という疑問に対しても、実際の導入事例や技術的な側面から理由を紐解いていきます。
初期コストに関しては、フルオート型の鉄筋結束ロボットが1台あたり数百万円から数千万円の価格帯にあり、これに加えてメンテナンス費や操作研修などの間接費用もかかるため、導入に踏み切れない施工会社も少なくありません。
柔軟性については、建設現場は設計図面通りに進まないことも多く、鉄筋の位置ずれや作業空間の制約が頻発するため、ロボットには高度なセンサー制御や現場判断力が求められます。現在は半自動機が主流で、フルオート機の現場適応には課題が残っています。
人との連携においては、現場での混在作業を円滑に進めるために、ロボットの動作原理を熟練作業者が理解する必要がありますが、そのための教育機会や明確な運用ルールが未整備な現場も多く、協働作業の定着が進みにくい状況です。
このような課題を乗り越えるには、価格の低減はもちろん、AI・制御技術のさらなる高度化と、現場教育やマニュアル整備による実運用体制の強化が重要なカギとなります。
次は、実際にどのような視点でロボットを選べばよいのかを見ていきましょう。
鉄筋結束ロボットの選び方

作業精度とスピード
鉄筋結束ロボットを導入する際にまず注目すべき選定ポイントは、作業精度とスピードです。
これは作業環境の条件、鉄筋の種類やサイズ、そして施工現場の広さや構造の複雑さによってその適正が左右されます。
精度やスピードが不足しているロボットを選んでしまうと、結束の不良や作業の遅延が発生し、結果として工期全体に悪影響を及ぼす可能性があるので気をつけましょう。
特に、大規模な建設プロジェクトや厳格な品質が求められる工事では、この点を重視する必要があります。
精度とスピードを最適化することで、施工品質が向上し、作業効率も改善されるため、最終的には現場全体の生産性向上に寄与します。
操作性とメンテナンスのしやすさ
次に意識すべきは、操作性とメンテナンスのしやすさです。
この項目は、現場の作業員の技術レベルや、日常的なメンテナンス体制、さらにはロボット自体の設計のシンプルさなどが要因として関係します。
もし操作が煩雑であったり、頻繁に止まってしまうようなメンテナンスの手間があると、現場での使用頻度が減り、逆に人力での対応が増えてしまうことになりかねません。
特に、さまざまなスキルレベルの作業員がいる現場や、限られた人員で効率を求める現場では、この選定項目を軽視するべきではありません。
簡単に操作でき、メンテナンスがスムーズに行えることで、現場での稼働率が高く保たれるため、結果として生産性と現場の安定性が両立されるでしょう。
サイズと可搬性
最後に確認しておきたいのが、サイズと可搬性です。このポイントは、現場のスペースや作業環境、鉄筋の配置状態といった要素に影響を受けます。
ロボットが大型で取り回しが難しい場合、狭い場所や複雑な配置がされた現場では、以前よりも作業効率が低下することもあるでしょう。
また、設置や移動にかかる時間が増えることで、工期にまで悪影響が出てしまう可能性もあるのです。
特に狭小地や多階層の現場、または鉄筋の密集度が高い構造物を扱う際には、ロボットの可搬性が作業の可否を分ける要素になります。
コンパクトで可搬性の高いロボットを選ぶことで、狭い場所でも効率的に作業が進められるため、結果として導入効果を限に発揮できより感じられるでしょう。
次のセクションでは、実際にどのようなメーカーが優れた鉄筋結束ロボットを提供しているのかをご紹介します。
鉄筋結束ロボットのおすすめメーカー

ここでは、日本国内で注目されている代表的なメーカーをご紹介します。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- 大成建設 / Taisei
※クリックすると該当箇所まで飛びます
大成建設 / Taisei
建設分野での豊富なノウハウを活かし、鉄筋結束作業の省人化と効率化を目指したロボット技術の開発に積極的に取り組んでいます。その代表的な製品が、T-iROBO Rebar(ティ・アイ・ロボ・リバー)です。自律移動機構と高精度なセンサーを搭載し、鉄筋上を安定して移動しながら結束作業を行う点が特徴となっており、大型の建築現場などでの活用が見込まれています。

