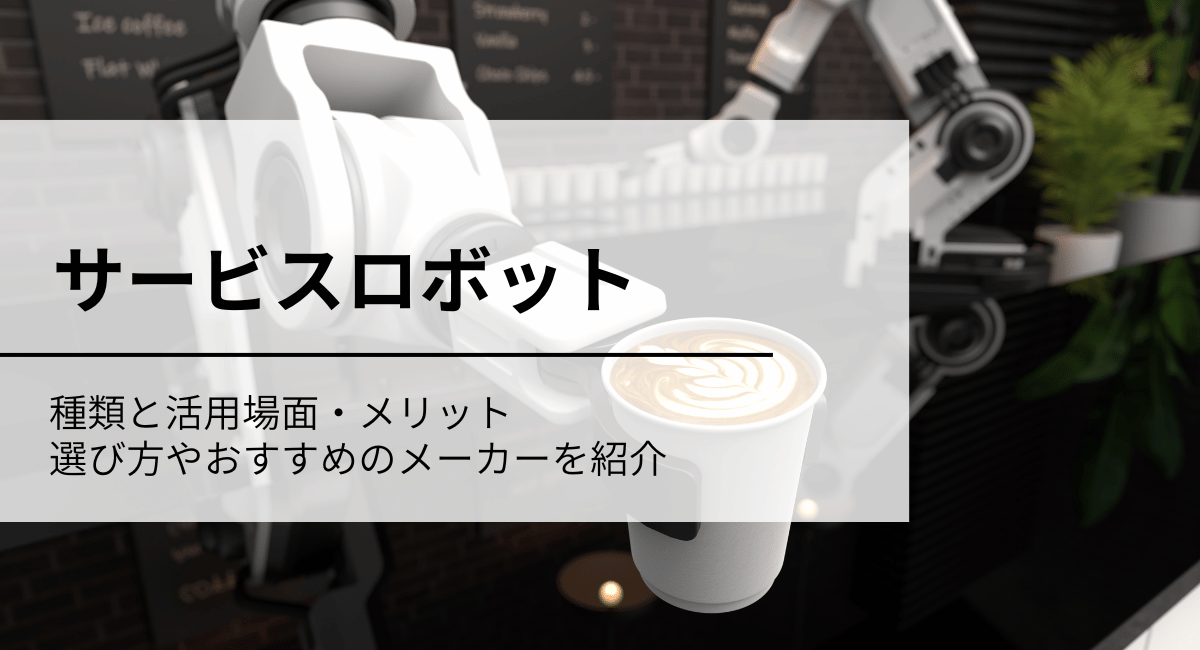警備ロボット
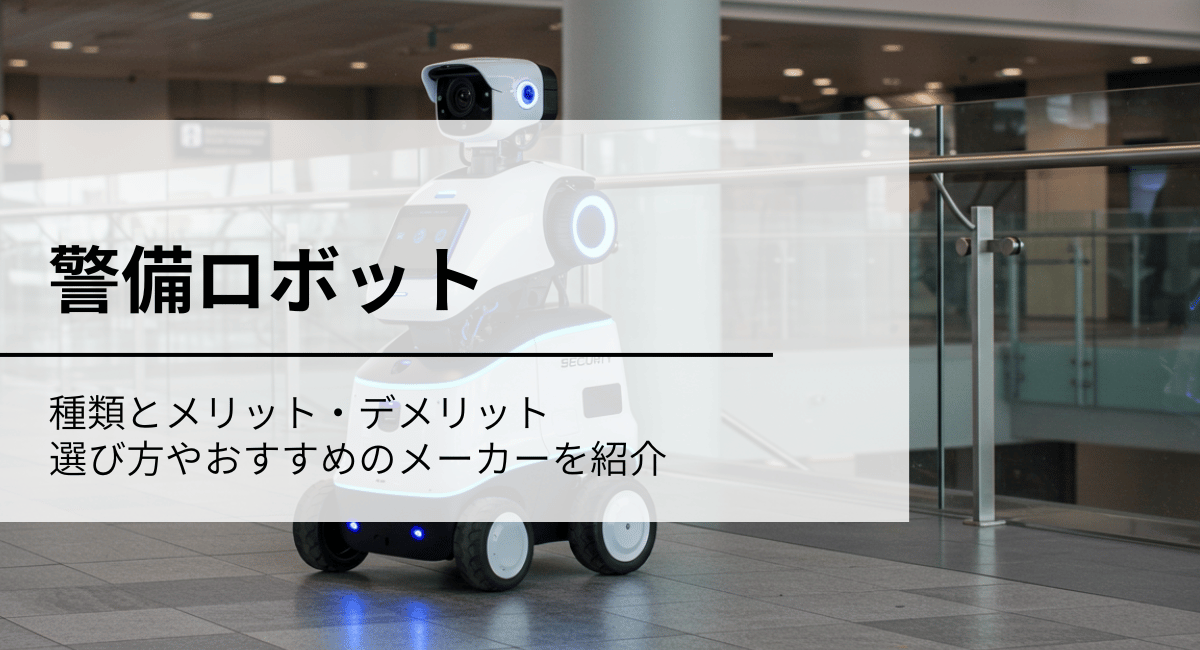
警備業界でも警備員の高齢化や慢性的な人手不足が深刻化する中、施設の安全を維持しながらコストと効率を両立させる手段として警備ロボットが急速に注目を集めています。
すでにオフィスビルや商業施設、物流倉庫などで、自律移動型ロボットやドローン型巡回ロボット、遠隔操作型ロボットが導入され始めていますが、「価格はどのくらい?」「屋外でも使えるモデルは?」「選定時にチェックすべきスペックは?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、RobiZy事務局監修のもと、警備ロボットの基礎知識から3タイプ別の導入効果、メリット・デメリット、7つの選定基準、主要メーカーの比較、そして導入時によくある質問への回答までを網羅的に解説します。
自社の警備体制を強化し、人的リソースの課題を解決するヒントとしてご活用ください。
また、警備ロボットについてご不明点やご相談したいことがありましたら、以下よりお気軽にご相談ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部メーカーとは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
また、JET-Roboticsでは、配膳ロボット以外にもサービスロボットを解説しています。サービスロボット全体について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
警備ロボットとは

警備ロボットとは、カメラ・センサー等を搭載し、巡回・監視業務を支援するロボットで、遠隔操作・自律走行型・ハイブリット型に大別されます。昨今のロボット技術向上により、警備ロボットは、警備員の業務を代行できるレベルまで進化しているといえますが、完全自律走行の警備ロボットは現状ほとんど存在せず、遠隔操作・監視方が主流です。自律走行であるがケースによって遠隔監視センターと連携して運用されるハイブリッド型が増えてきています。
運用上は、異常検知時の判断や対応は人間が行うことが多く、遠隔監視センターのオペレーターが確認・対処・介入できるような体制は必須です。以下のような状況では、そうした遠隔操作が要求されます。
人による警備のデメリットは、警備の品質にばらつきがあることなどが挙げられるでしょう。日々の疲労や、気分の変化に大きく左右され、常に同じ警備ができているとは限りません。
一方のロボットは疲労や気分に左右されず、基本的に入力されたプログラム通りに巡回警備ができます。介入判断などは人間が行う必要がありますが、昨今では画像判定AI技術が進化しており、自動認識機能により倒れている人や不審者などの検知は可能です。センサーで障害物や移動している物を検知し、自律運転もできるようになりました。
機種によっては無線接続、もしくはロボットに搭載されたロボットアームで、さまざまな作業ができます。また、「エレベーターでの階層移動」も可能です。基本的な巡回警備業務は代行できるようになったと言えます。警備ロボットを導入すれば、人的リソースを減らせる可能性があります。活用方法によっては、今まで以上の警備効率を生み出すことも可能です。
では、次の章では警備ロボットを種類ごとに解説します。
3種類の警備ロボットと導入効果

警備ロボットは、運用視点に基づいた分類をすると、以下の3種類に分けられます。警備ロボットのサイズによっては、搭載できる部品に制限があり、監視機能や稼働時間に差があります。ここでは、警備ロボットの各タイプの特徴を説明します。
巡回型(自律・遠隔)
屋内外を走行してパトロールを行う警備ロボットのタイプです。SLAMやAIを搭載することで、人からの直接的な指示なしに自らの判断で最適なルートを走行したり、現状は稀なケースではありますが、マニピュレーター(アーム)などを取り付けてカスタマイズすることで警備中に発生するさまざまな状況に対応できるようになります。
広大な工場や倉庫など、あらかじめ設定されたエリア内を巡回し、施設の安全確保や異常検知を担います。製造現場における人手不足の解消と、24時間365日の均質な警備レベルを実現する、スタンダードな選択肢と言えます。
監視能力
巡回型の警備ロボットは、その躯体を活かして多様なセンサー類を搭載できるのが強みです。深夜の暗闇に潜む不審者はもちろん、稼働中の生産設備や配電盤の異常な発熱といった、火災に繋がりかねないトラブルの予兆も早期に発見できます。異常を検知した際は、即座に防災センターや担当者のスマートフォンへ警報と映像を送信します。
また、LiDAR(ライダー)と呼ばれる高性能センサーで自ら施設内の3Dマップを作成し、人や生産設備、通路に置かれたパレットなどの障害物をリアルタイムで認識し、賢く回避しながら巡回するため、複雑なレイアウトの工場内でも安定した走行が可能です。
機種によっては、音声による警告・威嚇機能や、エレベーターと連携して別フロアへ移動する機能を持ち、警備員が駆けつけるまでの一次対応を任せることで、従業員の安全確保にも貢献します。収集された巡回データ(映像、各種センサーログ)はクラウド上に保存されるため、「いつ、どこで、何が起きたか」を後から正確に追跡・分析し、工場のセキュリティ体制や安全管理プロセスの改善に役立てられます。
稼働時間
多くの巡回型警備ロボットは4時間~8時間程度の連続稼働が可能です。夜間のみ、あるいは休日のみといった、人のリソースを割きにくい時間帯の警備を完全に自動化できます。
最大の特徴は自動充電機能です。バッテリー残量が少なくなると、ロボット自らが充電ステーションへ帰還・ドッキングして充電を開始します。人の手を介さずに24時間体制の警備網を構築できます。わざわざ充電のために担当者が出社する必要はありません。
ただし、注意点として、充電中は巡回警備が停止してしまいます。一台のロボットで工場全体の警備を切れ目なく行うのは難しいため、「複数台を導入し、一台が充電中にもう一台が巡回する」「警備員がカバーする」といった対策を検討する必要があります。
活躍するシーン
オフィスビルや商業施設はもちろん、特に製造業の工場や大規模倉庫でその真価を発揮します。24時間稼働が求められる生産ラインの周辺や、広すぎて人の目では監視しきれない倉庫エリアの巡回に最適です。
警備員を24時間体制で雇用する場合と比較して、警備ロボットは導入コストこそかかりますが、長期的に見れば人件費を圧縮できる可能性があります。プログラムに従って常に一定の品質で巡回業務を遂行するため、異常検知をする際に重要な「見落とし」や「気の緩み」といったヒューマンエラーを防げるのがメリットです。
導入成功の鍵は、警備員とロボットの役割分担を明確にすることです。現状、ロボットだけではトラブル発生時の複雑な判断や対応は困難です。「定型的な巡回と異常の一次検知はロボット」「異常発生時の駆けつけと最終判断は人間」というように、両者の強みを活かしたハイブリッドな警備体制を構築することが重要になります。
定点監視型
定点監視型の警備ロボットは、エレベーター前や出入り口など、重要なポイントに設置して常時映像監視をするタイプです。多くの場合、この定点監視は前述の巡回型の警備ロボットに搭載されており、普段は自動巡回、異常検知時に遠隔操作へ切り替える、といったハイブリッドな運用が主流です。
完全定点の場合もありますが、通常はロボット自体は定位置に固定されており、カメラ部分だけが首振りで稼働する仕様のものが多く見られます。カスタマイズでレール上を一定範囲の距離だけ動くものも存在します。
監視能力
基本性能は巡回型の警備ロボットに準じ、全方位カメラや赤外線カメラ、音声マイクなどを搭載しています。巡回型とは異なり、特定地点における見張り・異常検知・記録に強みがあるのがこのタイプです。
巡回型はエリアを動き回るため、監視対象から離れる時間がどうしても発生します。一方で定点監視型は一定の箇所に設置されているので、死角が生まれにくく、連続的に監視できます。また、経時的な映像・音声データを蓄積できるというのも定点監視型の利点です。
稼働時間
稼働時間は巡回型の警備ロボットと同様に4〜8時間程度が目安です。
巡回型とのハイブリッドの機種であれば、自動充電機能も搭載されていますが、いざという時に確実に稼働できるよう、運用計画に合わせた充電管理が求められます。
活躍するシーン
駐車場や病院、学校などの出入り口・ゲートや金庫室、サーバールームなど重要施設前、受付・ロビーなど、人や物の流れが集中する出入口やゲート、資産や機密を守るべき重要地点、不特定多数が出入りする公共性の高い場所で効果を発揮します。
不審者の侵入、関係者以外の立ち入り、持ち出し行為などを検知できたり、ログも記録できるため、防犯上の効果だけでなく、実際にトラブルが発生した際にも効果的です。
ドローン型
ドローン型の警備ロボットは、高所・広域監視用の警備ロボットです。地上の障害物の影響を受けないため、圧倒的な監視範囲の広さと機動力の高さが魅力です。
AIや高性能カメラを搭載しており、飛行速度は時速10〜50kmに達するモデルもあります。広大な敷地の端で異常が発生した場合でも、警備員が車で向かうより速く現場に到達し、初期状況をリアルタイムで映像伝送できます。
監視能力
高倍率ズームや4K撮影が可能なカメラ、そして夜間用の赤外線カメラを搭載し、昼夜を問わず上空から鮮明な監視映像を取得します。
地上の巡回型ロボットでは死角になりがちな、屋外に山積みされた資材の上や、建物の屋根、巨大なプラント設備の上部まで、人の目では届かない範囲をくまなくチェックできます。
画像認識AIが不審者や不審車両を自動で検知・追跡するため、警備員の監視業務の負担を軽減します。捉えた映像はリアルタイムで共有され、即座の状況把握と対応指示が可能です。
衝突リスクについては、高性能センサーが周囲の空間を立体的に認識し、屋外の樹木や電線、工場敷地内のクレーンといった障害物を自動で回避する機能が搭載されており、安全な航行を実現します。
稼働時間
一気に見回るという意味では優れていますが、連続飛行時間は巡回型に比べて稼働時間が短く、屋内利用や経路指定の自由度といった点では成約があります。自動で離着陸と充電を行う専用の「ドローンポート(基地)」を設置することで、実質的な連続運用が可能になります。
一台の飛行時間が短くても、その機動力は大きなアドバンテージです。特に不審者の追跡能力はに高く、警備員が直接対峙する前に、ドローンが安全な距離から追跡を続けることで、警備員の安全確保にも繋がります。
活躍するシーン
敷地面積が広大な化学プラントや大規模工場、屋外の資材置き場、メガソーラー施設などで特に有効です。人の巡回では半日かかるような広範囲も、ドローンなら短時間で完了できます。
また、警備用途だけでなく、工場の屋根や煙突、プラントの高所配管といった設備の劣化状況を定期的に点検するといったメンテナンス業務にも応用可能です。足場を組むコストや高所作業のリスクを削減できるという、副次的なメリットも期待できます。
なお、ドローンを飛行させる場所や方法によっては、航空法に基づく飛行許可・承認の申請が必要になる場合があります。導入を検討する際は、専門家やメーカーに確認することが重要です。
以上の3タイプ、巡回型と定点監視型、ドローン型を使い分けることで、警備の効率と安全性を最大化できます。
次の章では、警備ロボットを導入することで得られるメリットと、注意すべきデメリットを解説します。
警備ロボット導入のメリットとデメリット

スペックだけ並べて稟議書を提出しても、決裁者には警備ロボットの魅力がイメージできていないかもしれません。ここでは、警備ロボット導入時のメリットとデメリットについて触れていきます。
警備ロボットのメリット
警備ロボットを導入すると、警備品質が安定しやすくなります。
人の場合、疲労が蓄積して警備品質は落ちることもあります。また、気分の波もあるため、毎日同じパフォーマンスで警備業務を実施できない可能性があります。
警備ロボットを活用すれば、機械のメンテナンスさえ行っていれば、24時間365日、定時巡回を安定した品質で実現できる点が魅力です。
24時間体制の安定した警備が可能
警備ロボットは、休まず、夜間や休日でも、常に同じパフォーマンスを出せます。
ただし、警備ロボットは、充電が必要です。長期時間稼働が可能な巡回型警備ロボットでも4時間〜8時間程度を要します。バッテリー残量が少なくなれば自動的に充電ステーションに戻るようにプログラムされています。充電ステーションさえあれば24時間体制での警備が可能です。
充電中でもカメラ監視をすることはできますが、動くことができません。警備ロボット一台での対応はまだ難しく、充電時間を考慮した勤務時間設定が必要です。
警備品質のバラツキをなくす
警備ロボットを導入することで、ヒューマンエラーによる警備不足を解消し、安定した警備品質が期待できます。警備業務の効率が向上できます。
警備を人に頼った場合、巡回ルートを省略や、思い込みによる間違いが「絶対に起きない」とは断言できません。夜間の見落としや、疲労による見逃しのリスクは、常にあるものと考えるほうが自然です。
警備ロボットは、プログラムされたルートを自動巡回。広範囲のエリアを一定のパターンで監視し続けます。さらに、画像認識AIや異常検知システムにより、異常や不審者を自動で識別し、リアルタイムで警報を発することが可能です。
また、警備員一人では、同時に監視できるエリアは限られています。大規模施設や複数のエリアを効率的に一人で監視するのは困難です。警備員と警備ロボットが連携を取れば、人的リソースを増やさず、広範囲の警備ができます。
高度なカメラ・センサーや映像解析技術による精密な監視
警備ロボットには複数のカメラやセンサーが搭載されているため、人間の目では捉えにくい微細な異常や、変化を検知できます。例えば、赤外線カメラによる夜間の監視、熱感知カメラによる火災の早期発見、顔認識技術による不審者の特定などが可能です。広範囲を均等に監視できることも警備ロボットの強みです。
人の有効視野角は約70度で、周囲の状況や警備員の精神状態で、実際に監視できる角度は狭くなり、重要な異常を見逃すリスクがあります。しかし、ロボットは全方位カメラや高性能センサーを活用し、エリア全体を均等に監視することが可能です。エラーやトラブルが発生しない限り、見落としは考えにくいです。
人的リソースの節約とコスト削減
警備ロボットは一度プログラムができてしまえば、導入した日からプログラム通りの警備が可能です。「教育」や「慣れ」は必要なく、導入初日から高いパフォーマンスを発揮します。
警備員だけに警備を頼れば、夜間や休日の勤務には高い人件費がかかります。また、新任の警備員の場合は「教育」や「慣れ」も必要なので、すぐに能力が発揮できるわけではありません。狙いの警備品質に至るまでには、時間がかかることが予想されます。
運用方法次第ですが、警備ロボットを導入すれば大幅なコストカットができる上、警備品質の大幅な向上が期待できます。
以上が主なメリットですが、ほかにも以下のようなメリットが考えられます。
警備ロボットのデメリット
警備ロボットも万能ではありません。デメリットも存在しています。ここでは、警備ロボットのデメリットについて触れていきます。デメリットを上手く利用して、最適な警備体制をしてください。
現場の状況判断が人間よりも劣る
警備ロボットは、まだ人間のように柔軟かつ迅速に適応・判断することができません。AIや機械学習アルゴリズムが、複雑な状況や予期せぬ事態に対応していないためです。現場の状況判断能力は、警備員のほうが上だといわれています。
警備ロボットは緊急時でも、プログラムされた指示や学習したパターンに従います。適切な判断を下せず、緊急対応が取れないこともあります。最悪の場合、人的被害や物的損害に発展することが懸念されます。
ロボットが人間と同じ判断ができないのは、仕方ありません。警備ロボットのデメリットを補うためには、警備員との連携が必要不可欠です。今までの警備体制とは異なった、新たな仕組み作りが求められます。警備の人的リソースを、完全にゼロにするのは難しい点を、決裁者に説明したほうがよさそうです。
突然の停止や機能的なトラブルの発生
警備ロボットも機械なので、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。ソフトウェアのバグ、ハードウェアの故障、外部からの干渉などにより停止してしまう場合があるため、注意が必要です。
また、警備ロボットは機械なので、センサーの誤認識・誤検知して停止してしまう可能性もあります。不必要な警報が発生し、利用者や関係者に不安や混乱をもたらしてしまうこともあるかもしれません。
一度エラーを起こすと、ロボット自身で自動復旧するのは困難です。復旧には人の手でエラーをリセットして、再スタートしなくてはいけません。監視業務が停止してしまえば、事故や犯罪が発生する可能性があります。
少しでもトラブルを避けるためには、警備ロボットの定期メンテナンスが欠かせません。また、正常に稼働しているかを定期的に確認する必要もあります。加えて、トラブル発生時、ロボット停止時には、速やかに復旧対応できるように、社員教育も必要です。
導入コストがかかる
警備ロボットは、高度な精密機器を使用しています。購入時のコストは、数百万円〜数千万円程度で高額になりやすいです。小さい規模の企業が導入するには、ハードルが高いかもしれません。
導入金額が高いと感じる場合には、リース契約も視野に入れてください。各メーカーでは、多くの企業でも導入できるようにリース契約を実施しています。一ヶ月15〜30万円程度で、警備ロボットが導入可能です。
警備ロボットの導入費用は、新入社員の初任給と同程度か、それよりも少し高い程度です。一度プラグラムを組んでしまえば、複数の警備員を雇用する必要がなくなる可能性があります。人件費を削減でき、警備品質も向上します。費用対効果をよく吟味した上で、導入してください。
ほかにも、運用において以下のようなデメリットが考えられます。導入検討する際には頭の片隅においておくとよいでしょう。
次の章では、7つの選定基準から警備ロボットの選び方を解説します。自社にとって最適な警備ロボットの導入をする際、是非ご参考にしてください。
7つの選定基準 | 警備ロボットの選び方

効率的・効果的な警備をおこなうには「どのような警備をしたいのか?」を明確にする必要があります。警備ロボットには、さまざまな機能が搭載されていますが、効果的に使えなければコストの無駄になってしまいます。セキュリティの質を最大限に高めるために、事前に綿密な計画を練りあげましょう。
連続稼働時間で選ぶ
ロボットの機種によって連続稼働時間が違うため、選ぶ機種によって運用サークルが変わります。
巡回型ロボットなど連続稼働時間が長いロボットは、一回の充電で4~8時間の稼動ができます。警備員と連携すれば、夜間や休日を含めた24時間体制の監視が可能です。警備員が巡回する回数や、巡回エリアを減らすことができ、人的リソースを効率的に利用できます。
一方、ドローン型警備ロボットのような稼働時間が短いロボットは、特定の警備に特化しています。一回の充電で稼働できる時間は、わずか数十分。複数台の導入を検討しなければ、24時間の警備は難しいかもしれません。広範囲の監視範囲や機動性の高さを活かした運用方法を模索する必要があります。
価格で選ぶ
警備ロボットの価格で選ぶ場合、警備員と警備ロボットのコストを比較し、費用対効果を確認する必要があります。
警備ロボットの導入には、ロボットを購入する場合と、リース契約の場合にわかれます。リース契約は、ロボットの性能にもよりますが月額15万円~30万円程度。購入の場合には、数百万円〜数千万円程度かかります。
ロボットの性能は、価格相応の能力です。しかし、高級な警備ロボットだからといって、企業のニーズに合った性能をもっているとは限りません。有効に活用できなければ、コストの無駄です。目的に応じた警備ロボットを選定することがおすすめです。
また、警備ロボット導入の成果に「集客・企業イメージ」アップを盛り込むのであれば、ロボットの外観にもこだわりたいところです。費用はアップしますが、メーカーによってオプションで外観・カラーリング変更が可能です。企業のイメージ・知名度がアップすれば、売上アップを見込めるかもしれません。
屋外稼働の可否で選ぶ
屋外の商業施設や、工場の外を警備する際には、雨、風、極端な温度変化などの厳しい自然環境に耐える必要があります。屋内専用のロボットを屋外で使用すれば、性能を発揮できないだけではなく、最悪、故障してしまうかもしれません。屋外で使用する場合には、専用のロボットを選んでください。
段差踏破能力で選ぶ
巡回型警備ロボットを導入する際には、巡回エリアに大きな段差がないかも事前に調査しておきましょう。段差踏破能力は、各メーカーによって異なりますから、カタログスペックを確認してください。必要に応じて傾斜のゆるいスロープの設置が求められるかもしれません。
本体サイズで選ぶ
大型ロボットのメリットは、性能を高められる余地があることです。高機能なカメラやセンサーなどのさまざまな部品や、大きな部品も搭載できます。アームなどのオプションも搭載しやすくなります。
一方で、小型ロボットは、監視するエリアや通路が狭い場合に有利です。大型ロボットと比較すると、搭載できるカメラやセンサーには限りがありますが、特定の警備に特化した運用が可能になります。警備体制を十分に吟味すれば、小型ロボットでも対応できてしまうかもしれません。
以上を踏まえて、以下の観点からサイズについては考えるとよいでしょう。
本体重量で選ぶ
本体重量は、ロボットの強度や移動速度に影響します。重く、頑丈であれば移動速度は遅くなりますが、トラブルで壊れる確率やロボット自体を盗難されるリスクは低くなります。
ところが、安全性と扱いやすさはどうでしょうか。巡回型警備ロボットの重量は15~160kg程度まで幅があります。何かのトラブルで重いロボットが転倒し、周りに人がいた場合、怪我をさせてしまうかもしれません。
さらに、転倒時には自身の衝撃で精密機器が破損してしまう恐れがあります。警備員や現場スタッフだけでは、転倒したロボットを起こせないことも考えられます。各メーカーで転倒対策は十分におこなっていますが、万が一のケースは想定しておく必要があります。
移動速度で選ぶ
緊急事態への迅速な対応や、広範囲を監視する能力が欲しい際には、移動速度がポイントです。使用場所によって移動速度が速い警備ロボットを選定してください。
屋外で使用する場合、地上の障害物の影響を無視できるドローン型警備ロボットが適しています。時速10〜50km程度の飛行速度で、即座に現場に駆けつけられます。走って逃げる不審者でも追跡可能です。機体も飛行性を重視し、軽量で強度は低いですが、監視範囲の広さと機動力は、巡回型ロボットの比ではありません。
屋内では、巡回型ロボットが候補に挙がります。時速は、0.4km~6km程度。成人男性の平均歩行速度が時速2~3km程度といわれていますから、オフィスビルでは十分な速度を持っていると言えます。
また、目的によっては「より遅く、慎重」に作業できるほうが適している場合があります。ロボットアームを駆使して、遠隔操作で精密作業をおこなう際には、移動速度は妥協し、精密な作業ができるロボットを選定するのがおすすめです。
次の章では、警備ロボット導入の際に気をつけなければならない現行の法律について紹介します。
関連する法制度と警備ロボットについて
警備ロボットを利用する際には、いくつか知っておく必要のある重要な法制度があります。この章では、そうした警備ロボットに関連する法制度について紹介します。
警備業法
現状の警備ロボットの活用において、警備ロボット自体が物理的に何かを守るわけではないことは説明しました。つまり、カメラやセンサーで映像や情報を収集し、警備員が判断、対応するという構造が一般的です。このとき、その映像やセンサーデータをもとに判断、通報、対処する者が「警備業務従事者(警備員)」としての要件を満たす必要があります。
要するに、警備ロボットが提供する監視情報を使って業務判断や対応をする人間が存在する場合、その人は警備業者でなければなりません。特に、遠隔操作・遠隔監視センター側のオペレーターは、警備業の認可を持つ業者が担う必要があります。外部BPOやIT事業者に「遠隔監視業務」だけを委託することは基本的に禁止されていると考えましょう。
映像のリアルタイム監視と異常判断、インシデント通報、そして現場対応指示は警備業法における監視業務に当たるので、警備業法に基づき登録された警備業者が実施するようにしましょう。ただし、警備ロボットの自律巡回は機械制御となるため、警備業法の直接適用外です。そのため、この部分はロボットメーカーやアルバイトなどが代行することはできます。
消防法・建築基準法
ロボットの常設設置物、たとえば、自動充電ドックや待機場所が、消防設備や避難経路と干渉してしまうケースがあるため、以下の点については配慮が必要です。
以上の理由から、特にオフィスビルや商業施設、病院などは施設の防火管理者と事前協議が必要になります。設置場所の図面確認や消防点検報告書との照合も望ましいので、必要であれば、設置場所を消防設備設置区域外にずらすなどの手配を行いましょう。
また、警備ロボットと火災報知器との連携が話題になることも近頃多くなってきていますが、現状直接連動はしないので、火災発生時の自動停止・退避機能、または遠隔監視センターによる制御を基本としているところが多いです。
個人情報保護法
警備ロボットはカメラ・マイク・位置情報を用いて個人情報を取得・保存・送信する可能性があります。個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことであり、映像・音声・名前・顔認証ログなどがそれに当てはまります。
たとえば、カメラ映像が録画される場合、原則として何のために撮っているのかという利用目的を明示する必要があります。また、店舗やオフィスなど、不特定多数が入る場所では「防犯カメラ作動中」などの掲示によって録画されていることを周知することが一般的です。
同様に、クラウド記録される場合は、保存先・アクセス制限・暗号化・保存期間の定義が必要になり、GDPR対応も検討する必要があります。AWSなど外部サーバーに保存する場合は、クラウド事業者のセキュリティ要件を確認しましょう。
次の章では、警備ロボットの製造・販売を行うメーカーを紹介します。気になるメーカーや製品があればお気軽にお問い合わせください。
警備ロボット主要メーカーを解説

昨今のロボット技術の向上により、国内で警備ロボットを取り扱うメーカーが増えてきました。ここでは、最前線でロボットを開発・製造している主要メーカーを紹介します。
以下でご紹介する製品の中には、補助金を活用できるものが一部ございます。詳しい情報をご希望の方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
※JET-Robotics問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- セントラル警備保障 / CSP
- シークセンス / SEQSENSE
- オムロン ソーシアルソリューションズ / OMRON SOCIAL SOLUTIONS
※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。
セントラル警備保障 / CENTRAL SECURITY PATROLS
| 会社名 | セントラル警備保障 / CENTRAL SECURITY PATROLS |
| 創業年 | 1966年 |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル |
| 概要 | 常駐警備、機械警備、輸送警備、機器販売及び工事など |
セントラル警備保障は、創業の理念「仕事を通じ社会に寄与する」「会社に関係するすべての人々の幸福を追求する」をあらゆることの基盤として事業を行っています。これまでに培ってきたノウハウを基に、安全・安心・快適な社会づくりに向けて「人」と「技術」が最適に融合した警備サービスを提供しています。
警備ロボットとして、「C-SParX(シースパークス)」を展開しています。正確な自律走行と高度な防犯・警備機能を実装し、警備業務の効率化と品質の向上を実現します。また、高性能エッジPC(GPU搭載)にAI画像解析機能(ディープラーニング)を実装し高い精度の異常検知機能を実現しました。
駅や空港、商業施設、テナントビル、工場、そのほか防犯が必要とされるフィールド全般が利用シーンです。警備機能として、多言語の音声案内や異常発見時のブザー音、フラッシュライトによる注意喚起や威嚇など、音や光を効果的に使用できます。C-SParXに組み込まれている通話アプリで防災センターなどの遠隔地との通話も可能です。
シークセンス/SEQSENSE
| 会社名 | シークセンス/SEQSENSE |
| 設立年 | 2016年 |
| 本社 | 東京都中央区明石町6-4 ニチレイ明石町ビル5F |
| 概要 | 自律移動型ロボットおよび関連製品の開発を行う |
シークセンスは、独自開発の 3D LiDARとクラウド連携型自律移動アルゴリズムを核に、ビル内外の死角をなくす巡回警備を実現するロボット専業メーカーです。
同社の「SQ‑2」は、頭頂部に搭載した回転式3D LiDARで環境を高密度マッピングし、エレベーター連動による多層階巡回や遠隔操作・レポート自動生成をクラウド上で実現します。巡回・立哨・動哨を1台でこなし、音声アナウンスやライブ映像配信などオプションも豊富です。
同製品は、現在までにオフィス・商業施設・空港など国内30超の物件で稼働し、警備員の負担軽減と警備品質向上を実現しています。
オムロン ソーシアルソリューションズ / OMRON SOCIAL SOLUTIONS
| 会社名 | オムロン ソーシアルソリューションズ / OMRON SOCIAL SOLUTIONS |
| 創業年 | 2011年 |
| 本社 | 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F |
| 概要 | IoT、AI・ロボティクスなどの最先端技術、ソフトウェア、運用・メンテナンスのトータルサービス |
オムロン ソーシアルソリューションズはこれまで独自のオートメーション技術により、駅務自動化システムをはじめ、世界初・日本初の社会公共システムを数多く生み出してきました。社会課題をいち早く捉え、最先端技術、ソフトウェア、運用・メンテナンスのトータルサービスで安心・安全・快適な社会づくりに貢献します。
警備ロボットの導入で、警備の人的リソースを改善しましょう

警備業界は雇用環境や業務内容の影響により、人材不足が深刻な問題になっています。加えて、高齢化が進み、ますます厳しい状態が続くことが予想されます。企業の安全を守るためには、人とロボットが協力していく必要がありそうです。
警備員が人である以上、疲労や気分の変化による警備品質のバラツキに対策を打つのは、大変難しいことです。ヒューマンエラーをなくすために、常に一定品質で警備できる警備ロボットに頼ることも検討してみてください。
警備ロボットは、警備員の弱点を補う機能が搭載されています。上手な警備体制を構築できれば、効率のよい警備が可能です。警備ロボットは、既にオフィスビルや空港に導入され、実績を上げています。
よくある質問

はじめて警備ロボットを導入する企業担当者は、どこから手を付けたらいいかわからないかもしれません。高価な買い物になりますから、失敗は避けたいところではないでしょうか。ここでは、導入検討段階でよくある質問について触れていきます。参考にしてください。
無線インターネットへの接続は必要ですか?
警備ロボットは、カメラやセンサーで得た情報を、警備室に送信し共有しています。使用には無線インターネット環境が必要です。ただし、警備ロボットによっては、モバイルルーターでも対応している機種があります。
夜間に警備ロボットが巡回するには電気をつけておくべきでしょうか
多くの巡回型・ドローン型警備ロボットには、LEDライトや赤外線カメラが搭載されています。電気をつけることなく、夜間でも十分に警備が可能です。
導入費用はいくらですか?
各メーカーによって異なりますが、リース契約では月15~30万円程度。購入時は、数百万円〜数千万円程度かかるといわれています。メーカーによっては、リース契約のみしか実施していない場合があります。詳細は見積もり時にメーカーに確認してください。
どの警備ロボットでも屋内外どちらも使用可能でしょうか
警備ロボットによっては、屋外用に設計されていません。屋内専用のロボットは、屋内で使用してください。もし、誤った使い方をして破損した場合には、メーカーの保証対象外になる可能性があります。
エレベーターが無線対応していません。どうすればいいですか?
ロボットアームを搭載している警備ロボットがおすすめです。無線でエレベーターを操作できなくても、ロボットアームを用いて手動でエレベーターに乗れます。