壁面走行ロボット
壁面走行ロボットとは? おすすめメーカーや事例、仕組み、ほかの点検ロボットとの比較も
壁面走行ロボットは、建物やインフラ設備の垂直面を自走しながら点検作業を行うロボットで、高所作業の安全性向上や省人化に貢献する先進技術です。
しかし、「どのメーカーがどんな製品を出しているのか分からない」「導入事例や技術の違いを比較したい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、壁面走行ロボットを手がける国内主要メーカーについて、それぞれの強みや製品の特徴、導入実績を詳しく紹介します。
また、壁面走行ロボットの基本情報や事例、仕組み、メリット・デメリット等も解説するのでぜひご覧ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
目次
最近の更新内容
2026/1/22更新 企業情報の更新
壁面走行ロボットの基本情報を解説! 仕組みや活用事例も紹介

壁面走行ロボットとは、壁や垂直面を自律的または遠隔操作で走行しながら点検を行うロボットです。
工場設備や建築構造物、プラント、橋梁、ダムといったインフラ構造物の外壁や高所など、人手での点検が困難または危険な場所の点検業務を効率化する目的で活用されています。
点検対象は、既に稼働している構造物や設備であり、ある製品や部品が設計通りに製造されたかどうかを確認する「検査ロボット」とは異なる分類に属します。
壁面走行ロボットの仕組みは、壁面に密着して落下せずに移動するための吸着機構(磁力、真空、ファンなど)と、移動機構(クローラー、足、ホイールなど)を組み合わせたものが主流です。
加えて、カメラやセンサー、AI画像解析などを搭載し、異常箇所の早期発見やデータの自動取得を実現しています。
近年では、鉄塔の腐食検査、プラントの配管溶接部の劣化確認、ビル外壁の打診点検の代替など、用途が拡大しており、点検業務の省人化・安全性向上に貢献しています。
基本情報が分かったところで、次章では、壁面走行ロボットを種類分けして紹介します。
壁面走行ロボットは活用技術で細かく種類分けできる

壁面走行ロボットは、「どのように壁に吸着するか」と「どのように移動するか」の2つの技術的要素で構成されており、それぞれの方式を理解することで、用途や環境に適した壁面走行ロボットを選定しやすくなります。以下では、この2つの視点に分けて分類します。
壁面に吸着する方式(吸着機構)
壁面にくっついているための技術は、対象壁面の材質や設置環境に応じて最適な方式を選ぶ必要があります。
- 磁気吸着方式
- 真空吸着方式
- 負圧ファン方式
- バキュームチャンバー方式
金属製の壁面に対して磁力で密着する方式で、強力な保持力と低消費電力が特徴です。鉄鋼構造物や船舶などに適しています。
吸盤とポンプによって陰圧を生み出し、コンクリートやタイルなど非磁性体にも吸着可能です。凹凸のある面への対応力が求められます。
高速ファンで負圧を作り、壁面に吸着する方式です。軽量化が可能で、垂直面や天井面にも適応します。
密閉されたチャンバー内を減圧することで壁に吸着する方式で、吸着面の材質を問わず安定性に優れます。
壁面を移動する方式(移動機構)
吸着した状態でどうやって移動するかという点も、壁面走行ロボットの作業性能を左右する重要な要素です。
- クローラー型
- ホイール型
- 足つき型
- 吊り下げ式ウインチ移動型
走行用ベルトのような履帯で移動するタイプで、凹凸や段差のある面でも安定した走行が可能です。走行安定性と荷重耐性に優れています。
タイヤやローラーで走行する方式で、軽量・高速移動が可能ですが、凹凸面には不向きです。滑らかな壁面に適しています。
昆虫のように複数の脚を動かして壁面を這うように移動する方式で、曲面や障害物の多い面でも柔軟に対応できます。制御は複雑ですが、高い適応力が得られます。
上部からケーブルで吊り下げ、昇降や左右移動をウインチ制御する方式です。足場を設置できない場所や高所での作業に向いています。
上記の説明で、自社に必要そうな吸着技術と移動機構を持った壁面走行ロボットの目星はついたでしょうか?
さらに詳しい製品の選び方に移る前に、壁面走行ロボットを他の点検ロボットと比較した際のメリット・デメリットを見ておきましょう。
他の点検ロボットと比較した際のメリット・デメリット

壁面走行ロボットは、地上走行型や空中ドローン型と比較して、特定の条件下で高い点検効率と安全性を発揮します。一方で、導入環境や目的により適・不適が分かれるため、他の点検ロボットとの違いを理解することが重要です。
本章では、壁面走行ロボットと点検ロボットを比較した際の、壁面走行ロボットのメリット・デメリットを解説します。
まずはメリットからです。
続いて、以下がデメリットです。
メリットとデメリットの両面を理解したうえで壁面走行ロボットを導入することで、導入後にイメージとのブレが少なくなるでしょう。
壁面走行ロボット以外の点検ロボットについても詳しく知りたい方は、点検ロボットについて網羅的に解説している以下のコンテンツをご覧ください。
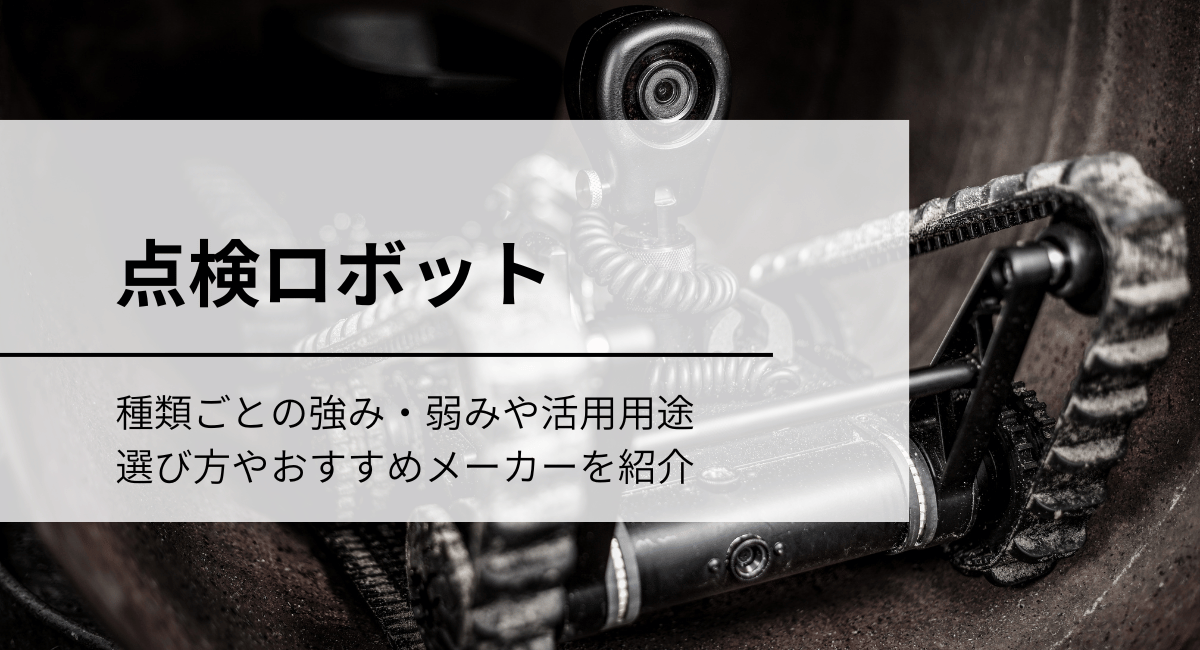
次章では、壁面走行ロボットの選び方を詳しく見ていきます。
壁面走行ロボットの詳しい選び方を紹介

本章で、壁面走行ロボットの詳しい選び方を理解して、自社に適した製品を選べる状態にしておきましょう。
壁面材質や傾斜に応じた走行方式で選定する
壁面走行ロボットを選定するうえでまず重要になるのが、壁面材質や傾斜に応じた走行方式の選択です。走行方式は、対象となる壁面の材質が磁性体か否か、凹凸の有無、傾斜の角度といった要因によって左右されます。
これらの要素を無視して選定してしまうと、壁面に適合せず、走行中の脱落や移動不能といった問題が発生する可能性があります。特に、複数の異なる壁面材質や角度が混在する建築物やインフラ設備を点検する際には、この観点を重視する必要があるでしょう。
最適な走行方式の壁面走行ロボットを選定できれば、高所や垂直面といった過酷な条件下でも安定した走行が実現でき、より安全かつ効率的な点検作業が可能になります。
使用環境に対する耐候性・防水防塵性で選定する
壁面走行ロボットの選定において、使用環境に対する耐候性や防水・防塵性能も重要な視点です。稼働する現場の気象条件や、対象となる壁面の設置場所(屋外、海沿い、高所など)は、機体の耐環境性を決定づける主要な要因となります。
この点を軽視して壁面走行ロボットを選定してしまうと、粉塵や雨風により機器が停止したり故障したりして、予定されていた点検作業が中断されたり、やり直しを余儀なくされるリスクが高まります。
特に、橋梁やトンネルの出入口、ダム、ビルの外壁など、風雨や埃の影響を受けやすい環境下で使用する場合には、この性能を重視すべきでしょう。
環境への耐性を備えた壁面走行ロボットを選定すれば、天候や周囲の環境に左右されることなく、計画通りの点検業務を安定して進めることが可能になります。
点検目的に応じたカメラ・センサー構成で選定する
壁面走行ロボットを選ぶ際には、点検目的に応じたカメラやセンサーの種類、解像度、解析機能の選定も大切です。
必要とされる仕様は、ひび割れの深さ、腐食範囲の検出、肉厚測定の精度などの検査要件や、写真だけでよいのか、定量的なデータ出力まで求められるのかといった報告レベルによって異なります。
こうした要件に合わない壁面走行ロボットを選んでしまうと、異常の検知漏れや記録の不備が生じ、点検のやり直しや見落としのリスクが高まります。特に、公共インフラの保守や、第三者機関への報告義務を伴うような高精度な点検を行う場合には、適切なセンサー構成を重視すべきです。
目的に合った機能を備えた壁面走行ロボットを導入すれば、信頼性の高いデータが取得でき、点検の品質向上と業務の効率化が同時に実現します。
次章では、おすすめの壁面走行ロボットメーカーを紹介します。気になるメーカーがあれば問い合わせをしてみてください。
当編集部おすすめの壁面走行ロボットメーカーを紹介! 各社を比較して強みも解説

以下が当編集部おすすめの壁面走行ロボットメーカーです。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- 住友重機械工業 / Sumitomo Heavy Industries
- ステラ技研 / Stella RTec
- アイ・ロボティクス / iRobotics
※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。
住友重機械工業 / Sumitomo Heavy Industries
鉄鋼壁面走行ロボットとして、鉄鋼曲面を吸着走行する新型ロボット機構の開発を行いました。2つの回転軸によって回転可能な磁石を内蔵した中空の球状車輪を新たに考案し、従来のロボットでは困難だった鉄鋼曲面の吸着走行を容易に行えるロボットです。従来人手に頼らざるを得なかった曲面上での溶接作業などでの活用が期待されています。このロボットにより作業者の負担が軽減され、より安全な次世代の重工製造現場の実現が目指せるでしょう。
ステラ技研 / Stella RTec
経年劣化が進む社会インフラの保全対応のため、点検補修の各種アプリケーションに使用可能な高層壁面走行プラットフォームとしてのタイル・コンクリート垂直壁面などの自走ロボットを開発して提供している会社です。同社が開発した壁面走行ロボットは「天龍Ⅲ(TENRYU)」や「Tenryu-Vmin」などがあります。天竜Ⅲは、真空吸着によってコンクリートなどの壁面を自走できることが強みです。
アイ・ロボティクス / iRobotics
技術的にはさまざまなことが実現段階な現代において、その技術を実際に社会で使うための「社会実装」に挑戦している会社です。同社は、「壁面・高所作業ソリューション」の提供や、光洋機械産業との共同開発で「スパイダーロボ」などを扱っています。スパイダーロボはウインチを利用した3D壁面作業システムと昇降式足場を組み合わせたメンテナンスロボットで、壁面の点検、清掃、塗装などの作業を行うことができます。
導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
壁面走行ロボットの製品はまだありません。
