電子顕微鏡
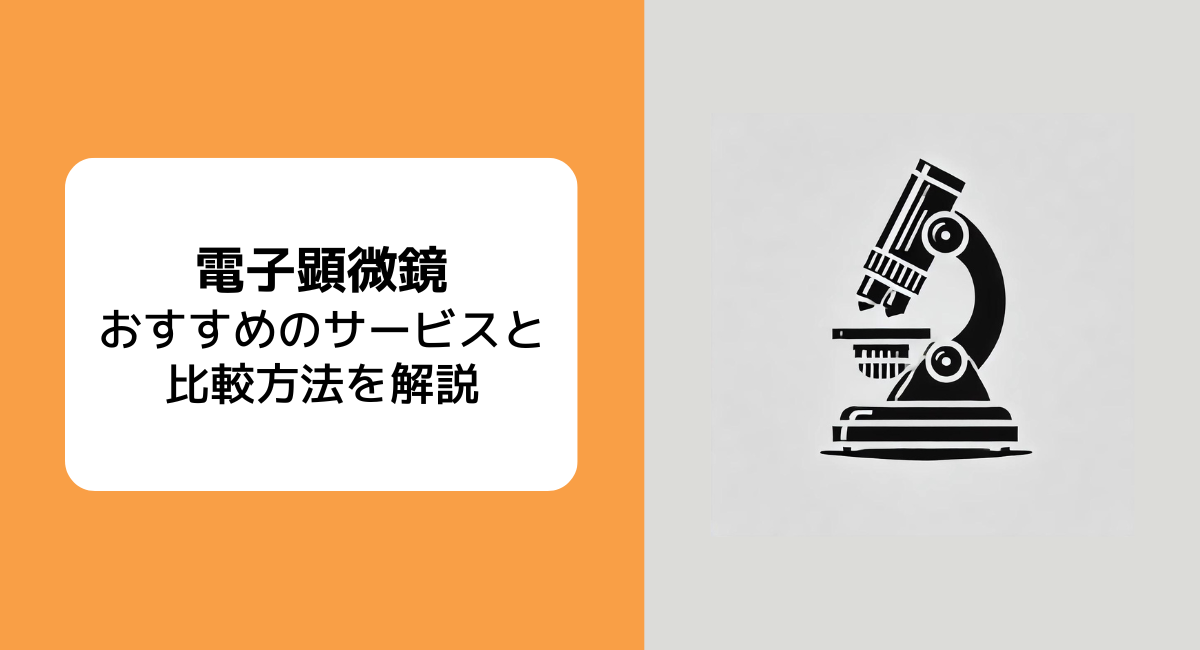
半導体などの電子機器や、ナノテクノロジーの発展により、電子顕微鏡の高倍率、高解像度の機能が必要になる場面が増えています。一方、電子顕微鏡の活用方法や活用シーンについて詳しく知っている人は少ないでしょう。
顕微鏡の中でも高性能な電子顕微鏡は、オーバースペックになる恐れがあるため、正しい選定が大切です。
この記事では2種類の電子顕微鏡や、それぞれ適した利用シーンについて解説します。電子顕微鏡の導入を検討している方はぜひ最後まで読み参考にしてください。
2種類の電子顕微鏡
2026年最新情報:進化を続ける電子顕微鏡の技術トレンド
電子顕微鏡はTEM/SEMを基盤にしつつ、現場の課題に応える形で確実に進化しています。ここでは、導入判断に直結するトレンドをコンパクトに整理しました(まずは全体像をつかんでから、個別要件に落とし込むのがおすすめです)。
観察モード・装置構成の拡張
- STEM(Scanning TEM):TEMの走査モード。HAADF検出で原子番号コントラストに優れ、界面評価や原子カラムの同定に有効。
- クライオ電子顕微鏡(Cryo-EM):凍結固定により生体高分子やソフトマターをネイティブに近い状態で観察。ビームダメージや乾燥収縮を抑制。
- FIB-SEM(Dual Beam):集束イオンビームで断面/薄片(TEMラミラ)を作製しながらSEMで撮像。半導体欠陥解析や3Dトモグラフィーに強み。
- 低真空・環境SEM(LV/ESEM):非導電・含水・揮発成分を含む試料を前処理簡素化で観察。導電コートや脱水の手間を削減。
性能と運用のアップデート
- 低加速電圧での高分解能:1 kV前後でもサブナノ級を狙える設計が普及。表面・高分子のダメージ低減に有効。
- 自動化・AI:自動アライメント、オートフォーカス/スタイグマ、ドリフト補正、パノラマ撮像/マッピングのバッチ化でスループット向上。
- AI画像解析:欠陥自動検出、粒子サイズ分布の自動計測などで客観性とスピードを両立。熟練者の目をデジタルで補完。
- リモート運用・データ管理:遠隔操作や権限管理、中央保管・自動レポート出力が一般化。複数拠点での活用がしやすくなりました。

電子顕微鏡は電子ビームの特性などにより、以下2種類に分けられます。
- 透過型電子顕微鏡(TEM)
- 走査型電子顕微鏡(SEM)
それぞれの顕微鏡が観察を得意とする対象物や、活躍する場面について解説します。
透過型電子顕微鏡(TEM)
透過型電子顕微鏡(TEM: Transmission Electron Microscope)は、非常に高い解像度を持つ顕微鏡です。TEMは電子ビームを試料に通し、その透過した電子を検出することで画像を生成します。試料は非常に薄くスライスされていて、電子が通過できる厚さが求められます。
透過型電子顕微鏡の強みは以下のとおりです。
- 他の顕微鏡技術よりも遥かに高い解像度を実現し、原子レベルの詳細まで観察が可能
- 電子線回折を利用して、結晶材料の内部構造を詳細に分析できる
- 観察対象の化学的組成を分析するために、エネルギー分散型X線分析(EDX)などの技術を併用できる
透過型電子顕微鏡は特に以下の場面で活躍します。
- 材料科学:新しい材料の開発や既存材料の改良において、原子レベルでの構造を明確にすることが必要な場合
- 生物学:ウイルスの構造解析や細胞の微細構造の観察など、生物学的サンプルの詳細な解析を行う際に用いられる
- 半導体業界:半導体デバイスの製造過程での欠陥分析や、デバイスの微細構造の検査などに利用される
走査型電子顕微鏡(SEM)
走査型電子顕微鏡(SEM: Scanning Electron Microscope)は、細く絞った電子ビームを表面上で走査し、主に二次電子(SE)や後方散乱電子(BSE)などの信号を検出して像を形成します。SEは表面の微細な凹凸・形状コントラストに優れ、BSEは原子番号の違い(組成コントラスト)を反映します。これにより、表面の3次元的なトップグラフィーから材料の相分布まで幅広い情報が得られます。
走査型電子顕微鏡の強みは以下のとおりです。
- 非常に高い拡大率で試料の表面構造を鮮明に捉えることができる
- 非常に硬い材料から生物学的な柔らかいサンプルまで、広い範囲の試料に対応可能
- EDX(エネルギー分散型X線分析)などの技術を組み合わせることで、サンプルの元素組成を分析できる
走査型電子顕微鏡は特に以下の場面で活躍します。
- 材料科学:合金、セラミックス、ポリマーなどの微細構造を調査し、材料の物理的特性との関連を理解するために使用される
- 生物医学研究:細胞の表面構造や組織の断面の詳細を調べる際に利用される
- 品質管理と故障分析:電子部品や微小デバイスの製造過程での欠陥や故障の原因を特定するために使用される
TEMとSEM、どちらを導入すべきか迷ったら、まず「何を(表面/内部)」「どの程度(必要最小解像度:nm)」「どんな情報(形状/組成/結晶)」を明確にしましょう。比較の目安は下表です。
| 比較項目 | 透過型電子顕微鏡(TEM) | 走査型電子顕微鏡(SEM) |
| 観察対象 | 試料の内部構造(透過像) | 試料の表面形状・凹凸 |
| 画像イメージ | レントゲンに近い2次元透過像 | 立体感のある表面像 |
| 解像度 | 非常に高い(原子レベル) | 高い(ナノメートル級) |
| 試料準備 | 超薄片化(非常に薄くスライス)が必要 | 前処理が比較的容易(塊のまま観察も可) |
| こんな時に | ・新素材の原子配列評価 ・細胞内微細構造の解析 |
・金属破面/樹脂表面の観察 ・半導体回路の欠陥探索 |
迷ったら「内部=TEM、表面=SEM」が基本です。必要最小解像度(nm)を書き出すと決めやすくなります。
用語補足(SEM信号の使い分け)
- 二次電子(SE):形状・微細凹凸の描写に優れる(形状観察・表面粗さ)。
- 後方散乱電子(BSE):原子番号依存の組成コントラスト(相分布/異物同定)。
併用分析例:EDS(元素組成)、EBSD(結晶方位・粒径)、CL(発光中心・欠陥)、WDS(定量精度)など。
電子顕微鏡を活用するメリット

電子顕微鏡を活用するメリットは以下の3点です。
- 極めて高い解像度
- 高い拡大率
- 詳細な材料解析能力
それぞれ解説します。
極めて高い解像度
電子顕微鏡は電子ビームを使用するため非常に解像度が高いです。
電子の波長は可視光よりもはるかに短いため、数ナノメーター(nm)単位、時には原子レベル(0.1 nm以下)の詳細まで観察可能です。これにより、微細な構造や原子配列まで詳しく観察することが可能となり、物質の基本的な特性を理解するのに役立ちます。
このメリットは以下の場面で活躍するでしょう。
- ナノテクノロジーの研究と開発
- 生物分子の構造生物学
高い拡大率
電子顕微鏡は拡大率が非常に高く、数百万倍の拡大率を実現します。この極めて高い拡大率により、原子や分子レベルの微細な構造を詳細に観察できるため、科学的な理解を大きく深めることが可能です。
光学顕微鏡が使用する可視光の波長に限界があるため、最大でも約2000倍程度の拡大率に制限されます。
このメリットは以下の場面で活躍するでしょう。
- 材料科学における微細構造分析
- 半導体業界における欠陥分析
詳細な材料解析能力
電子顕微鏡は主にエネルギー分散型X線分析(EDX)、電子線後方散乱回折(EBSD)、およびその他の分光学的手法を使用するため、材料解析能力が高いです。
これらの技術は、電子顕微鏡に組み込まれることで、サンプルの化学的組成や結晶構造、さらには電子と物質の相互作用に関する情報を詳細に提供します。これにより、物質の微細な構造だけでなく、その性質や反応のメカニズムも理解可能です。
このメリットは以下の場面で活躍するでしょう。
- 新素材の開発
- 故障分析と品質保証
電子顕微鏡を活用するデメリット

電子顕微鏡を活用する際、以下のデメリットも考慮が必要です。
- 高コスト
- サンプルの準備が複雑
- 操作と解析が専門的
デメリットを軽減する方法も紹介するので、電子顕微鏡を導入する際は参考にしてください。
高コスト
電子顕微鏡は購入価格だけでなく運用、および維持管理コストが必要で、高額になりやすいです。一台の電子顕微鏡が数千万円から数億円することがあります。さらに、高度な技術を使用するための特別な設備投資が必要です。
例えば特定の室温や湿度を保つための設備、振動を避けるための特殊な基盤などが必要です。また、消耗品、電源のコスト、専門技術者による操作や維持管理も定期的に必要であり、これらが運用コストをさらに増加させます。
このデメリットは以下の方法で軽減可能です。
- 大学や研究機関のような電子顕微鏡の共同利用施設を利用することで、高額な設備投資を行わずに電子顕微鏡を使用できる
- 政府や民間の研究助成プログラムを利用して、電子顕微鏡の購入や運用資金を支援してもらう
- レンタルやリースサービスを利用することで、長期にわたる高額な資金投資を避けつつ、必要な期間だけ設備を利用可能
- 中古品の購入。新品よりもコストを大幅に削減できる場合がある
(中古装置は、適切に再調整されていれば、新品と同等の性能を持つことが多く、コストパフォーマンスに優れている)
サンプルの準備が複雑
電子顕微鏡では、観察するサンプルを特別な方法で準備する必要があります。このプロセスに含まれる作業は以下の通りです。
- サンプルを非常に薄く切断する
- 真空状態での観察に適した加工を行う
- (場合によっては)特定の物質でコーティングする
特に、電子顕微鏡の真空環境では水分が蒸発しやすいため、生物学的サンプルは事前に適切に固定化し、脱水処理する必要があります。
また、非導電性のサンプルは電子ビームによるチャージングを防ぐために、金属などでコーティングすることが一般的です。これらのプロセスは専門的な技術と機材を要求し、時間もコストもかかります。
このデメリットは以下の方法で軽減可能です。
- 自動化されたサンプル準備装置の利用:サンプル準備の一貫性と効率が向上し、手間が大幅に削減可能
- 専門トレーニングとプロトコルの標準化:新しい研究者や技術者が必要なスキルを迅速に習得でき、間違いも少なくなる
- 共同利用施設でのサンプル準備:トレーニングされたスタッフがサンプル準備を行うため、個々の研究グループでは高度な設備や専門知識が不要
- 新技術の導入:より少ない準備で済む新しい観察技術やサンプル準備技術を利用する
- 低真空/環境SEMの活用:非導電・含水試料を導電コートや脱水を最小限で観察可能にする。
- クライオ手法の導入:凍結固定/凍結割断により、ビームに弱い試料の変性や収縮を抑える。
操作と解析が専門的
電子顕微鏡は特殊な状態のサンプルを扱うため、操作と解析にも専門知識が求められます。たとえば、走査型電子顕微鏡はサンプルが動いたり、ぼやけるなどの事象が起こります。これは電子線による荷電が原因とされており、外的な要素が要因です。
観察時のイレギュラーな事象は、電子顕微鏡について正しい知識を持っている、あるいは経験がある場合は対処できます。一方、知識も経験も持たない方では対処が難しいでしょう。電子顕微鏡は使いこなせれば、光学顕微鏡では観察が難しいサンプルにも対応できますが、操作と解析が難しい欠点があります。
このデメリットは以下の方法で軽減可能です。
- 専門機関への依頼:大学や研究機関など電子顕微鏡を活用することで、専門知識の習得が不要になる
- 見識者の誘致:経験と知識を誘致することで教育コストの削減と解析ミスのリスクを低減できる
最新機能で敷居を下げる
- オートアライメント/オートフォーカス/スタイグマ/ドリフト補正で再現性と立ち上げ速度を向上。
- AIによるピント・明るさ最適化や欠陥自動検出で、解析の客観性とスループットを強化。
- リモート観察とデータ中央管理で、複数拠点・多人数の運用をスムーズに。
4つの比較基準 | 電子顕微鏡の選び方
選定では「倍率」よりも、まず必要解像度(nm)と得たい情報(形状/組成/結晶)、そして試料適合性(導電性・厚さ・真空耐性)を優先してください。倍率は可変で、機種優劣の指標にはなりにくい点に注意しましょう。

電子顕微鏡の選定をする際は、以下4つのポイントを比較して決めると良いです。
- 用途に適切な倍率の顕微鏡を選ぶ
- 解像度
- サンプルの種類
- 価格
それぞれのポイントを解説します。
用途に適切な倍率の顕微鏡を選ぶ
電子顕微鏡を選定する際、使用目的に応じて適切な倍率の顕微鏡を選ぶことは非常に重要です。倍率は、観察したいサンプルの詳細度と直接関連しています。
そのため、適切な倍率の選定は、効率的で正確な観察を保証し、研究や品質管理の精度を高めます。倍率が適切でないと、サンプルの重要な特徴が見逃されたり、解析に無関係な詳細に時間を費やすことになりかねません。
また、特定の応用に最適な電子顕微鏡を選ぶことで、研究開発のコスト効率と効果を最大化できます。
電子顕微鏡の種類とそれぞれの平均的な倍率、適切な用途例は以下の通りです。
| 平均的な倍率 | 適切な用途例 | |
| 透過型電子顕微鏡(TEM) | 約50倍から数百万倍 | 原子レベルの材料科学研究 ナノテクノロジー開発 |
| 走査型電子顕微鏡(SEM) | 約10倍から数十万倍 | 表面形態の観察 故障分析 |
用途に適切な倍率の顕微鏡を選ぶことで、電子顕微鏡を導入する目的を最低限のコストで達成しましょう。
解像度
電子顕微鏡を選ぶ際は、必要な解像度を理解しておく必要があります。
解像度とは顕微鏡が識別できる最小の詳細度を指し、通常はナノメーター(nm)単位で表されます。解像度は顕微鏡の能力を示す重要な指標であり、電子レンズの品質、電子源の種類、操作条件などによって決定されます。
電子顕微鏡の種類と一般的な解像度は以下の通りです。
- 透過型電子顕微鏡(TEM):0.1 nmから1 nmの範囲
- 走査型電子顕微鏡(SEM):1 nmから10 nmの範囲
近年は収差補正TEMによりサブオングストローム級(0.1 nm未満)の観察が一般化し、SEMでも低加速電圧下での高分解能化が進んでいます。表面感度や試料ダメージ低減を重視する場合は「低kV性能」も重視しましょう。
適切な解像度を持つ顕微鏡の選定は、観察したいサンプルの性質や要求されるデータの精度に基づいて行う必要があります。
解像度が選定に重要とされる要因は以下の通りです。
- 観察目的の達成研究や分析の目的に最適なデータを得るには、対象とするサンプルのサイズや構造に適した解像度の顕微鏡を使用する必要がある
- より詳細な情報を得られるため、研究結果の正確性と再現性が向上し、科学的発見や技術開発の質が高まる
- 高い解像度の顕微鏡は高価なため、必要以上の解像度を備えた顕微鏡を選択すると、コストパフォーマンスの悪化に繋がる
解像度も倍率と同様に、目的を達成できることを前提として、最もコストを下げられる選択をしましょう。
サンプルの種類
電子顕微鏡を選定する際には、サンプルの種類を考慮することも重要です。
サンプルの物理的および化学的性質(硬度、導電性、熱安定性など)は、どの顕微鏡技術が適しているかを決定する上で重要な要素です。例えば、非常に薄いサンプルは透過型電子顕微鏡(TEM)に適しており、表面の微細構造を観察する必要がある場合は走査型電子顕微鏡(SEM)が適しています。
サンプルの種類が選定に重要とされる要因は以下の通りです。
- 不適切な顕微鏡を使用すると、サンプルが適切に観察されず、データの解釈が誤って行われる可能性がある
- 高エネルギーの電子ビームを使用するため、サンプルに応じて適切な顕微鏡を選ぶことで、サンプルの損傷や変質を避けられる
電子顕微鏡の種類ごとの適したサンプル例は以下の通りです。
透過型電子顕微鏡(TEM)
- バイオロジカルセクション:ウイルスや細菌などの微生物、または細胞の超薄切片
- ナノ粒子:化学合成によるナノ粒子や、材料科学でのナノスケールの粒子
走査型電子顕微鏡(SEM)
- 半導体デバイス:微細加工された回路の品質管理や故障分析
- 材料表面の分析:金属、セラミックス、ポリマーなどの表面構造の観察
価格
電子顕微鏡の価格はその種類、機能性、解像度、および製造業者によって大きく異なります。一般的に、透過型電子顕微鏡(TEM)は高価であり、特に高解像度モデルはさらにコストが高くなります。走査型電子顕微鏡(SEM)も幅広い価格帯が存在しますが、通常TEMよりは安価です。
価格を考慮することで、購入後の維持費用を含めた総コストが予算内で収まるかどうかを判断し、財務的に持続可能な選択をすることが可能になります。
価格が選定に重要とされる要因は以下の通りです。
- 決められた予算があるため、必要とする機能を持ちながらもコストパフォーマンスが最も高い顕微鏡を選ぶことが重要
- 電子顕微鏡は初期投資だけでなく、維持管理にも高額なコストがかかる傾向がある
- 研究目的や必要とする機能に見合った機器を選ぶことで、投資した資金に対して最大のリターンが得られる
企業や研究機関では、限られた予算の中で最大のパフォーマンスを発揮することが求められるでしょう。
電子顕微鏡の選び方(実務版チェックリスト)
- 観察目的:表面形状か/内部・原子配列か(表面=SEM、内部/原子配列=TEM/STEM)。
- 必要解像度:必要最小分解能(nm)を数値で定義(例:表面1–2 nm、界面0.1–0.2 nmなど)。
- 必要信号:形状(SE)/組成(BSE・EDS)/結晶(EBSD・回折)/電子状態(EELS等)。
- 試料適合性:サイズ・厚さ・導電性・含水/揮発・真空耐性(低真空やクライオの要否)。
- 試料作製:超薄切片(TEM)、断面(FIB)、導電コート/樹脂包埋などの可否と内製性。
- 運用条件:スループット(自動測定/マッピング)、据付環境(防振/温湿度/電源)、保守体制。
- 総コスト:本体+付帯設備(防振台・前処理装置)+消耗品+保守・教育のトータルで試算。
迷ったら、現状の観察画像(光学写真でもOK)と上記要件を整理して、共同利用施設やメーカーに相談してみましょう。最短ルートで「できる/できない」と前処理の要否が明確になります。
電子顕微鏡を製造するおすすめのメーカー

観察対象(材料・生物・半導体)や必要分解能、EDS/EBSDなどの分析拡張、操作性と保守体制を軸に比較すると最適解が見つかります。主要メーカーの特徴と代表機を整理しましたので、ご覧ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- 日本電子 / JEOL
- 日立ハイテク / Hitachi High-Tech
- 島津製作所(TESCAN提携) / Shimadzu
- エリオニクス / Elionix
- 松定プレシジョン / Matsusada Precision
※クリックで各メーカーの詳細に移動します。
日本電子 / JEOL
| 会社名 | 日本電子 / JEOL |
| 設立年 | 1949年 |
| 本社 | 東京都昭島市武蔵野3-1-2 |
| 概要 | 電子顕微鏡メーカー(SEM/TEM等) |
日本電子は、超高分解能TEM/FE-SEMを含むフルラインアップと国内製造・サポート体制に強みがあります。
代表機はJSM-IT800、JSM-7900F、JCM-7000(NeoScope)、JEM-ARM300Fです。原子分解能まで視野に入るハイエンド機の実績と製品層の厚さで研究から品質管理まで一気通貫の運用が可能です。
導入例として福井県立恐竜博物館での微化石・鉱物観察やミュージアムパーク茨城県自然博物館での学術展示支援が挙げられ、教育・研究用途に広く用いられます。
日立ハイテク / Hitachi High-Tech
| 会社名 | 日立ハイテク / Hitachi High-Tech |
| 設立年 | 1947年 |
| 本社 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー |
| 概要 | 半導体検査・計測装置メーカー |
日立ハイテクは、卓上SEMから超高分解能機までの幅広いラインアップと直感的な操作性で、初心者から熟練者まで使いやすい環境を提供します。
製品はTM4000 II、SU8600、SU9000、HT7800です。卓上SEMの扱いやすさと導入のしやすさ、加えて保守網の充実によって研究室や工場で素早く立ち上げられます。
活用例には大阪大学 超高圧電子顕微鏡センターでの材料研究のほか、製造現場の異物解析や教育機関での基礎実習があり導入効果が期待できます。
島津製作所 / Shimadzu
| 会社名 | 島津製作所 / Shimadzu |
| 設立年 | 1917年 |
| 本社 | 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1 |
| 概要 | 計測・試験機メーカー |
島津製作所は、総合分析機器メーカーとしての統合サポートと全国サービス体制により、装置導入から分析運用まで一貫支援します。
取り扱い機はTESCAN VEGA、TESCAN MIRA、TESCAN CLARAです。SEM本体とEDSなど分析機器のワンストップ対応により、据付後のデータ活用や保守がスムーズです。
エリオニクス / Elionix
| 会社名 | エリオニクス / Elionix |
| 設立年 | 1975年 |
| 本社 | 東京都八王子市元横山町3-7-6 |
| 概要 | 電子線装置・電子顕微鏡メーカー |
エリオニクスは、高分解能SEMや三次元粗さ解析SEMなどの特化技術とカスタム対応で、微細構造評価の現場を支援します。
主な機種はERA-600(高分解能走査電子顕微鏡)、三次元粗さ解析走査電子顕微鏡(ERAシリーズ)です。微細構造観察や形状解析に適した専用機ラインアップにより、測定再現性と解析効率の向上が期待できます。
松定プレシジョン / Matsusada Precision
| 会社名 | 松定プレシジョン / Matsusada Precision |
| 設立年 | 1978年 |
| 本社 | 滋賀県草津市青地町745 |
| 概要 | 高電圧電源・計測機器を中心としたエレクトロニクスメーカー(電子線/真空応用領域のソリューション提供) |
松定プレシジョンは、高電圧電源や真空応用の技術と全国サポート体制を活かし、卓上SEMを中心とした導入・運用支援や周辺機器のワンストップ対応に強みがあります。省スペース・コスト重視の現場でも立ち上げやすく、教育用途から品質管理までスムーズに展開できます。
- 卓上中心の省スペース構成と導入しやすい価格レンジ
- 据付環境(防振/電源)や前処理を含む運用設計のサポート
- デモ・評価から保守までの一貫サポートで運用リスクを低減
導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
電子顕微鏡の製品はまだありません。
