実体顕微鏡
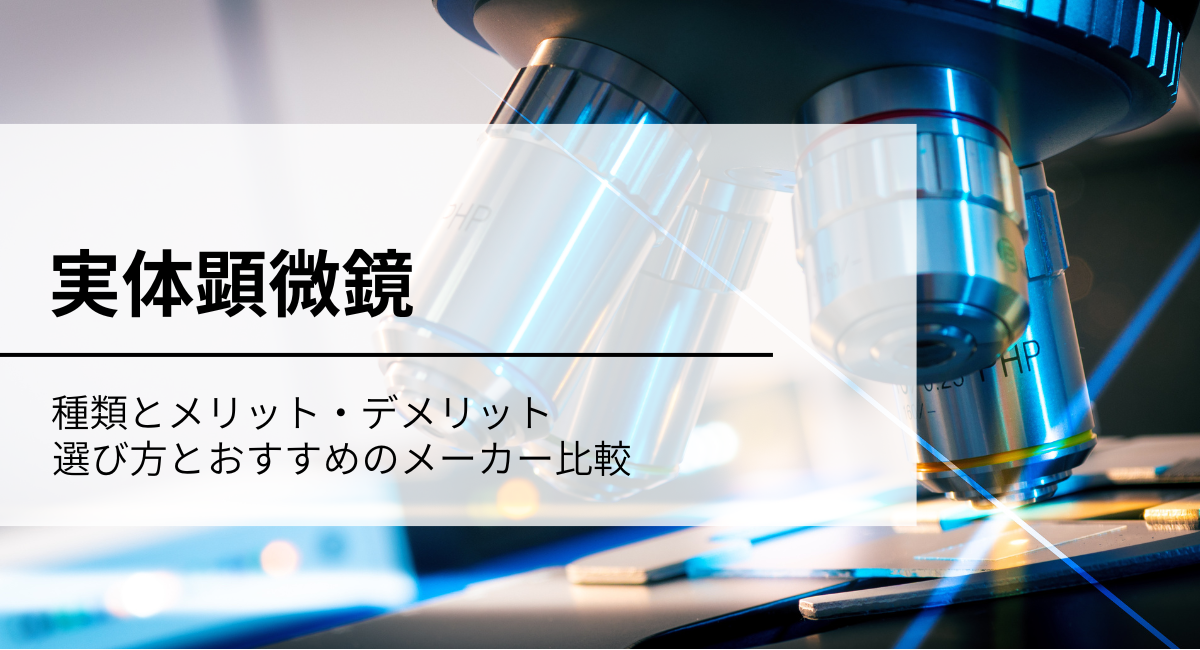
実体顕微鏡は、左右に配置された二つの光学系を持ち、観察対象を立体的に見ることができる顕微鏡です。これにより、深さや形状を直感的に把握することが可能です。
通常の顕微鏡と比べて低倍率(一般的には10倍から50倍程度)で観察を行うことができるため、広範囲の観察に適しています。ここでは、固定倍率式実体顕微鏡からデジタル実体顕微鏡まで、5種類の実体顕微鏡について詳しくご紹介します。
5種類の実体顕微鏡

実体顕微鏡は、左右に配置された二つの光学系を持ち、観察対象を立体的に見ることができる顕微鏡です。
これにより、深さや形状を直感的に把握することが可能。通常の顕微鏡と比べて低倍率(一般的には10倍から50倍程度)で観察を行うことができます。
実体顕微鏡には、以下の5種類があります。
- 固定倍率式実体顕微鏡
- ズーム式実体顕微鏡
- 双眼実体顕微鏡
- 三眼実体顕微鏡
- デジタル実体顕微鏡
固定倍率式実体顕微鏡
固定倍率式実体顕微鏡は、特定の倍率に固定された顕微鏡で、倍率を変更することができないことが特徴です。一般的には10倍、20倍などの固定倍率が設定されています。
固定倍率式実体顕微鏡の強みは以下のとおりです。
- 構造がシンプルで製造コストが低い
- 固定倍率のため、倍率を変更する必要がなく、操作が非常に簡単
- 一定の倍率で観察を行うため、観察結果が一貫しており、比較や記録が容易
特定の作業や観察において一貫した倍率が必要な場合に適しています。
ズーム式実体顕微鏡
ズーム式実体顕微鏡は、倍率を連続的に変更できる機能を持つ顕微鏡です。一般的には6.7倍から45倍までの範囲で倍率を調整でき、広範囲の観察が可能です。
ズーム式実体顕微鏡の強みは以下のとおりです。
- 広範囲の観察から詳細な検査まで一台で対応可能
- 最新のズーム式実体顕微鏡は、解像度が飛躍的に向上しており、微細な構造まで鮮明に観察可能
- ズームダイヤルを回すだけで倍率を変更できるため、操作が直感的で簡単
多様な倍率での観察が必要な場合や、詳細な検査が求められる場合に適しています。
双眼実体顕微鏡
双眼実体顕微鏡は、左右の目で同時に観察することができる顕微鏡で、立体的な視野を提供してくれることが特徴です。これにより、観察対象の深さや形状を直感的に把握することができます。
双眼実体顕微鏡の強みは以下のとおりです。
- 両目で観察することで、対象物を立体的に見ることができ、深さや形状を正確に把握できる
- 低倍率で広い視野を提供するため、対象物全体を一度に観察することができる
- 両目で観察するため、長時間の観察でも目の疲労が少なく、快適に作業を続けることができる
- 生物学、医学、材料科学、電子工学など、さまざまな分野で使用される
一般的には、低倍率(10倍から40倍程度)で広い視野を持ち、立体物の観察に適しています。
三眼実体顕微鏡
三眼実体顕微鏡は、双眼実体顕微鏡に加えて、カメラやそのほかの撮影機器を取り付けるための第三の光路(撮影鏡筒)を持つ顕微鏡です。これにより、観察しながら同時に写真やビデオを撮影することが可能です。
三眼実体顕微鏡の強みは以下のとおりです。
- 第三の視路を通じて高品質な画像やビデオを撮影できるため、観察結果を記録し後で詳細に分析することが容易
- カメラやほかのデバイスを簡単に取り付けられるため、さまざまなタイプの分析や報告に対応できる
- 観察と記録を同時に行えるため、作業効率が向上
三眼実体顕微鏡は、観察と記録を同時に行う必要がある場合に特に有用です。
デジタル実体顕微鏡
デジタル実体顕微鏡は、光学レンズを使用して観察対象を拡大し、その画像をデジタルカメラでキャプチャし、ディスプレイに表示する顕微鏡です。これにより、観察者は接眼レンズを通してではなく、モニター上で観察を行います。デジタル技術を活用することで、画像の保存や解析が容易になります。
このタイプの実体顕微鏡の強みは以下のとおりです。
- デジタルカメラを使用することで、高解像度の画像を取得でき、微細な構造まで鮮明に観察できる
- 観察した画像を簡単に保存し、他の研究者や学生と共有することができる
- 画像解析ソフトウェアを使用することで、リアルタイムでの解析や計測が可能
- モニター上での観察は、複数人で同時に観察することができ、教育現場やプレゼンテーションでの利用に適している
デジタル実体顕微鏡は、特に画像の保存や解析が重要な場合に非常に有用です。
実体顕微鏡を活用するメリット・デメリット

実体顕微鏡には、メリットとデメリットの両方があります。両方を検討することで、適切な機械を選ぶことが重要です。
メリット
実体顕微鏡を活用するメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 立体視が可能
- 広い視野
- 操作の簡便さ
立体視が可能
実体顕微鏡は左右の目で異なる角度から観察するため、対象物を立体的に見ることができます。これにより、深さや形状を直感的に把握が可能です。
このメリットのため、以下の場面で活用されることが多いです。
- 昆虫の観察:昆虫の足や触角の構造を立体的に把握することで、動きや機能の理解が容易
- 宝石の観察:内部構造やカットの状態を立体的に観察し、品質や価値を正確に評価
広い視野
低倍率で広い視野を提供するため、対象物全体を一度に観察することができるため、全体像を把握しやすくなります。
このメリットのため、以下の場面で活用されることが多いです。
- 回路基板の観察:回路基板全体を一度に観察し、欠陥や不具合を迅速に発見
- 植物の観察:植物の葉や茎の構造を広い視野で観察することで、病害虫の被害状況や成長状態を容易に把握
操作の簡便さ
実体顕微鏡は構造がシンプルで操作が簡単で、特に初心者や特定の作業に集中する場合に便利です。
このメリットのため、以下の場面で活用されることが多いです。
- 学生の観察:操作が簡単なため、学生が自分で顕微鏡を使って観察を行うことができる
- 製造ラインでの品質検査:操作が簡単で迅速に観察が行えるため、製品の不良品を早期に発見し、対策を講じることが可能
このように、実体顕微鏡は操作の簡便さが求められる場面で非常に有用です。
デメリット
一方で、実体顕微鏡を選定する際は以下のポイントに注意する必要があります。
- 低倍率である
- 解像度の限界
- 照明の制約がある
低倍率である
実体顕微鏡は高倍率での観察が難しいため、微細な構造の詳細な観察には向いていません。
高倍率や高解像度が必要な場合は、電子顕微鏡や光学顕微鏡を活用する必要があります。
解像度の限界
高解像度の画像を得ることが難しく、微細なディテールの観察には限界があります。
高い解像度での観察が必要な場合は、デジタルカメラや画像解析ソフトウェアを併用することがおすすめです。
照明の制約がある
照明条件によっては、観察対象が見えにくくなることがあります。
照明条件が悪い場所での観察が必要な場合は、LED照明やリングライトなど、高品質な照明を使用することがおすすめです。
5つの比較基準 | 実体顕微鏡の選び方

最適な実体顕微鏡を選ぶには、以下の5つの点を考慮する必要があります。
- 倍率
- 視野数
- 作動距離
- 焦点深度
- 光学性能
倍率
観察対象によって適切な倍率が変わるため、観察対象に対して適切な倍率の実体顕微鏡を選ぶ必要があります。
以下の表では、10から50倍まで、それぞれの倍率に対して適切な用途や観察対象物の例をご紹介するので、こちらを参考にしながら適切な倍率を確認してください。
| 倍率 | 用途 | 観察対象物の例 |
|---|---|---|
| 10倍 | 小さな部品の組立や検査など、 対象物の全体像を把握しながら作業したい場合 | 電子部品:ICチップ、抵抗器、コンデンサーなどの形状や配線状態の確認 昆虫:ハチ、アリなどの小さな昆虫の形態観察 |
| 20倍 | 10倍では見えにくい小さな文字や模様の確認など、細部を観察したい場合 | 印刷物:活字や画像の細かな部分の確認 鉱物:結晶構造や表面の傷などの観察 |
| 30倍 | 植物の葉脈や昆虫の複眼など、微細な構造を観察したい場合 | 植物:葉の表皮や気孔の観察 繊維:布地の織り方や糸の太さの観察 |
| 40倍 | 半導体ウェハの検査や精密機械部品の表面検査など、高度な検査に利用 | 半導体:ICチップの配線パターンや欠陥の確認 細胞:生物の細胞の観察 |
| 50倍 | 極めて小さな生物や物質の観察など、極限的な観察に利用 | 微生物:ダニやカビなどの微生物の観察 微粒子:粉塵や微粒子の形状や大きさの観察 |
※スマートフォンは横にスクロールできます。
視野数
視野数が変動すると、観察できる範囲(実視野)が変わります。
視野数が大きいと、一度に広い範囲を観察できるため、全体像を把握しやすくなる。また、広い視野を持つことで、試料を頻繁に動かす必要がなくなり、観察作業がスムーズに進むため、作業効率が向上します。
一方で、視野数が小さいと、狭い範囲を詳細に観察できるため、微細な構造や細部の確認がしやすいです。また、視野数が小さいと解像度が高くなり、観察対象の細部がより鮮明に見えます。そのため、微小な欠陥や異常を発見しやすくなります。
作動距離
作動距離が変動すると、対物レンズの先端から観察対象までの距離が変わります。作動距離が長いと、試料の取り扱いや観察が容易になり、作動距離が短いと、試料に対する詳細な観察が可能です。
作動距離が長いと、試料と対物レンズの間に十分なスペースができるため、試料の配置や操作がしやすくなります。これにより、工具を使った作業や大きな試料の観察が容易になります。また、さまざまなサイズや形状の試料を観察できるため、幅広い用途に対応できます。例えば、自動車部品や電子機器の検査など、大きな試料の観察に適しています。
一方、作動距離が短いと、対物レンズの開口数が大きくなり、解像度が向上します。これにより、微細な構造や細部を詳細に観察することができます。また、試料と対物レンズの距離が近いため、観察対象が安定しやすくなります。これにより、微小な動きや振動の影響を受けにくくなります。
焦点深度
焦点深度が変動すると、観察対象のどれだけの範囲が焦点内にあるかが変わります。焦点深度が深いと、厚みのある標本でも全体にピントが合い、はっきり見えます。逆に焦点深度が浅いと、ピントの合う範囲が狭くなり、特定の層にしかピントが合わなくなります。
焦点深度が深いと、厚みのある試料でも全体にピントが合い、観察が容易になります。例えば、植物の葉や昆虫の体など、立体的な構造を持つ試料の観察に適しています。また、焦点深度が深いとピント合わせが容易になり、観察対象の全体像を把握しやすくなります。これにより、観察作業が効率的に行えます。
一方、焦点深度が浅いと、特定の層にピントが合うため、解像度が高くなり、微細な構造を詳細に観察できます。これにより、細胞内部の観察や微小な欠陥の検出が可能になります。また、焦点深度が浅いと、ピントが合う範囲が狭いため、観察対象のコントラストが向上し、細部がより鮮明に見えます。
光学性能
光学性能が変動すると、観察対象の解像度や色収差の補正能力が変わります。光学性能が高いと、より鮮明で正確な画像が得られ、低いと画像の鮮明さや色の正確さが劣ることがあります。
光学性能が高いと、解像度が向上し、微細な構造や細部を詳細に観察できます。これにより、精密な分析や検査が可能になります。また、高性能な光学系は色収差を効果的に補正するため、観察対象の色が正確に再現されます。これにより、試料の本来の色を確認しやすくなります。さらに、光学性能が高いと光の透過率が向上し、試料の細部まで明瞭に観察できるため、観察の精度が向上します。
一方で、光学性能が低いと製造コストが抑えられるため、顕微鏡の価格が低くなります。これにより、予算が限られている場合でも導入しやすくなります。
また、高性能な光学系は複雑な調整が必要な場合があるのに対し、低性能な光学系は操作が簡単で、初心者でも扱いやすいです。さらに、光学性能が低いとレンズや光学部品が軽量化されることが多く、顕微鏡全体の重量が軽くなるため、持ち運びや設置が容易になります。
実体顕微鏡を製造するメーカー

観察対象のサイズや必要倍率、作動距離、カメラ連携や照明方式などを整理してから候補を絞ると選定がスムーズです。用途に応じたスタンドやアーム、リングライトなど周辺機器の互換性もチェックしてください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- ニコン / Nikon
- エビデント / Evident
- 成和光学製作所 / Seiwa Optical
※クリックで各メーカーの詳細に移動します。
ニコン / Nikon
| 会社名 | ニコン / Nikon |
| 設立年 | 1917年 |
| 本社 | 東京都港区港南2-15-3 |
| 概要 | 精密機器・計測ソリューションメーカー |
ニコンは、研究・産業向けの高性能光学と豊富なアクセサリー体系を生かした拡張性で評価されています。
代表機種はSMZ25、SMZ18、SMZ1270、SMZ800N、SMZ745で、観察から記録まで柔軟に対応します。高NAに基づく解像度と長い作動距離を両立し、微細観察から操作作業まで安定した視野を提供可能です。
エビデント / Evident
| 会社名 | エビデント/Evident |
| 設立年 | 2021年 |
| 本社 | 東京都新宿区西新宿2丁目3−1 |
| 概要 | 非破壊検査機器や工業用顕微鏡などを開発・製造するメーカー |
エビデントは、広いズーム比レンジと人間工学設計、周辺機器の充実で長時間作業を支えます。
ラインアップはSZX16、SZX10、SZ61、SZ51などで、研究から生産現場まで対応します。倍率域とアクセサリーの選択肢が広く、作業プロセスに合わせて最適な観察条件を組めるのが魅力です。
成和光学製作所 / Seiwa Optical
| 会社名 | 成和光学製作所 / Seiwa Optical |
| 設立年 | 1964年 |
| 本社 | 東京都大田区南馬込3-22-17 |
| 概要 | 産業用光学機器メーカー |
成和光学製作所は、自社で設計・製造・修理まで一貫対応し、現場要件に沿った個別提案に強みがあります。
製品はSKZ-1、SKZ-2、SKZ-4、SKZ-5、SKZ-6などのSKZシリーズで、多様なスタンド・照明に対応します。作業距離や照明条件、スタンド構成を柔軟に選べるため、実装・検査・リワークなど現場に適したシステムを構築しやすいです。
