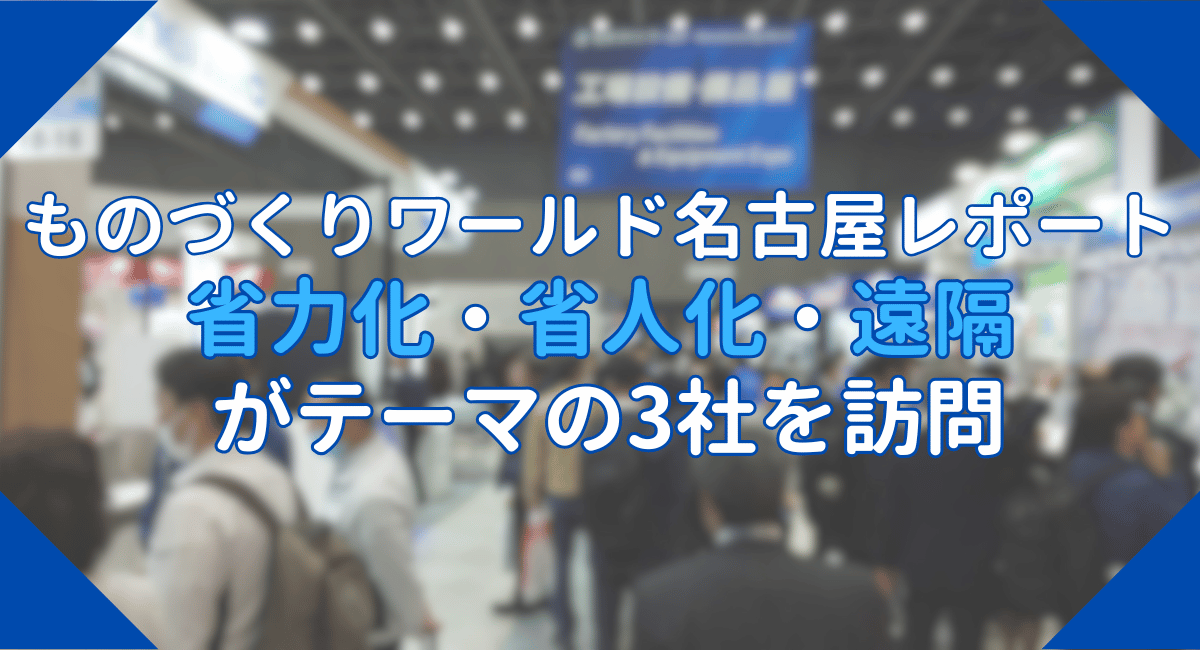バランサ
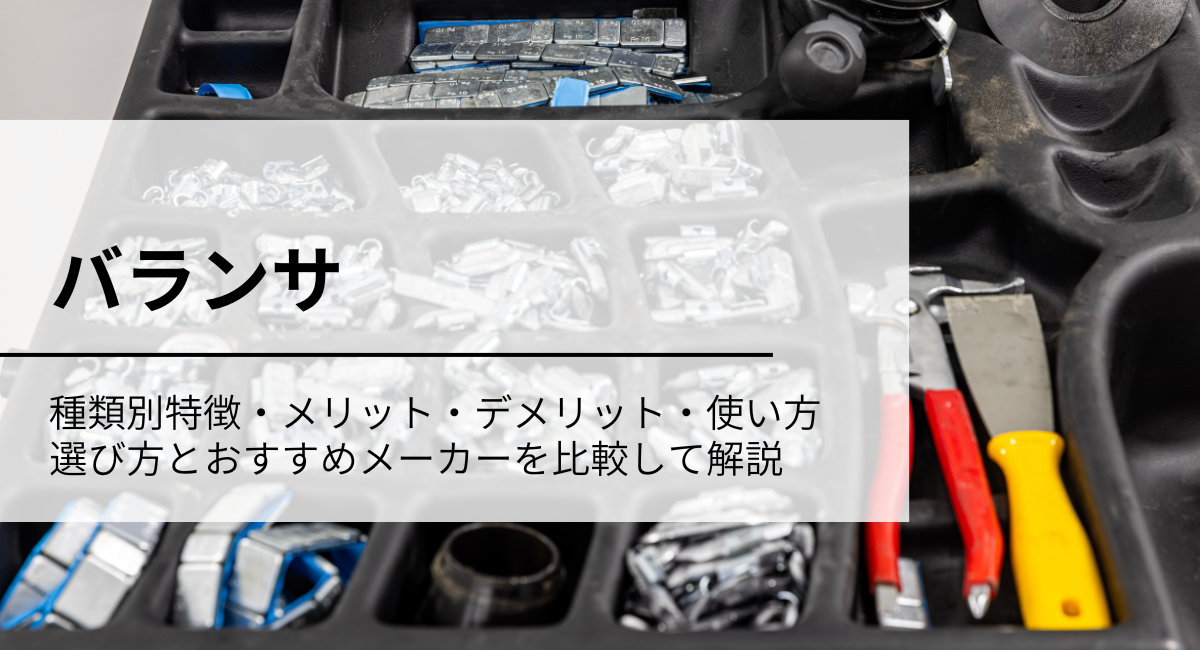
「重いワークの昇降や移動が大変」「作業者に負担がかかり、作業効率が下がってしまう」――そんな悩みを抱えていませんか?
バランサは、重量物を手軽かつ安全に操作できる頼もしい装置です。本記事では、バランサの基本的な特徴から種類、使い方、そして製品を選ぶ際のポイントや、おすすめメーカーの情報まで一挙にご紹介。
職場環境や作業負荷の改善を考えている方にとって、新たな一歩につながるヒントを多数お伝えします。ぜひ最後までご覧いただき、貴社の現場に最適なバランサの活用方法を見つけてください。
目次
バランサとは? 特徴や活用例などを解説
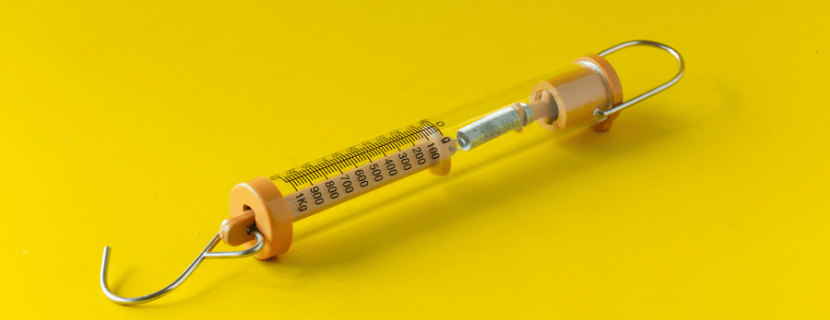
バランサとは、重量物を比較的少ない力で昇降・移動させるための補助装置を指す総称です。工場や倉庫など、さまざまな現場で導入されており、作業負荷を減らしつつ、安全性と作業効率を高めることができます。
例えば、組立製造ラインで工具や部品を吊り下げておく、あるいは重たいワークを持ち上げる負担を軽減するといった使い方が代表的です。
最大のメリットは、作業者が少ない力でワークを扱えるようになる点で、肉体的な疲労や事故リスクを大幅に抑えられます。一方で、導入コストなど、デメリットとなり得る要素も存在します。
バランサを検討する際は、事前にどのような運用方法を想定しているのかを明確にしながら、メリットとデメリットの両方を押さえておくことが大切です。
次のセクションでは、具体的なバランサの種類を詳しく見ていきます。
【その他の助力装置との違い】ホイストとバランサの違いとは

バランサと似た機能を持つ機械として、ホイストがあります。
ホイストは、バランサと同じように”吊る”事ができる器具で、ワークの上下に使用できます。
用途としては、どちらも重いものを吊り下げて運んだり、組み立て作業に用いられるなど、共通点も多いです。
ホイストとバランサが異なる点としては、ホイストが主にボタン操作で上下の動きを行うのに対して、バランサは手で持って直感的な操作ができる点にあります。(手で持たず、リモコンでも操作可能なバランサもあります)
ホイストのメリット
重量物を扱える:バランサよりも大きな荷重を扱うことができる
高い場所への搬入ができる:2階、3階等の高い場所へワークを運びたい場合に適している
危険物も扱える:熱い、鋭利など、直接触れない危険なものに使える
バランサのメリット
細かい作業が得意:ボタンでの上下の微調節が必要なホイストに比べ、バランサは直感的な操作が可能で、微調節がしやすいです。
作業時間の短縮:直感的に操作できることで、スムーズに作業を行うことができ、作業時間が短縮されます。
教育時間の短縮:経験が求められる、微妙なコントロールが必要なく、直感的に操作できるため、入社から日が浅い従業員でも取り付け、搬送を行えます。
種類はいくつあるのか|各バランサのメリット・デメリットを解説

ひと口にバランサと言っても、その内部機構や動力源によって複数の種類が存在します。どのタイプを選ぶかによって、重量制限や操作性、導入コストなどが異なります。
ここでは代表的な種類として、スプリング式、エア式、電動式の3つをご紹介。それぞれのメリット・デメリットを押さえて、自社や自分の現場に最適なタイプを見極める参考にしてください。
スプリング式バランサ
スプリングの力を利用して、吊り下げたワークの重量をバランスよく支えるタイプです。
エア式バランサ
圧縮空気を動力源とするバランサで、圧力調整によってワークを浮かせる仕組みです。
電動式バランサ
モーターを動力源とするバランサで、スイッチ操作などにより昇降動作を行います。
以上のように、バランサの種類によって、適した環境や導入コストが異なります。
次のセクションでは、実際の現場でバランサを活用する際の使い方ガイドについて解説しますので、併せて確認してみてください。
バランサの仕組みと構造について

バランサは、大きく分けて動力部とワイヤ、レール、そして吊り具やフックなどの末端部品によって構成されています。
物を動かす動力の部分に目が行きがちですが、バランサはレールや吊り具などそれぞれのパーツを最適に選ばなければその本領を発揮することはできません。本章では、広義のバランサを構成するパーツについて解説します。
動力部・ワイヤ
動力部は、一般的にバランサと言われてイメージがつきやすい部分です。動力と、そこから出ているワイヤーによって力を伝え、ワークを支えたり持ち上げたりします。
スプリング式であればスプリングを伸縮させてワークを支え、エア式であればシリンダーと圧縮空気の力で重量を支持し、電動式の場合はモーターとギアなどで支える仕組みです。
複数の動力を組み合わせたタイプもあります。
いずれの方式も、重力と釣り合う力を発生させてワークの重量を軽減する考え方は共通しています。要点は、バランサ内部でワークの重量をどのように吸収し、制御しているかという点です。
構造の違いによって使い勝手や保守の考え方が変わるため、導入の際は各方式の内部構造を知っておくことが長期的にトラブルを防ぐうえでも大切です。
支持構造
支持構造は、動力部を吊り下げる骨組みの部分で、使用環境によってレールやクレーンタイプなどを選ぶ必要があります。
レールタイプは、地上のスペースをが空くため、作業場所を広く取ることができます。一方、初期工事が大掛かりになることや、簡単にレイアウトを変えられないというデメリットがあります。
レールタイプの種類には、1本のレールだけがあり、前後の動きだけをする1軸式、前後左右の動きをカバーできる2軸式(クロスレール)などがあります。
素材としては、主にアルミとスチールがあり耐荷重の大きさと耐久性に違いがあります。
レールは外観での違いは分かりづらいですが、動作性の高いものを選べば、少ない力で動かすことができます。
逆に、動作性が低いと引っかかりを感じたり、ワークを吊り下げて運ぶ際に強い力で押す必要があり、導入した目的である、「作業者の負担を軽くしたい」を達成できなくなってしまう可能性もあるため、慎重に選ぶ必要があります。
レール以外のタイプは、地上に設置してクレーンのような機構で吊り下げるクレーン型、スタンド型と呼ばれるものがあります。
クレーン型、スタンド型はレイアウトの柔軟性があり、移動も比較的容易です。一方、地上に台車や柱を置くため、作業スペースが狭くなってしまうなどのデメリットがあります。
自社の環境が、レイアウトを頻繁に変えたり制約がある場合はクレーン・スタンドタイプ、レイアウトが固定であればレールタイプがおすすめです。
吊り具(アタッチメント)
吊り具とは、ワイヤーの先につけてワークを直接吊り上げる部分です。
ワークの形状や素材によって適したものを選ばないと、ワークをしっかり把握できず事故につながったり、作業がスムーズにいかず、ロスが生まれる原因にもなります。
道具を常に吊り下げておくのであればフック式、ワークの形状が複雑な場合は掴む動きをするグリッパー式(ゲームセンターのUFOキャッチャーの構造を思い浮かべてください)が適しています。
空気を吸い込むことで真空を作り出す真空パッド式は、段ボール箱やパネルなど平面部分があるものに利用でき、素早いワークの移動に適しています。
その他にも、鉄製のワークに適したものや大型ワークに適したものもなど、数多くの吊り具があります。
特殊な吊り具を取り揃える、吊り具の専門メーカーもあるので、一般的な吊り具でよいか不安な場合は、吊り具専門メーカーに相談してみるのもよいでしょう。
本章では、バランサの構造を解説しました。次章では、実際にバランサを選ぶ際に気をつけたいポイントをお伝えします。
選定の比較ポイントは? バランサの選び方

バランサは単に重量物を持ち上げればよいというわけではなく、現場環境やワークの特性に合わせた選定が不可欠です。
ここでは、選定時に押さえておきたい3つのポイントを解説します。
ワークの重量
バランサの選定ポイントとして、取り扱うワークの重量に対して十分な余裕を持つ最大荷重を備えた製品を選ぶことが挙げられます。
ワークの重量や形状、持ち上げ頻度などによって必要とされる最大荷重は変わるため、事前に作業条件を詳細に洗い出すことが重要です。
もし最大荷重を考慮せずに選んでしまうと、ワークを落下させたりバランサ自体に過度な負荷をかけたりするリスクが高まります。新たに重量物を扱う工程を導入する場合や既存ラインで荷重オーバーが疑われる場合には特に注意が必要です。
バランサでは対応できないような高重量のワークを取り扱う場合は、ホイストであれば対応可能な場合もあります。
また、0.5t(500kg)以上のバランサはクレーン等安全規則に準じ、労働基準監督署に設置報告が必要となります。
適切な最大荷重を検討すれば作業者の安心感を高め、作業中のヒヤリハットを減らしてより安全な職場づくりに貢献できます。
現場環境
現場の設置環境や作業スペースに適した動力方式を選ぶことも重要です。
1.動力源の確保:エア式であれば、工場内にエア源を確保できるか、電気式であれば電源の確保や配線を安全に通すことができるかといった導入環境によって導入可能なバランサは絞られます。
2.リスク管理:バランサの種類を選ぶ視点で大切なのはリスク管理面です。
化学工場や、粉塵が多く出るような防爆工場の場合、液体がかかるリスクのある現場で、電気式を使うと火花から引火したりショートが起こり事故のリスクが高まります。
そのような場合は、エア式、スプリング式を選ぶ必要があります。
3.操作性:空気式、電気式どちらでも導入可能な現場では、それぞれの操作性で選ぶやり方ができます。
エア式の場合は、ふわっとした操作感です。電気式の場合は、より精密な作業に向いています。
現場環境に適したバランサを導入できれば、余分なメンテナンスや稼働トラブルを減らし、安定した操業を続けやすくなります。
作業動線
レバーやグリップ操作のしやすさ、ブレーキ性能など実際の作業動線に合わせた操作性を重視することが挙げられます。
作業者の身長や腕のリーチ、さらにワークの持ち手部分の形状などが操作性を左右する要因であり、これらが合っていないと誤操作や扱いづらさにつながるでしょう。
誤操作が頻発すると事故リスクや作業者の疲労が増大し、生産性にも悪影響を及ぼします。
特に多品種少量生産の現場では、オペレーターが入れ替わる可能性が高いため、操作しやすいバランサを導入する重要性が高まります。
このとき、作業範囲は平面(XY軸方向)だけでなく、天井配管など人間の頭上の空間(Z軸方向)も考慮する必要があります。
操作性のよいバランサを選定すれば、短期的な教育でも作業の統制が図りやすくなり、安全かつ効率的な運用が実現可能です。
ここまでバランサの選定ポイントを解説しました。
次の章では、バランサのおすすめメーカーを解説します。
JET-Robotics編集部おすすめのバランサメーカー・代理店

バランサを選ぶ際には、信頼できる会社の製品から検討を始めるのがおすすめです。
ここでは、それぞれ独自の強みを持つメーカー・代理店をJET-Roboticsのピックアップでご紹介します。各社の概要と、どんなバランサを提供しているのかをぜひ参考にしてください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- キトー / Kito
- 遠藤工業 / ENDO KOGYO
- トーヨーコーケン / TOYOKOKEN
- 元田技研 / MOTODA GIKEN
※クリックで各メーカーの詳細に飛べます。
バランサを製造するメーカー
キトー / Kito
| 会社名 | キトー / Kito |
| 設立年 | 1944年 |
| 本社 | 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000 |
| 概要 | マテリアルハンドリング機器やクレーンなど構造物の設計、製造、工事、販売、修理サービス業務やホイスト機器及びホイスト周辺機器の提供 |
キトーは1944年に山梨県中巨摩郡に設立された企業です。マテリアルハンドリング機器やクレーンなどの構造物の設計、製造、工事、販売、修理サービス業務のほかに、ホイスト機器とホイスト周辺機器を提供しています。
キトーの「キトー電動チェーンバランサ」は高い応答による超低速動作により、微細な位置決めをサポートしてくれます。
組付け作業や繊細な荷物の取り扱いなど、細かな調整が必要とされる作業にも適しており、誰にとってもわかりやすく、使いやすい直感的・感覚的操作が可能です。さらにキトーでは「キトーライトクレーンPROシステム」やワーク形状に合わせた専用吊具も提供しており、ユーザー毎の特性に応じた搬送システムの導入をサポートしてくれます。
導入事例としては、段ボールやプラスチックコンテナなど定型物の搬送負荷軽減や、車体部品の組付け、陶器の搬送など慎重さが求められる作業の負担軽減に加えて、農作物や食品原料の搬送・投入作業の負荷軽減などが挙げられます。
遠藤工業 / ENDO KOGYO
| 会社名 | 遠藤工業 / ENDO KOGYO |
| 設立年 | 1935年 |
| 本社 | 新潟県燕市秋葉町3丁目14番7号 |
| 概要 | 産業用機械・機具の製造・販売 |
遠藤工業は金属洋食器の産業事業で創設後、さまざまな変遷を経て、現在は荷役機器、給電機器、環境機械の3部門を事業の柱としています。特に荷役機器の一つのスプリングバランサーは、自動車業界をはじめ、産業機械、電子機器、食品、物流など、世界50カ国以上の多様な製造現場で広く使用されています。
同社が扱っているバランサは、電動バランサの「サーボバランサー」などです。操作はシンプルで、サーボモータのため繊細な操作感、パラメータ設定により、昇降速度の調整なども行えます。また、クリップボックス部に設けられた標準制御機能により、バキューム式やクランプ式のアタッチメントにも対応可能です。
繊細な作業が必要な重量物のハンドリング、手作業で運んでいる重量物の搬送、加工機のチャックへのワーク取り付け、組立て作業時の位置決めなどが主な用途例です。特に搬送・位置合わせを伴う組付け作業を行う現場に最適でしょう。
トーヨーコーケン / TOYOKOKEN
| 会社名 | トーヨーコーケン / TOYOKOKEN |
| 設立年 | 1957年 |
| 本社 | 東京都江東区南砂2-11-1 |
| 概要 | ウインチ・ホイスト、荷揚機、バランサ、ジラフ等の設計、製作、施工、販売 |
トーヨーコーケンウインチで60年、バランサで40年以上の歴史を持ち、建設、産業機械をはじめ、製品が多くの企業に使用されている会社です。お客様一人ひとりのニーズに適合するモデルを標準品としてラインナップしていることに強みがあり、スムーズな導入、安定したユーザビリティ、迅速なアフターサポートを実現しています。
同社は電動式、エアー式、ハイブリッド式のバランサを扱っており、たとえば電動式は「インテリジェントバラマン i2シリーズ」などがあります。高性能のバランス機能をはじめ、すべての搭載機能をオール電気で実現しています。電気・電子制御技術、機械設計技術の粋を結集して開発され、従来型の電動式バラマン(電気式バランサ)とは一線を画する機能・性能性です。
段ボール搬送や米袋の搬送、ガラスや銅板、ロール材、プラケース、自動車部品、缶・容器、リサイクル品などの搬送などに用いることができます。
元田技研 / MOTODA GIKEN
| 会社名 | 元田技研 / MOTODA GIKEN |
| 設立年 | 2000年 |
| 本社 | 東京都八王子市片倉町633-10 |
| 概要 | 荷重取扱作業用バランサーの研究、商品開発、設計、製造、販売 |
元田技研は、作業現場で働く方々の「困った」を解消するため、バランサーワイマンの開発・製造を始めて50年以上、設計から原材料の仕入れ、加工、塗装、組立、電気制御まで一貫生産で行っている会社です。
同社は多人数を必要とする作業を1人で安全に行うことができるような、オーダーメイドの電動バランサーを扱っています。たとえば、「ベーシックワイマン MY-B型」などがあり、動力伝達にラック&ピニオンを採用、パンタグラフ機構を採用した垂下型アームを持つ円筒座標型であるのが特徴です。
コンテナ移載作業、コンテナパレタイズ作業、ブロック吸着移載、反転付ロール物つかみジグなどが用途例として挙げられています。ワークに合わせてアタッチメントを採用することで、つかむ、すくう、吸着、まわすといった作業が可能です。