解体ロボット
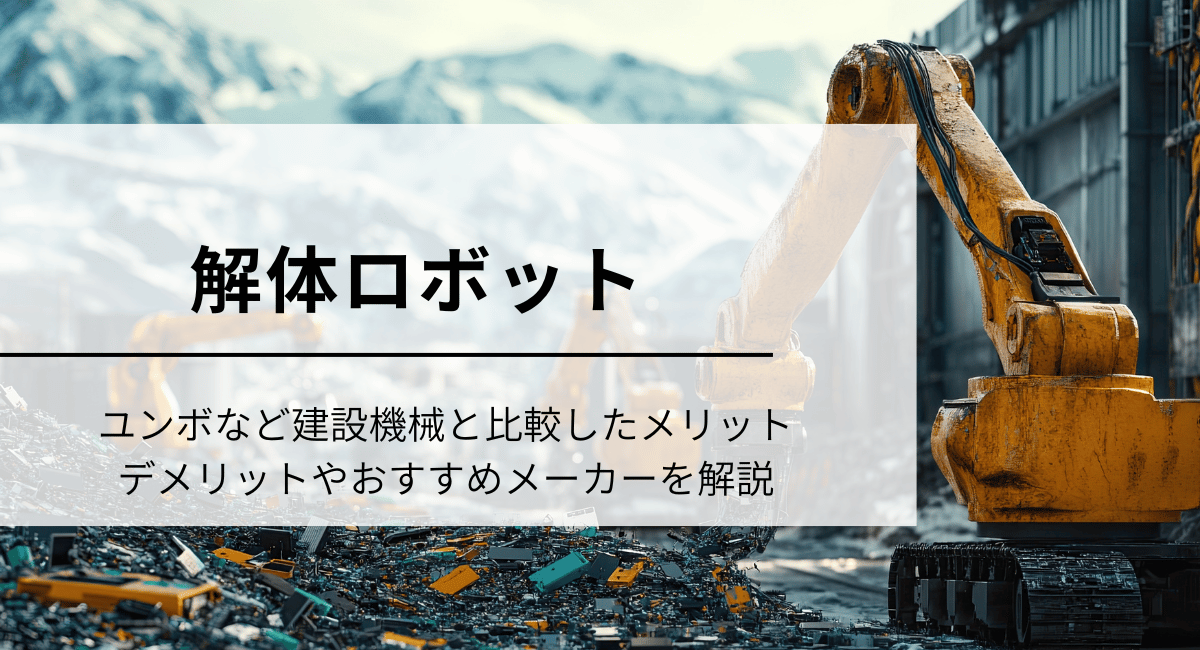
解体ロボットは、高リスクな解体作業を遠隔操作や自律運転で行うことで作業員を危険から遠ざけ、省人化と安全性向上を図る建設機械です。
「どの機種を選べばよいのか」「導入コストは?」「自社の現場に適応できるのか」といった不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では解体ロボットの基本的な仕組みから、解体機械との違い、人手不足に対する有効性、選び方の具体的なポイント、そしておすすめのメーカーも解説しています。
自社に最適な解体ロボットを選定するために、技術的な視点と導入実績の両面から情報を整理しました。
これから導入を検討する方にとって、お力になれたら幸いです。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
また、JET-Roboticsでは、解体ロボット以外にもさまざまな建設ロボットを解説しています。建設ロボット全体について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
最近の更新内容
2026/1/22更新 企業情報の更新
解体ロボットとは? 仕組みや技術を解説

解体ロボットとは、建物の解体現場における作業の一部またはすべてを、自動化・機械化することを目的として開発されたロボットです。
人手不足や高齢化、安全性の確保などの課題に対応するため、国内外で注目を集めており、特に解体現場においては高リスク作業の代替手段として注目の技術です。
構造物の破砕や切断、粉塵対策、搬出などを高い精度で行うことができ、従来の重機では対応困難だった作業もこなせるなど、既存の重機の幅に囚われません。
実現には課題も伴いますが、解体ロボットは安全性・効率性・省人化を向上させ、現場に大きな変革をもたらすことを期待されています。
建設ロボットの仕組みと技術
建設ロボットは、複数のテクノロジーが融合したシステムで構成されています。
センサー、画像認識、AI(人工知能)、アクチュエーターなどが一体化し、現場の状況に応じた動作をリアルタイムで判断・実行する構造です。
※現在、広く解体ロボットと呼ばれているものの中には画像認識やAIが搭載されていないものもあるので注意して下さい。
AI搭載のものの場合、切断対象の材質や厚さをセンサーが検出し、過去データと照合したうえで適切な圧力と速度で解体を行うよう自動制御されます。AI未搭載のものは、従来通り遠隔で操作する人間が判断と操作を行わなければなりません。
AI搭載のものは、従来では職人の勘と経験に依存していた作業を、均質かつ安全に遂行することが可能となっています。
次は、以前から使われている建設機械の油圧ショベルと、解体ロボットを比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理していきましょう。
建設機械と比較! 油圧ショベル(ユンボ)と解体ロボットのメリット・デメリットを比較

解体現場では、以前から使われてきた建設機械「油圧ショベル(ユンボ)」と、近年導入が進んでいる「解体ロボット」が併用されるケースが増えています。
これらは外見や使用目的が似ているものの、運用スタイル・作業効率・安全性など多くの面で違いがあります。
ここでは、両者の特徴を客観的に比較し、それぞれの長所・短所を理解したうえで、適切な使い分け方を探っていきましょう。
油圧ショベル(ユンボ)の特徴とメリット・デメリット
油圧ショベル(ユンボ)は、土木・解体・積込・運搬など多様な作業に対応できる万能建設機械として、長年にわたり現場で活用されてきました。
オペレーターがキャビンに乗り込み、レバーやペダルを操作して作業する方式が一般的です。
解体ロボットの特徴とメリット・デメリット
解体ロボットは、高リスクな作業を無人または遠隔から安全に実施できる点が特徴です。AIやセンサーによる環境認識能力を備えたものも実験段階にあります。
また、天井や高所、床下の撤去など複雑な状況にも対応可能な柔軟性があり、機動性の高い小型タイプが増えているようです。
将来的には現場に応じた動作パターンの最適化や、施工記録データの保存といった「スマート施工」ができるようになる可能性もあり、注目されています。
このように、油圧ショベル(ユンボ)は「幅広い対応力」と「導入のしやすさ」、解体ロボットは「高精度な自動作業」と「安全性の高さ」に優れています。
両者は対立関係ではなく、現場の特性や作業内容に応じて適材適所で併用されることが理想的です。
実は、解体ロボット市場はまだ発展途上で、分類がはっきりされていません。
そのため「解体ロボット」と一口に言っても、現在「解体ロボット」と呼ばれている広義の意味と、正確なロボットの定義に当てはまる狭義の「解体ロボット」の2種類が混在しています。
そのため次章では2種類の特徴を踏まえたうえで市場の整理をし、JETが「解体ロボット」と定義する領域を明確にしていきましょう。
解体ロボットの種類を整理! 遠隔型と自律型

解体ロボットは、大きく分けて「遠隔型」と「自律型」に分類されます。この2つは制御方法や現場での運用スタイルが大きく異なるため、目的に応じた使い分けが必要です。
遠隔型ロボットとは
遠隔型ロボットは、オペレーターがリアルタイムで機体を遠隔操作しながら作業を行うタイプです。
代表的な例として、無線通信で操作される油圧ショベル型ロボットや、ワイヤレスクレーンなどが挙げられます。
この方式のメリットは、人が危険な場所に立ち入らなくても済む点にあります。
ただし、基本的には人が常に操作を行っており、機械自体が自律的に判断・実行することはありません。
自律型ロボットとは
一方、自律型ロボットは、センサーやAIによって現場の状況を分析し、常に人間が操作をし続けなくても動作を行えるタイプです。
たとえば、対象物の構造や材質を読み取り、作業手順を自動的に最適化して実行したり、障害物を避けながら移動するなどの機能を備えています。
作業効率、安全性、標準化、データ活用などあらゆる側面で次世代の建設現場に必要とされており、JETでは今後の主流になると考えています。
JETの解体ロボットの定義
JETではロボットの定義を「知覚・思考・行動」の3つを持ち、部分的または完全に人の手を介さずに自律できるものとしています。
その点で行くと、遠隔型は遠隔で操作できるものの、人が常に操作しなくてはならず、知能が欠けているためJETの定義ではロボットではないと判断されてしまいます。
ここまでは、広義に解体ロボットと呼ばれている、遠隔型、自律型どちらもを対象に説明してきました。
しかしここからは、「自律型」のロボットのみを『解体ロボット』と定義して、説明する内容は自律型のみの説明します。
次章では、自律型の解体ロボットが業界の課題である「人手不足」にどう貢献し、どのような導入課題があるのかを深掘りしていきましょう。
建設ロボットによる自動化は人手不足を解消できるのか 浮き彫りになる課題も

建設業界では長年にわたり人手不足が深刻な問題となっており、特に解体現場においては高齢化の影響が顕著です。
若年層の担い手が減少している一方で、熟練工の引退が進み、作業の継続そのものが難しくなっている現場も少なくありません。
こうした背景から、建設ロボットの導入は「人手不足の抜本的な解決策」として期待されています。
しかしその実態はどうなのか、メリットと共に見えてきた導入課題についても丁寧に解説します。
ロボット導入による人手不足対策の可能性
自律型の解体ロボットは、1人のオペレーターが複数台の機体を同時に管理できる仕組みを持ち、現場作業員の数を減らしても高い生産性を維持することが可能です。
また、これまで熟練工の「経験」に頼っていた判断や技能を、AIやアルゴリズムに置き換えることにより、属人的だった作業を標準化しやすくなると言われています。
これにより、新人でもすぐに作業に参加できる環境が整い、現場教育の負担も軽減されることでしょう。
さらには、長時間労働や危険な作業の削減にもつながり、労働環境の改善にも寄与します。こうした利点から、自治体や大手ゼネコンを中心に解体ロボットの導入が進んでいくでしょう。
導入時に浮き彫りとなる課題
一方で、導入にはいくつかの障壁も存在します。特に多くの現場で共通して指摘されているのが以下の3点です。
- 初期投資の大きさ:高性能な自律型ロボットは1台数百万円〜数千万円と高額であり、導入コストがネックになるケースがあります。
- 対応人材の不足:ロボットを運用・保守できる技術者や管理者の人材育成が追いついていない現状があります。
- 現場適応への調整負荷:施工現場は常に異なる条件で構成されており、AIやセンサーの調整に高い柔軟性が求められます。
加えて、ネットワーク環境の整備や、ロボットの稼働ログをもとにしたデータ管理体制の構築など、デジタルインフラの整備も並行して求められる点は見落とせません。
このように、建設ロボットは人手不足の大きな助けになる一方で、導入から定着までには戦略的に行わなければ効果はあまり大きくならないでしょう。次章では、この章の内容を踏まえて、解体ロボットを選ぶときのポイントをお伝えします。
解体ロボットの選び方!後悔しないために確認すべき3つの視点

解体ロボットの導入においては、現場の制約や作業条件に応じた適切な機種選定が重要です。
特に建物の構造や電源設備、作業対象の種類によって選定基準が変わるため、選び方を間違えると工程の遅延や事故にも直結します。
ここでは、後悔しないための代表的な3つの視点から、解体ロボット選定のポイントを解説します。
【重量と大きさ】現場の搬入経路と床耐荷重に合わせた重量の選定
解体ロボットを選定するうえで、まず重要なのが現場の搬入経路と床耐荷重に合わせて重量クラスを選定することです。
この判断は、搬入口の幅や高さ、階段・エレベーターの有無、建物のスラブ耐荷重、現場に設置可能なクレーンの能力など、複数の物理的条件によって左右されます。
もし適正を無視して過大な重量機を選んでしまえば、スラブを破損させるリスクがあるだけでなく、現場にクレーンを追加せざるを得ず、コスト増加や工期遅延を引き起こします。
特に中高層ビルの内装解体や老朽化したスラブ構造の建物では、この点を重視する必要があるでしょう。
最適な重量の製品を選ぶことで、上階でもクレーンレスで搬入でき、設置後すぐに稼働可能となり、段取りのための日数を大幅に短縮できます。
【動力選定】電源容量と排ガス規制に応じて動力を選ぶ
次に考慮すべきは、作業環境の電源容量と排ガス規制に応じて電動(有線/バッテリー)かハイブリッド動力を選ぶという視点です。
これは、現場における電源供給の有無、室内・地下などの換気環境、さらには日中/夜間の稼働シフトなどの要因によって判断されます。
不適切な動力方式を選択すると、排ガスが規定値を超えたり、充電切れによりロボットが停止してしまい、連続作業ができずに工期全体が伸びてしまいます。
特に地下階や商業施設の夜間施工といった密閉性の高い現場では、排ガスへの配慮が欠かせません。
現場の環境に合った適切な動力選定が、現場の準備コストと作業準備時間を削減できるでしょう。
【アーム選定】対象部材と作業手順に合わせてアーム構造を選定する
そして最後に重要なのが、対象部材と作業手順に合わせて単腕・二腕・伸縮ブームなどアーム構造を選定するという観点です。
アーム構造は、作業対象となる部材の高さ、厚み、梁や壁の位置関係、周囲の障害物の有無といった要因に大きく依存します。
この検討を怠ると、アームのリーチや可動範囲が不足し、解体対象に届かずに手壊し作業が必要となり、安全事故や余計な人件費の発生を招く恐れがあります。
特に鉄骨構造の高所作業や吹き抜け部など、仮設床が設けにくい現場では、アームの構造が施工の可否を左右すると言っても過言ではありません。
適切なアームを選定することで、梁を確実に把持しながら切断ができ、落下物事故のリスク減ると言われています。
これで、解体ロボットの選定における重要な視点を3つ紹介しました。続いては、実際にどのようなメーカーが自律型の解体ロボットを開発しているのか、代表的な製品と併せて見ていきましょう。
解体ロボットのおすすめメーカーを紹介! 製品特徴と実績

ここでは、解体ロボットの分野で注目されるメーカーについて、それぞれの特徴や代表製品、導入事例をもとに詳しく紹介します。
導入を検討している方が、自社のニーズに合ったメーカーを見つける手がかりとなるよう、強みや実績を整理しました。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- オカダアイヨン / Okada Aiyon
- TopTec Maschinen / トップテック・マシーネン
- Husqvarna / ハスクバーナ
※クリックすると該当箇所まで飛びます
オカダアイヨン / Okada Aiyon
長年培ったアタッチメント開発の知見を、ロボット本体の設計に活かせる点に強みを持つメーカーです。解体ロボットの「e-ROBO」は、電動のため排ガスや騒音が少なく、狭い場所でもパワフルに作業できる点が特徴です。ビル内部やトンネルといった閉鎖空間や、市街地での精密な解体作業を担う建設・土木業界に導入されています。
TopTec Maschinen / トップテック・マシーネン
顧客の個別要求に応える特殊環境向けの設計・開発力に強みを持つメーカーです。同社の解体ロボット「TopTec 1850 E」は、コンパクトな設計で狭い場所への進入が容易であり、遠隔操作で安全に作業できる点が特徴です。原子力施設の廃炉作業や製鉄所、トンネル工事といった一般の重機が入れない特殊な業界に導入されています。
Husqvarna / ハスクバーナ
300年以上の歴史で培った技術力と、幅広い建設機器を開発する総合力に強みを持つメーカーです。同社の解体ロボットである「DXRシリーズ」は、軽量ながら高いパワーを持ち、直感的に操作できるリモコンで精密な作業が可能な点が特徴です。床の耐荷重が限られる建物内部や、作業員の立ち入りが危険な現場を扱う解体・建設業界に導入されています。

