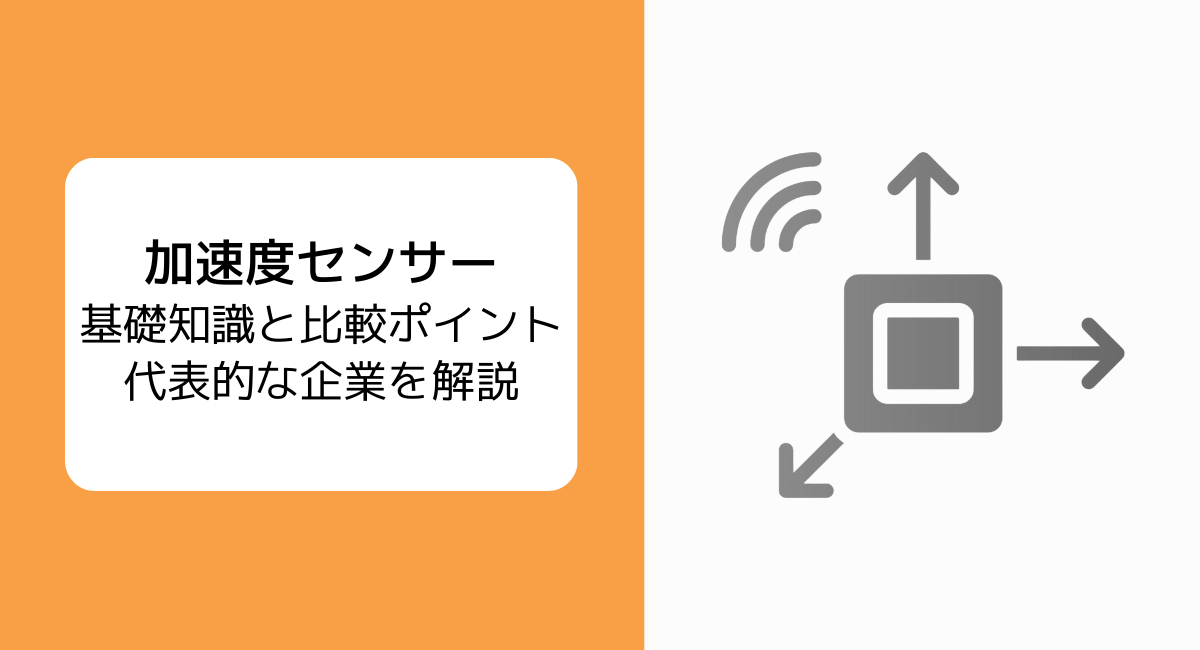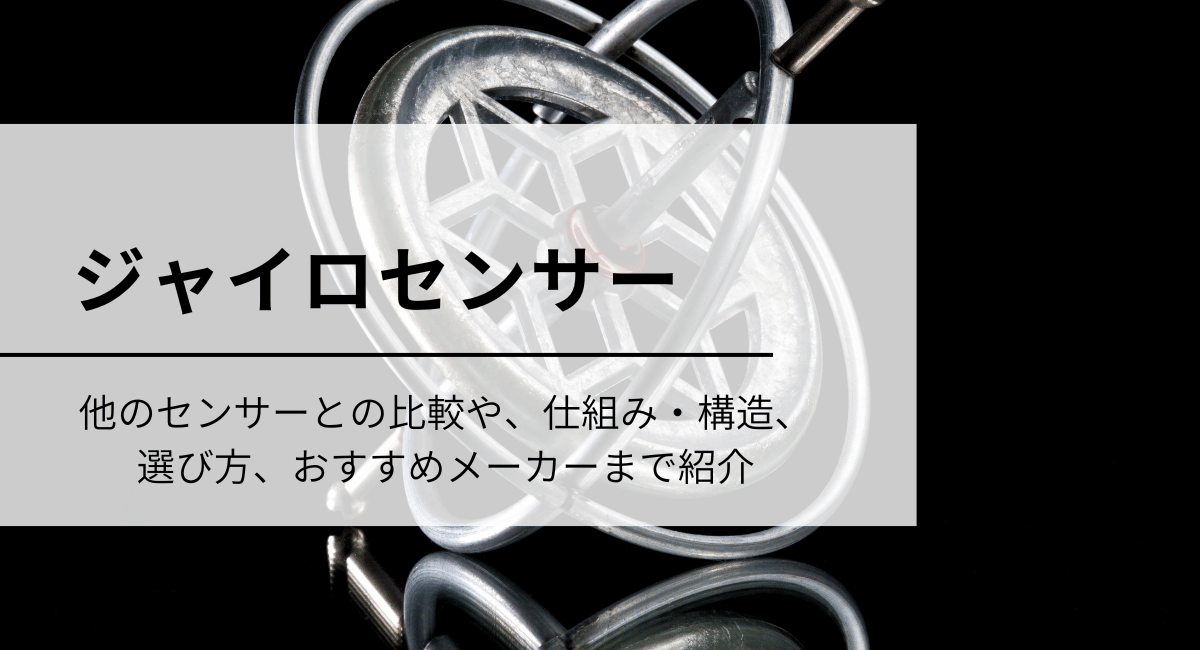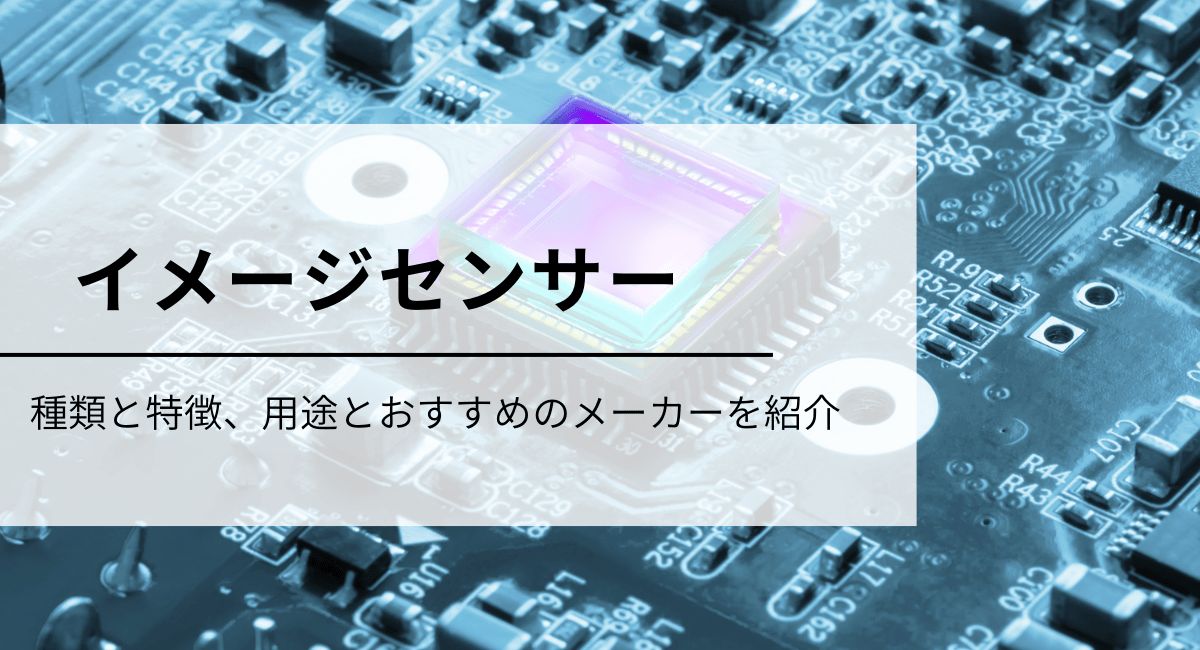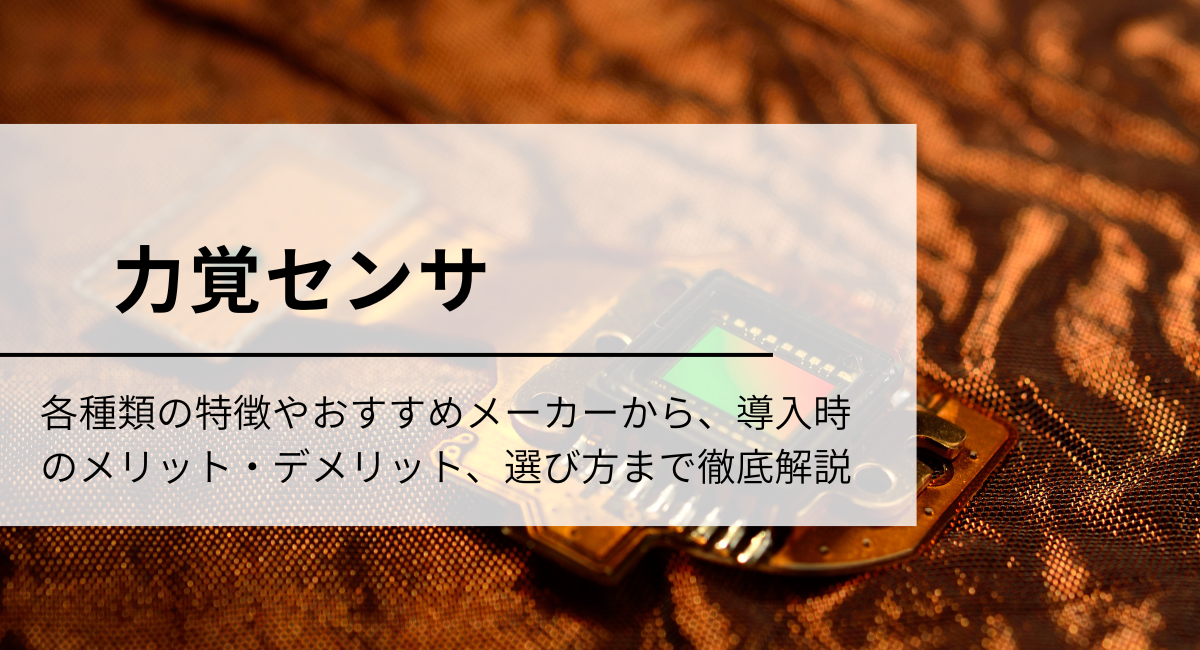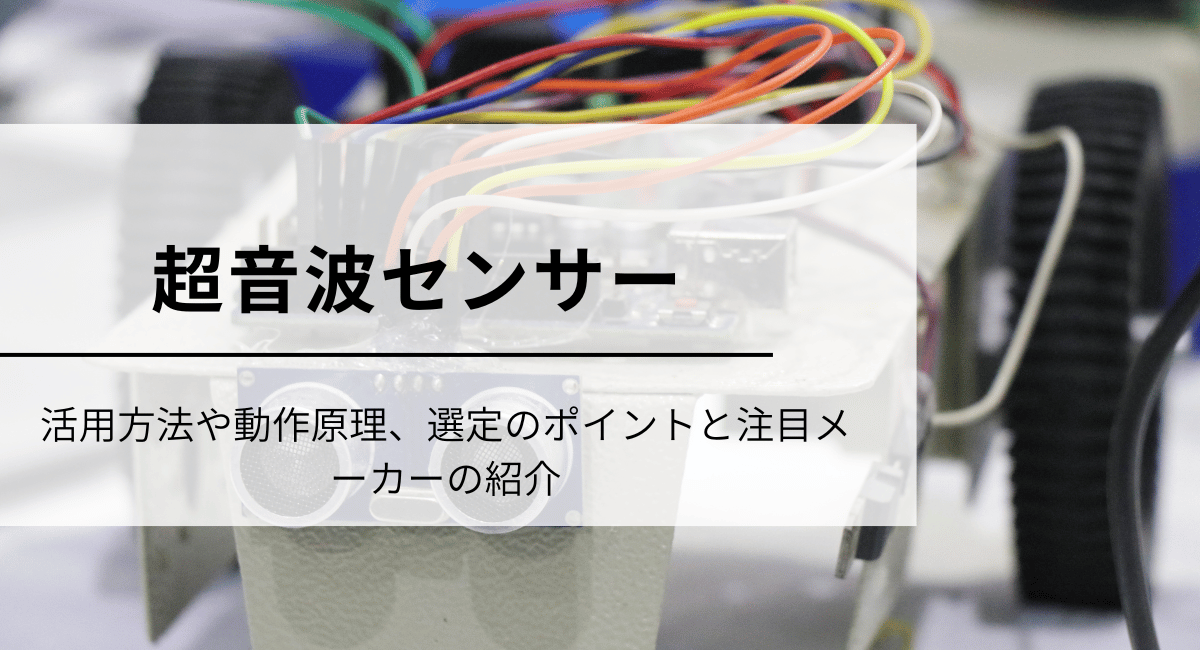ロボットセンサ
ロボットセンサとは? 各種類の特徴と活用例や将来性、おすすめメーカーを解説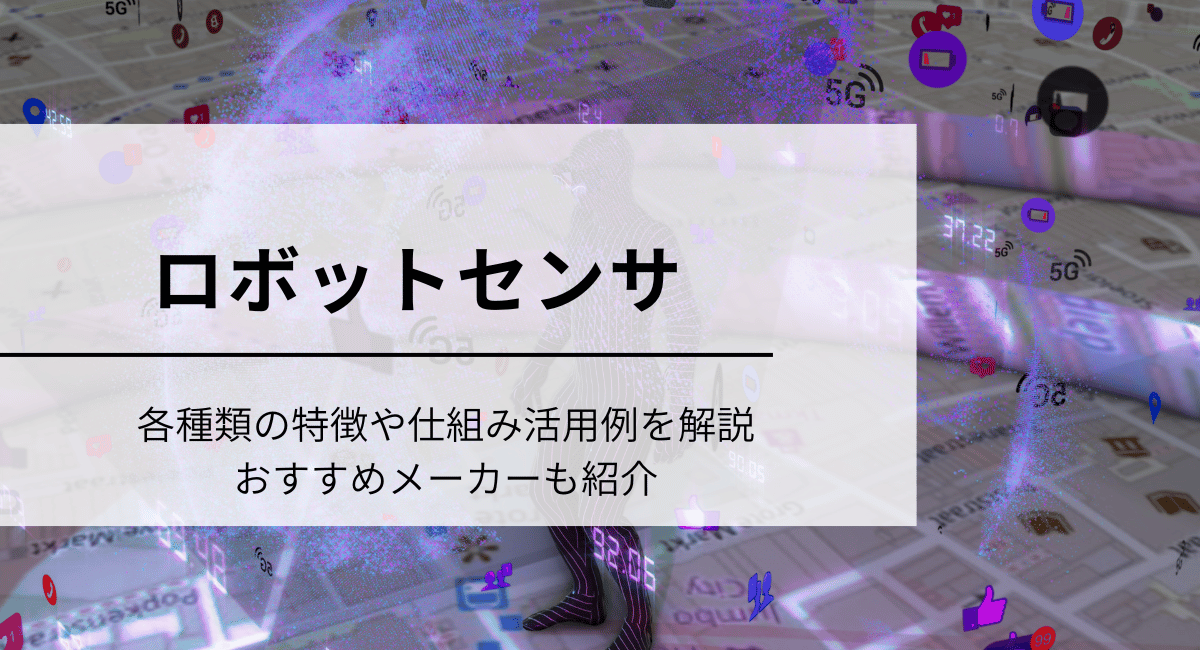
近年、製造業や物流分野においてロボット活用が加速する中、その性能を最大限に引き出す中核技術としてロボットセンサが注目されています。
「どのセンサが自社に合っているのかわからない」「環境に合わず誤検知が多い」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ロボットセンサの仕組みや種類、現状の課題と将来性、選定時に見るべき評価軸、そしておすすめの国内メーカーまでを解説します。
ロボット導入を成功させたい方にとって、本記事が最適な選定と判断を後押しする確かな手がかりになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
※一部メーカーとは提携がない場合がありますが、ユーザー様に最適なご案内ができるよう努めています。
目次
ロボットセンサとは? 仕組みや役割などをわかりやすく解説
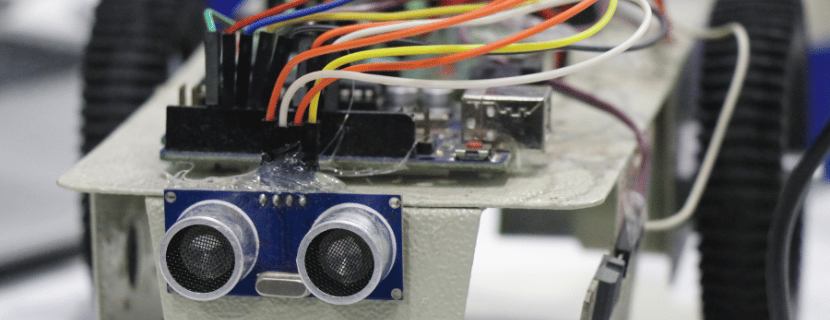
ロボットの進化とともに欠かせない存在となっているのがロボットセンサです。本章ではまず、ロボットセンサの仕組みや産業ロボットとの関係性について解説します。
ロボットセンサの定義と仕組みを解説
ロボットセンサとは、ロボットが自律的に動作するための「感覚器官」にあたる重要な構成要素です。センサから取得される情報を基に、ロボットは外部環境や自身の状態を認識し、適切な判断や動作を実行します。
ロボットセンサが取得した情報は、アナログ信号またはデジタル信号としてロボット制御装置(コントローラ)へ送られます。制御装置でこれらの信号をリアルタイムで解析しすることで、必要な動作制御(回避、調整、制動など)が可能です。
最近ではAIやエッジコンピューティングと組み合わせて、複雑な環境下でも高精度な認識と判断を実現するシステムが増えてきています。
産業用ロボットとロボットセンサの関係性とは?
産業用ロボットは、製造現場において多様な作業を担う高度な自動化装置ですが、その柔軟性や正確性を担保しているのがロボットセンサです。
例えば、自動車工場で稼働する溶接ロボットは、トーチの位置や姿勢をセンサで検知し、わずかなズレも自動で補正します。また、組立ロボットでも、センサを活用して部品のはめ合い時の圧力を監視し、過剰な力による破損を防止可能です。
さらには、可搬ロボットやAMR(自律移動型ロボット)においては、LiDARやステレオカメラによる外界認識を行い、人や障害物を検知しながら経路をリアルタイムで調整します。
これらのロボットセンサがなければ、ロボットは外部の変化に対応できず、固定的・単調な動作しか実現できません。つまり、ロボットセンサは、産業用ロボットの「目」「耳」「皮膚」など体の一部となって、複雑な作業への対応力を高めているのです。
以上のように、ロボットセンサはロボット技術の根幹を成す存在であり、その高度化は自動化・省人化の実現に直結します。次の章では、ロボットセンサの種類ごとの特徴について詳しく見ていきましょう。
ロボットセンサの種類を解説
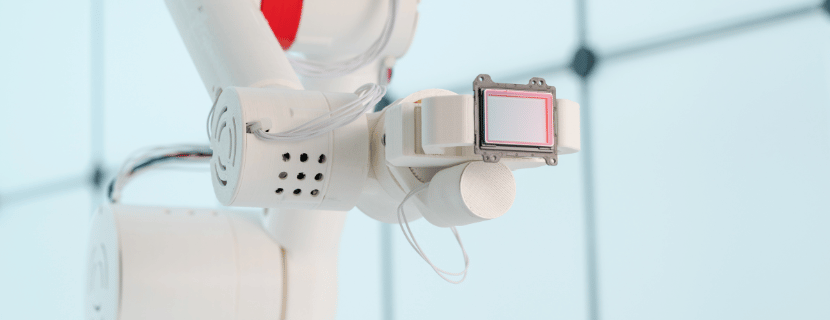
ロボットセンサは、「内界センサ」と「外界センサ」の2種類に大別されます。ここでは、それぞれのカテゴリーに属する代表的なセンサについて、仕組みや役割、活用される場面を詳しく解説します。
内界センサ
内界センサとは、ロボット自身の動作状態や内部の物理量を測定するセンサ群です。これらのセンサは、位置・角度・速度・温度・電流などの情報を取得し、ロボットが正しく制御・自己診断できるように支援します。
本節で解説する内界センサは以下の4つです。
- エンコーダ
- IMU(加速度センサ&ジャイロスコープ)
- 温度センサ
- 電流センサ
エンコーダ
エンコーダは、回転軸の角度や回転速度を高精度に計測するロボットセンサです。主にモーター軸や関節部分に取り付けられ、ロボットアームの位置制御やサーボ制御に使われます。
仕組みとしては、光学式・磁気式などがあり、相対位置検出と絶対位置検出の2種類に分かれます。
特に、組立ロボットや協働ロボットの精密制御などに欠かせません。
IMU(加速度センサ&ジャイロセンサ)
IMUは、加速度センサとジャイロセンサを一体化した慣性計測装置です。加速度センサは直線加速度を、ジャイロセンサは角速度を検出します。
ロボットの姿勢制御やバランス保持などに用いられます。近年は地磁気センサを加えたIMUも一般的です。
加速度センサやジャイロセンサについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
温度センサ
温度センサは、ロボット内部の電子部品やモータの発熱状態を監視するロボットセンサです。
温度感知には、サーミスタや熱電対などが主に使用され、過熱による故障を防ぐためのフェイルセーフ機構に組み込まれています。ロボットアームや搬送ロボットでの安定動作維持に役立っています。
電流センサ
電流センサは、ロボットに供給される電流量を監視するロボットセンサです。
モータ駆動時の消費電流や異常電流をリアルタイムで検出し、過負荷やショートの早期発見に活用されます。ホール効果を利用した非接触型の電流センサが多く、ロボットの安全制御において重要な役割を果たします。
以上が主な内界センサの解説です。次節からは外界センサを解説します。
外界センサ
外界センサは、ロボットの周囲環境を認識するためのセンサです。対象物との距離や形状、音、光、圧力、気体成分など多岐にわたる情報を取得し、人間との協働や環境変化への対応に役立ちます。
本節で解説する外界センサは以下の5つです。
- イメージセンサ
- 圧力センサ
- 距離センサ
- 音センサ
- ガスセンサ
イメージセンサ
イメージセンサは、ロボットに視覚情報を与えるロボットセンサで、対象物の色・形状・位置などを画像として取得します。
2Dカメラは平面的な認識、3Dカメラは立体的な物体認識が可能です。特に、ロボットビジョン、外観検査、自動ピッキングなどで広く活用されています。ステレオカメラやToFカメラなどの派生技術も存在します。
イメージセンサーについてより詳しく知りたい方は、イメージセンサーに特化した以下の記事をご覧ください。
圧力センサ
圧力センサは、物体との接触による力を検出するロボットセンサです。
ロボットハンドやグリッパに力覚センサとして搭載され、つかむ力を適切に制御し、対象物を壊さずに把持するために使われます。膜式や静電容量式などの方式があり、人との接触力を感知する協働ロボットにも多く利用されています。
力覚センサについてより詳しく知りたい方は、力覚センサに特化した以下の記事をご覧ください。
距離センサ
距離センサは、対象物との距離を非接触で計測するロボットセンサです。代表的な方式には以下があります。
- 超音波センサ
- LiDARセンサ
- 赤外線センサ
音波の反射時間を利用して距離を計測。障害物検知などに有効。
レーザー光の飛行時間を計測して高精度に距離や形状を取得。自律走行ロボットで広く使用。
赤外線の反射を用いて距離を検出。簡易的な近接検知に用いられる。
用途としては、障害物回避、作業対象の距離測定、安全柵の検知などがあり、移動型ロボットやアーム制御に広く導入されています。
超音波センサーやLiDARセンサについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
音センサ
音センサは、周囲の音を拾って音源の有無や音の強度を検出するロボットセンサです。
マイク型のセンサを使い、作業現場での異常音検出や、人間の声とのインタラクション、設備稼働音の記録分析などに使われます。近年では機械学習と組み合わせた異音検出にも応用が進んでいます。
ガスセンサ
ガスセンサは、特定のガスの存在や濃度を検出するロボットセンサです。
半導体式や電気化学式、赤外線式などの方式があり、一酸化炭素、メタン、揮発性有機化合物(VOC)などの検知が可能です。工場内の安全監視、発煙検知、有毒ガス検知などに用いられます。
このように、ロボットセンサは情報の取得対象によって内界センサと外界センサに分かれ、それぞれ多様な技術と仕組みでロボットの知覚能力を支えています。
次章では、こうしたロボットセンサが抱える現状の課題と、今後期待される技術的進化を見ていきましょう。
現状の課題と未来|ロボットセンサの将来性

先述したように、ロボットセンサは多くの分野で実用化が進み、高度な自律性や安全性の実現に貢献しています。しかし一方で、環境依存性や導入コスト、データ処理の負荷など、運用面での課題も顕在化しています。
ロボットセンサの課題
現在のロボットセンサにおける大きな課題のひとつは環境の影響を受けやすい点です。
たとえばカメラや距離センサは、照明条件や対象物の素材(反射率や透明度)によって認識精度が変化します。屋外や変化の激しい現場では、誤認識やノイズによる誤作動が課題となっています。
次に挙げられるのがセンサ同士のキャリブレーションや統合の難しさです。
たとえばIMUとカメラ、LiDARを組み合わせる場合、それぞれの時刻・座標系を一致させる必要があり、設定やメンテナンスの手間がかかります。これにより、導入・運用のハードルが高まっています。
さらに、リアルタイム処理における計算負荷も見逃せません。
高精度センサの多くは大量のデータを出力するため、AI処理やフィルタリングをリアルタイムで行うには、GPUやFPGAなど高性能な演算装置が必要となります。これはハードコストの上昇や設計スペースの制限をもたらします。
ロボットセンサの将来性
現状のロボットセンサには上記のような課題がありつつも、これらの課題を解決に導く次世代技術も登場しつつあります。
ひとつは、複数のセンサ情報を融合処理するセンサフュージョンの高度化です。時間軸と空間軸を一致させることで、個別センサの弱点を補い、より信頼性の高い認識が可能になります。
また、AIチップの進化により、ローカル処理能力の向上が進んでいます。これにより、センサから得られるデータをクラウドに依存せず、端末内で即時処理できるようになり、リアルタイム性と安全性が同時に向上していくでしょう。
加えて、低コスト・小型・高耐環境性を兼ね備えたセンサも多く登場しており、過酷な環境下やモバイルロボットへの搭載が容易になっています。たとえば、全天候対応型のステレオカメラや、自己診断機能を備えたIMUなどは、今後の主流になるでしょう。
このように、ロボットセンサの進化は、ロボット技術全体の将来性を支える基盤となります。次章では、ロボットセンサを導入・選定する際に見るべき評価軸について、わかりやすく解説します。
自社に適合するロボットセンサの評価軸を解説
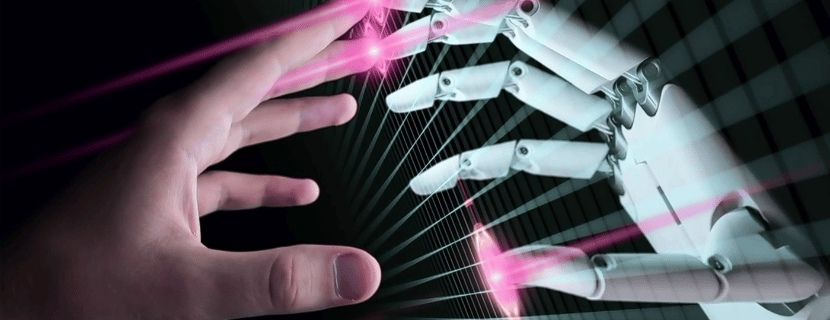
ロボットセンサを導入する際には、単に価格や機能だけでなく、導入環境や作業内容に応じた評価軸で比較検討することが重要です。ここでは、実際の導入現場で失敗を避けるために必ず確認すべき3つの評価ポイントを詳しく解説します。
計測方法が検知対象と作業環境に適合しているか
ロボットセンサの評価軸として、計測方法が検知対象と作業環境に適合しているか確認することが挙げられます。
対象物の材質や形状、必要な分解能、測定距離、照明環境などの条件に応じて最適な計測方法を選定する必要があります。
仮に適合しないロボットセンサを選んでしまうと、対象を正確に検出できず、位置ずれや誤認識といったトラブルが頻発するでしょう。特に光沢のある金属や透明な樹脂など、検知が難しいワークを扱う現場では慎重な選定が求められます。
適切な計測方法を選べば、視認精度が向上し誤検知を減らして、作業品質や生産効率の向上につながる可能性が高いです。
センサのデータ更新周期と通信遅延がロボット制御周期に合うか
ロボットセンサを評価する上で、センサのデータ更新周期と通信遅延がロボット制御周期に合うか確認することも重要です。
センサが取得したデータを制御系にリアルタイムで反映できなければ、急な環境変化に対応できず、衝突や制振ミスを引き起こす可能性があります。
特に、高速搬送や人と協働するような環境では、通信遅延が直接安全性に関わるため、より厳格な選定が求められるでしょう。
適正な周期のロボットセンサを選定することで滑らかな動作と高い安全性を実現できるでしょう。
キャリブレーション手法の容易性
最後に、キャリブレーション手法の容易性を評価することも、ロボットセンサ導入後の安定運用には不可欠です。
適切なキャリブレーションが行えないと、座標ずれが補正できず、自動化ラインの精度が低下します。とくにセンサの交換や洗浄頻度が高い食品・医薬品業界では、素早く確実に調整できる構成が強く求められます。
簡易かつ再現性の高いキャリブレーションが可能であれば、ライン変更や保守時の停止時間を短縮できるため、全体の生産性にも貢献するでしょう。
ロボットセンサの選定は、細かな仕様の確認と実運用を想定した総合的な評価が求められます。次章では、おすすめのロボットセンサメーカーを紹介し、それぞれの強みや特徴について詳しく見ていきます。
おすすめのロボットセンサメーカーを紹介! 各社の強みも解説

ロボットセンサの導入を検討する際、どのメーカーが自社のニーズに最適かを見極めることは重要です。ここでは、国内のおすすめロボットセンサメーカーをピックアップし、それぞれの特徴や製品ラインアップ、導入事例などを詳しくご紹介します。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
※一部メーカーとは提携がない場合がありますが、ユーザー様に最適なご案内ができるよう努めています。
- キーエンス / KEYENCE
- パナソニックインダストリー / Panasonic Industry
- 北陽電機 / HOKUYO AUTOMATIC
※クリックすると該当箇所まで飛びます
キーエンス / KEYENCE
| 会社名 | キーエンス / KEYENCE |
| 設立年 | 1974年 |
| 本社 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-3-14 |
| 概要 | センサ・画像処理装置の専業メーカー |
キーエンスは、ファクトリーオートメーション分野のセンサ・ビジョンメーカーで、自社で開発した3Dビジョンと画像処理技術をベースに、現場に即応できる直販体制を構築している点が強みです。
3Dビジョンセンサ「XTシリーズ」など、精密な認識が求められるロボット用途に最適な製品を数多く提供しています。自動キャリブレーションとAIピッキング機能で難検知ワークも安定把持できる点が強みであり、認識精度と導入後の運用性の両立が図られています。
自動車部品ビンピッキングセルや食品包装ラインのピックアンドプレース、半導体外観検査ラインなど、精度とスピードが求められる現場での導入実績も豊富です。
パナソニックインダストリー / Panasonic Industry
| 会社名 | パナソニックインダストリー / Panasonic Industry |
| 設立年 | 2022年 |
| 本社 | 東京都港区虎ノ門二丁目6番1号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 22階、23階 |
| 概要 | 電気部品・電子部品・制御機器・電子材料等の開発・製造・販売 |
パナソニックインダストリーは、「未来の兆しを先取り、お客様とともに社会変革をリードする」をビジョンとして掲げた産業デバイス・センシング部品のメーカーです。独自のTOF技術を搭載したレーザ距離センサを開発しており、長距離測定でも高い精度を保持できる点が魅力です。
同社は、TOFレーザ距離センサ「HG-F1」など、小型で高性能な製品群を展開しています。3m先でも±1cm以下の再現性を実現する設計が、空間制約のある現場においてメリットとなるでしょう。
AGVの障害物検知、工作機械の無人段取りにおける位置決めといった用途で幅広く活用されています。
北陽電機 / HOKUYO AUTOMATIC
| 会社名 | 北陽電機 / HOKUYO AUTOMATIC |
| 設立年 | 1946年 |
| 本社 | 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番6号 肥後橋ユニオンビル9F |
| 概要 | 光通信機器、センサ、レーザ機器、計測機器、障害物検知センサ |
北陽電機は、オートメーションという言葉がまだ一般に普及する以前から自動制御を手がけ、顧客のニーズに応えていろいろな産業分野に役立つオンリーワンの商品を創出してきました。レーザースキャナおよびLiDARのメーカーで、可搬性と環境耐性を両立しています。
例えば、2D LiDAR「UTM-30LX」「URG-04LX」や安全レーザースキャナ「UXM-30LAH」などが代表的な製品です。
これらは、USBやEthernetでの簡単接続が可能で、AMRやAGVに柔軟に組み込みやすい点が際立ちます。
製品の中には、補助金を活用し導入コストを抑えることができるものもございます。
導入などでお困りでしたら以下からお気軽にご相談ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
ロボットセンサの製品はまだありません。