トンネル点検ロボット
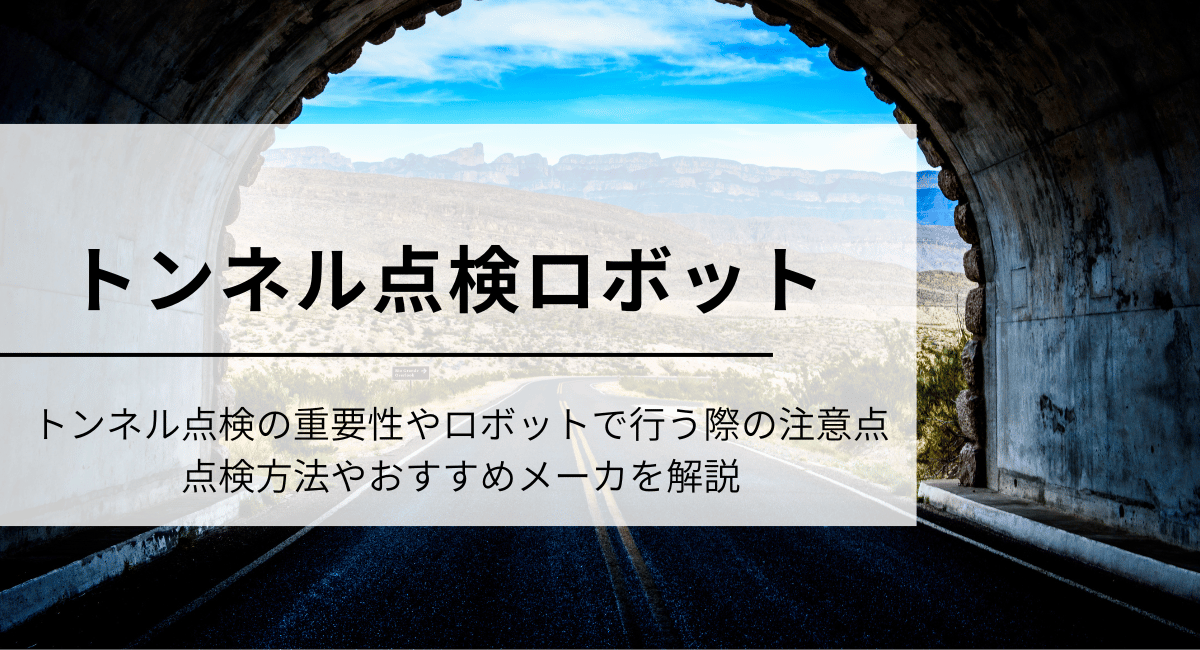
トンネル点検ロボットは、トンネルの老朽化や劣化を安全かつ効率的に確認するために開発されたロボットです。「人の手で確認するには危険が伴う」「精度にばらつきが出る」「作業時間がかかる」そう感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、トンネル点検ロボットの基本的な特徴や種類、導入のメリット、注意点をわかりやすく解説します。さらに、点検対象や現場環境に応じた選び方や、おすすめのメーカー情報も掲載しています。
トンネル点検業務の安全性・効率性を向上させたいとお考えの方にとって、実用的な判断材料となる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
目次
最近の更新内容
2026/1/23更新 企業情報の更新
トンネル点検ロボットとは? 特徴や最新技術を紹介
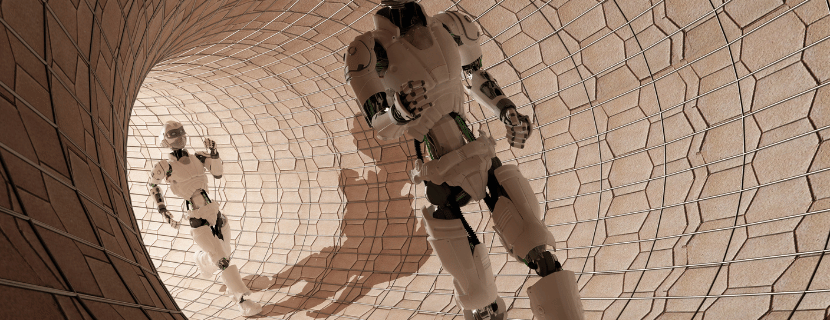
トンネル点検ロボットとは、トンネル構造物の劣化や異常を効率的かつ高精度に把握するために開発されたロボットです。人手による点検に比べて、安全性の向上・作業時間の短縮・コスト削減を実現する手段として注目されています。
これらは、トンネルの壁面を走行したり、ドローンとして空中を移動したり、ロボットアームを駆使して接触式の検査を行うなど、目的や環境に応じて様々な形状や技術が採用されています。
また、近年はAIや画像解析技術の進化によって、ひび割れや漏水などの異常箇所を自動で検出する精度が向上しており、点検データをクラウドにリアルタイム送信し、遠隔地でのモニタリングや履歴管理も可能になってきました。
点検対象は主にコンクリート構造の覆工面や構造物内部で、非破壊検査技術を組み合わせることで、目視では発見できない内部の劣化兆候も捉えることができます。
トンネル点検ロボットは今後ますます重要性を増し、インフラ維持管理の高度化に欠かせない存在となっていくでしょう。
次の章では、点検ロボットの「形状」や「点検手法」による分類について詳しく解説します。
形状や点検手法でトンネル点検ロボットを種類分け

トンネル点検ロボットは、その形状や搭載している点検技術によって、いくつかの種類に分類されます。現場の環境や点検目的によって、最適なロボットの選定が求められます。
ここでは、「形状による分類」と「点検手法による分類」の2つの視点から代表的なロボットタイプを紹介します。
形状による種類分け
接触式点検機器を搭載したロボットアーム型
ロボットアーム型のトンネル点検ロボットは、アームの先端に打音検査や触診センサなどを搭載し、覆工面に直接接触して点検を行うタイプです。主にトンネル内に設置された足場車両などに搭載される形で利用されます。
壁面走行車型
壁面走行車型は、トンネルの側壁や天井に吸着・走行しながら、画像やレーザーなどで点検を行う自律型のタイプです。磁石や吸盤、ファン吸引などの技術で壁面に密着します。
ドローン型
ドローン型のトンネル点検ロボットは、小型無人航空機を使って空中からトンネル内を点検する方式です。GPSが使えない環境でも、SLAM(自己位置推定)やセンサフュージョンにより安定飛行します。
点検手法による種類分け
打音点検
ハンマーやアクチュエータで覆工面を叩き、その音響反応から空洞や浮き、剥離などの異常を検出する伝統的かつ信頼性の高い手法です。近年ではロボットアームに自動打音装置を搭載し、定量的なデータを取得可能です。
画像解析
高解像度カメラで撮影した画像から、AIや画像認識アルゴリズムを用いてクラックや漏水、変色などを自動抽出する技術です。近年は3D画像解析やディープラーニングの導入で精度が向上しています。
レーダー探査
電磁波を用いた非破壊検査手法で、コンクリート内部の空洞、鉄筋の腐食、ひび割れ深さなどを計測できます。トンネル内部に設置した装置から放射されるレーダー波の反射を解析します。
サーモグラフィ
赤外線カメラを使用して表面温度を計測し、内部の異常や漏水箇所を視覚的に検出する手法です。点検中の気温や湿度に左右されやすいため、他の手法との併用が効果的です。
以上がトンネル点検ロボットの種類分けです。自社の目的に適した形状や点検方法は見つかったでしょうか?
次章では、トンネル点検の重要性を改めて確認し、ロボットで代替する際の注意点を解説します。
トンネル点検の重要性とロボットを使う際の注意点
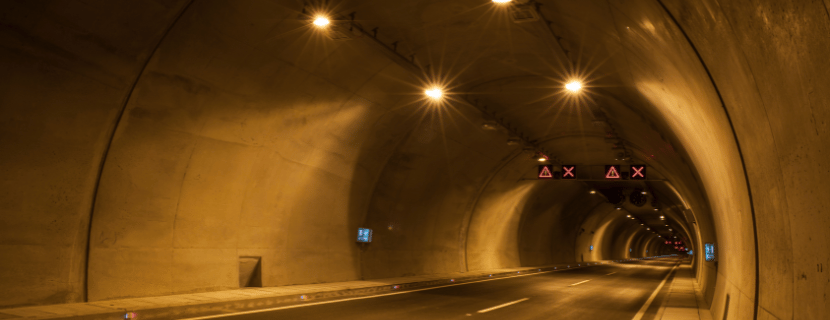
トンネルの安全性を維持するためには、定期的かつ精度の高い点検が不可欠です。点検ロボットの活用が進むなかで、その利点と導入時の注意点について理解を深めることが重要です。
トンネル点検の重要性
トンネルは一度建設されると数十年単位で使用され続けるため、構造物の経年劣化に対して継続的な監視が求められます。わずかなひび割れや漏水でも、放置すれば構造全体に影響を及ぼし、事故につながる可能性があります。
特に高速道路や鉄道など通行量の多いインフラでは、事前に異常を検知して補修を行う「予防保全」が大切です。
また、道路法などの法令により、5年に1度の近接目視点検などが義務付けられており、これを確実に実施することが安全性の確保と社会的責任を果たすうえで欠かせません。
適切な点検を通じて重大なトラブルを未然に防ぎ、長期的な維持管理コストの削減にもつなげることができるでしょう。
ロボット導入時の注意点
点検ロボットの導入により、安全性や作業効率の向上が期待されますが、現場ごとの条件を正確に把握したうえでの運用が不可欠です。
トンネルは形状や勾配、湿度、内壁素材などがそれぞれ異なるため、すべての現場に共通するトンネル点検ロボットというものは存在せず、目的に応じた選定が求められます。
点検の方式によっても必要とされるセンサーや機構が異なり、例えば打音検査にはアクチュエータと音響センサが必要となる一方で、ひび割れ検出には高解像度カメラや画像解析機能が求められます。
こうした機能の選定には、土木工学や設備管理に関する知識が必要です。
さらに、トンネル点検ロボットが取得した膨大なデータを正確に分析・判断するには専門的なスキルを持った人材が欠かせません。
AIによる自動判定が普及しつつありますが、すべてをAIに任せてしまうと誤検知や見落としのリスクも伴います。最終的な確認は人の目で行うという体制づくりが大切でしょう。
加えて、ロボット導入には高額な初期費用がかかることに加え、機材の操作に習熟したオペレーターの育成も必要です。導入効果を最大限に発揮するためには、単なる機器購入にとどまらず、組織全体での運用体制の構築が重要となります。
ここまででトンネル点検ロボットの基礎から種類・重要性までを解説しました。次章では、現場に適したトンネル点検ロボットをどう選べばよいか、選定のポイントを具体的に紹介します。
導入失敗を避けるために確認したいトンネル点検ロボットの選び方を解説

トンネル点検ロボットは、単に最新機能を備えているからといって、すべての現場に適しているとは限りません。点検対象の構造や目的に合わせて、最適な製品を選定することが重要です。
ここでは、導入失敗を避けるために確認すべき3つの視点を紹介します。
トンネル断面形状や路面状態に合った移動方式を選ぶ
トンネル点検ロボットの選定ポイントとしてトンネル断面形状や路面状態に合った移動方式(壁面走行・床走行・ドローンなど)を選ぶという観点があります。
この選択は、円形・馬蹄形・矩形などの断面形状や、内装材の凹凸・勾配・濡れ具合といったトンネル固有の特徴によって左右されます。
適合しない移動方式を選ぶと、走行不能や途中停止といったトラブルが発生し、点検作業が中断されたり、そもそも一部の構造が確認できないといった問題に発展しかねません。
特に、坑口が狭かったり、老朽化による路面の段差が激しいトンネルでは、この選び方が重要になります。
一度の走行で全周を均一にスキャンでき補修計画の精度が向上することで、現場の生産性と安全性を同時に高めることが可能です。
検査目的に対応したセンサー構成を備えているかを確認する
トンネル点検ロボットを選ぶ際には、検査目的に対応したセンサー構成を備えているかを確認しましょう。このポイントは、国交省が定める道路トンネル定期点検要領などで要求される劣化項目や診断精度といった要因によって決まります。
目的に合わないセンサーを搭載したトンネル点検ロボットを使うと、剥離や漏水、ひび割れといった重要な劣化を見逃すリスクがあり、結果的に大規模な事故につながる恐れがあります。
特に、国の基準に準じた精密調査を一度で完結させたい場合には、この選択が大切です。
一台で複数欠陥を同時検出でき現場作業と再点検回数を削減できることにより、調査の効率と信頼性が向上するでしょう。
電源・駆動方式がトンネル長と作業時間に適合するかを確認する
電源・駆動方式がトンネル長と作業時間に適合するかを確認するという点も実務では大事です。この判断は、対象トンネルの長さや勾配、作業できる通行止め時間の制限、さらに現地の電源設備の有無など、複数の現場条件に基づいて行われます。
不適切な駆動方式を選ぶと、点検中に電源が切れたりケーブルが絡まったりして、やむなく作業を中断したり、再入場による時間とコストの増大を招くかもしれません。
特に、長大な山岳トンネルで発電機の持ち込みが難しく、作業時間に厳しい制約があるようなケースでは、この選択の重要性が増します。
最長区間を一度で連続点検でき閉鎖時間や夜間作業コストを圧縮できるという利点を得られるため、必ず事前に確認しておくべき項目です。
ここまでで、現場に応じたトンネル点検ロボットの選定ポイントについて理解が深まったかと思います。次章では、実際に製品を製造している信頼性の高いメーカーを紹介します。
編集部が厳選したおすすめのトンネル点検ロボットメーカー

トンネル点検ロボットは各メーカーによって技術や特徴が異なります。ここでは、編集部が独自に調査したおすすめメーカーを紹介します。
※JET-Roboticsの問い合わせフォームに遷移します。
一部の会社とは正式な提携がない場合がありますが、皆さまに最適なご案内ができるよう努めています。
- 三井E&S / Mitsui E&S
- 首都高技術 / Shutoko Engineering
- 計測検査 / Keisokukensa
- JR東海 / Central Japan Railway
※クリックすると該当箇所まで飛びます
三井E&S / Mitsui E&S
船舶やプラント分野で培った高度な非破壊検査技術と精密計測力を、土木インフラ分野にも展開しています。同社の「トンネルキャッチャーTC3」は、高速道路を走行しながら点検できる車載型覆工撮影システムです。時速80kmで走行しながらも0.2mm幅のひび割れを検出でき、交通規制不要で点検できる精度とスピードが強みです。高速道路会社の供用中トンネル点検において運用開始され、国土交通省の性能カタログにも採択されています。
首都高技術 / Shutoko Engineering
首都高速道路の保守現場でのニーズをいち早く技術開発に反映できる体制が強みです。同社が提供するトンネル点検ロボット「やもりん®」は、施工中のトンネル覆工内部を精密に走行しながら検査できます。ネオジム磁石により型枠内のわずか70mmの隙間を安定走行し、施工できるだけ止めずに覆工品質を確認できる点が高く評価されています。首都高速道路のコンクリート打設現場で巻厚確認ロボットとして活用されており、現場での実績も豊富です。
計測検査 / Keisokukensa
画像処理技術と3Dレーザ点群をIMUやGPSと組み合わせて統合し、トンネル変状を定量的に可視化する技術が強みです。同社の主力製品である走行型トンネル点検車MIMMシリーズは、カラー画像と高分解能点群を同時に取得しながら、統合データを自動で展開図として出力できます。変状箇所を位置付きで自動生成できる統合データ化能力により、従来の記録作業を効率化できるでしょう。
JR東海 / Central Japan Railway
高速鉄道で求められる厳格な安全基準を満たすために、独自の自動打音ロボットを開発中です。現在開発中のトンネル検査ロボットは、壁面に沿って走行しながら連続打撃を行い、振動を計測して内部欠陥を評価します。人の技能に依存せず打音点検を定量化できる自律打音方式は、今後のトンネル点検の標準化を目指す取り組みです。山梨リニア実験線や小牧研究施設での検証を経て、中央新幹線トンネル保守への適用が検討されています。
