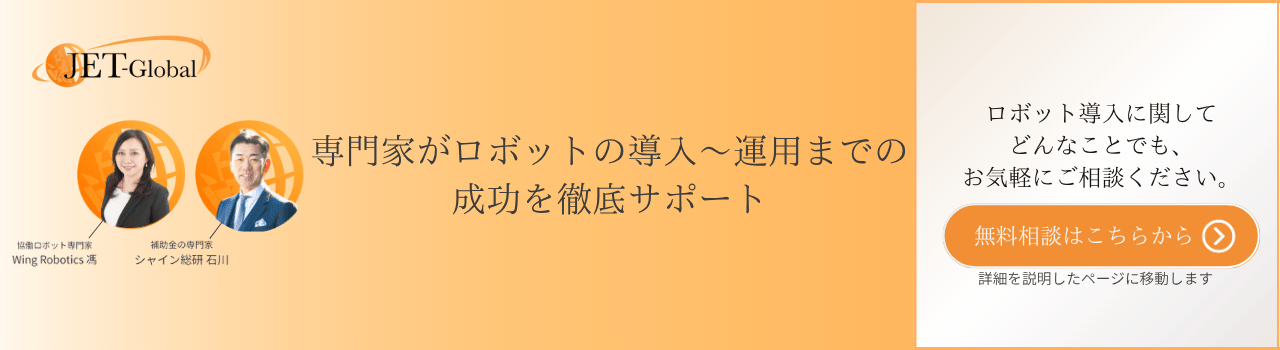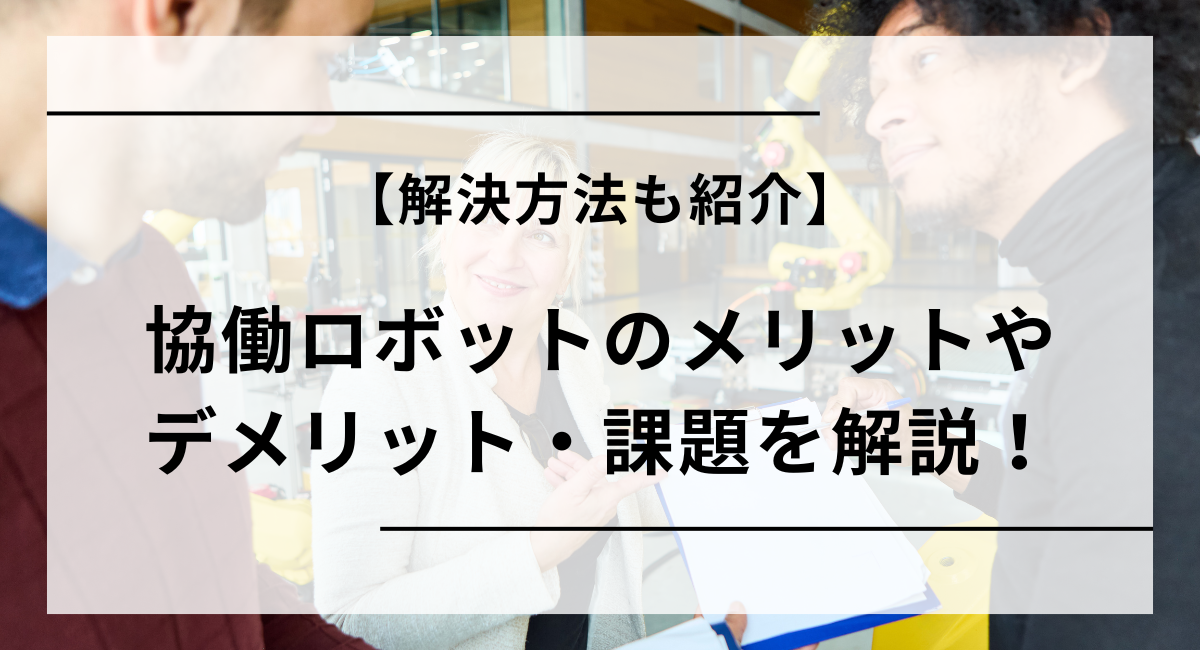
協働ロボットのメリットやデメリット・課題を解説!解決方法も説明します
協働ロボットを導入する企業が日本でも徐々に増えてきましたが、導入するとどのようなメリットを享受でき、どんなデメリットや課題に直面するのでしょうか。
本記事では、協働ロボットの基本的な特徴を押さえつつ、メリット、デメリット・課題を詳しく解説します。また、解説したデメリットや課題に対する解決策も紹介します。
協働ロボットを導入しようか迷っている方から導入することは決めたが不安が残っている方まで、必読の内容となっています。ぜひ最後までご覧ください。
また、JET-Roboticsでは実際に、協働ロボットの導入支援も行っております。
協働ロボットの専門家による製品の選定から補助金の活用、ロボット研修による社内人材の育成まで、協働ロボット導入をあらゆる面からサポートいたします。
「一度ロボットを触ってみたい」や「こんな自動化ができるか知りたい」などの軽い相談も可能です。
相談は無料ですので、関心のある方は以下のサービス詳細をご覧ください。
そもそも協働ロボットとは?導入が進む背景も紹介
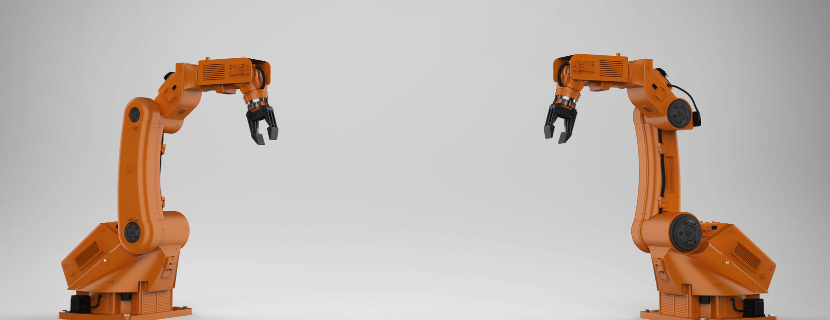
協働ロボット(コボット)とは、ISO規格で「人間と共に安全に作業できるロボット」と定義されており、安全装置やセンサー技術を搭載することで、人と同じ作業空間で稼働可能です。
従来の産業用ロボットは高出力と高速動作を重視するため、安全柵が必須でしたが、協働ロボットは衝突検知機能や力制御機能によって人との接触を回避・制限できるよう設計されています。
また協働ロボットの導入が進む背景には、少子高齢化による人手不足や2013年の規制緩和が挙げられます。安全柵を必ずしも必要としない運用が可能になったことで、狭いスペースや変種・変量生産にも柔軟に対応しやすくなりました。
さらに、プログラミングが直感的に行える協働ロボットが増え、専門家がいなくても比較的短期間で運用を始められる点も普及の大きな後押しとなっています。
以下の記事では、協働ロボットの全体像についてより詳しく触れています。具体的には、協働ロボットの特徴や定義、産業ロボットとの違いを解説しています。
協働ロボットの基本的な事項において、もっと詳しく知っておきたい方はまずはこちらをご覧ください。
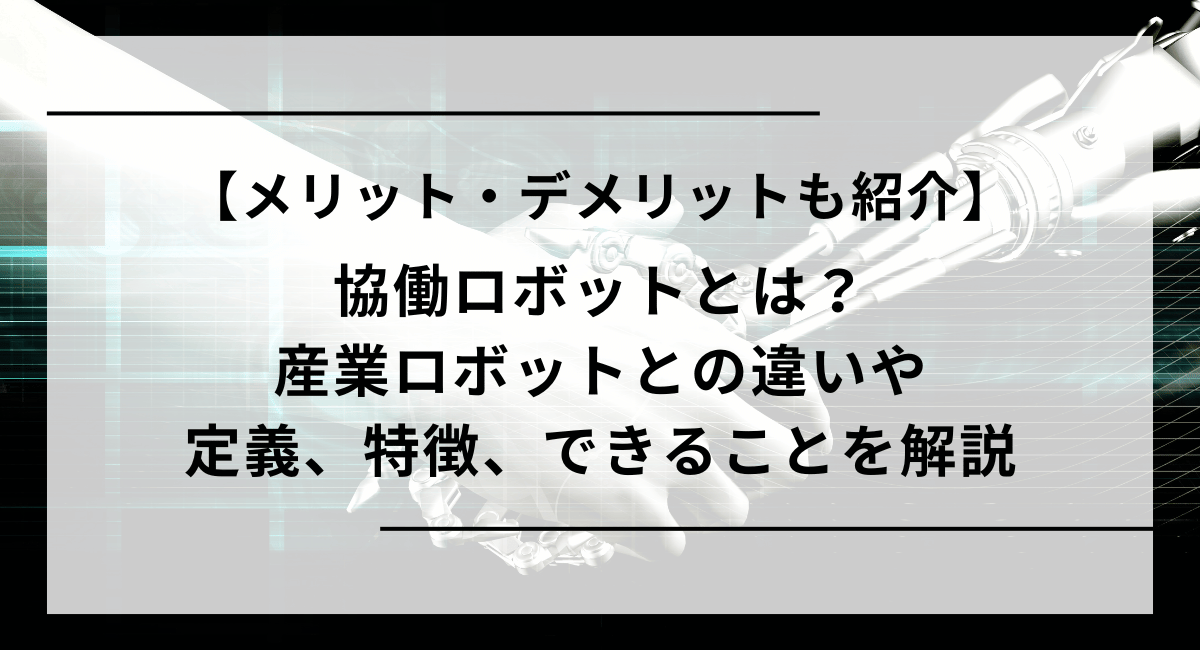
協働ロボットの基本を押さえたところで、次章からは協働ロボットのメリット・デメリットを解説します。
まずはメリットから解説するので、先にデメリットを知りたい方は、こちらから当記事の協働ロボットのデメリット解説箇所に飛べます。
協働ロボットのメリットを解説

本章では、協働ロボットのメリットを網羅的に紹介します。そもそも協働ロボットのメリットは、以下の2種類にわかれます。
協働ロボット導入によって何が達成されるのかも大事ですし、同じくそれらを達成できる産業ロボットと比べて、協働ロボットにはどんな特長があるのかを知っておくことも大切です。
本章では、まず協働ロボットを導入することのメリットを紹介します。
協働ロボットを導入するメリットを解説
本節で解説する、協働ロボットを導入することで得られるメリットは以下の4つです。
労働力を確保し人手不足を解消できる
協働ロボットは、人間の労働時間や休日の制約を受けることなく、24時間稼働することができます。この特性は、特に製造業や物流業など、慢性的な人手不足に悩む業界にとってメリットとなるでしょう。
日本は少子高齢化により、今後も労働人口の減少は避けられませんが、協働ロボットの活用により生産ラインを安定的に運営し、労働力の不足を補完することが可能です。
品質安定と生産性向上にも寄与する
人間が作業を行う場合、ヒューマンエラーは避けて通れない問題です。また、人間の作業は、個々人の能力差や体調、やる気など、不確実性の高い多くの要因に左右されます。
一方、協働ロボットは、プログラムされた作業を繰り返し行うため作業にブレがなく、製品の品質を一定に保てます。
また、同じ作業を繰り返し続ける工程では、プログラム通りに高精度で作業を行い続けられる協働ロボットの方が、人間に比べて生産性が高まるでしょう。
以上より、協働ロボットの導入は、品質向上や生産性向上等にも寄与するというメリットがあります。
労働環境の改善にもつながる
重い物を運ぶ作業や、高温・多湿な環境での作業、反復的な作業など、肉体的・精神的な負担が大きい業務を代替することができるのも、協働ロボット導入のメリットです。
これにより、従業員の過度な負担を軽減し、労働環境を改善することができます。また、このような改善は、従業員の満足度やモチベーションを高め、離職率の低下にも貢献するでしょう。
いろいろなコストを削減できる
協働ロボットの導入には初期投資が必要ですが、長期的に見れば、さまざまなコスト削減が期待できます。
まず、協働ロボットは24時間稼働可能なため、残業代や追加人件費を削減できます。さらに、人間の教育や研修にかかる費用も不要になるため、人材採用・教育コストも削減可能です。
また、協働ロボットは作業の標準化を促進し、不良品の減少や材料のロスを防ぐことで、製造にかかる無駄なコスト削減にも寄与します。
以上より協働ロボットによるコスト削減は、特に、コスト意識を高く持つ必要がある中小企業にとって、魅力的なメリットでしょう。
産業ロボットと比較した際のメリットは?
本節で解説する、産業ロボットと比較した際の協働ロボットのメリットは以下の3つです。
安全柵不要で導入でき、省スペース化を実現する
産業ロボットは、一般的に高速で高出力のため、人間との接触を防ぐために安全柵を設置する必要がありました。
しかし、協働ロボットは、人と共に作業を行うことを前提に設計されており、力覚センサーや速度制限機能などの安全機能を備えています。そのため、安全柵を必要とせず、設置が可能です。
この特徴により、作業エリアのレイアウトを柔軟に変更することができ、工場のスペースを効率的に活用できるメリットがあります。
また、安全柵が不要になることで、設置やメンテナンスにかかるコストや手間を削減できる点も協働ロボットのメリットです。
専門教育不要で導入のハードルが低い
従来の産業ロボットは、プログラミングや操作に専門的な知識を必要とし、そのため導入には高いスキルが求められました。
しかし、協働ロボットは、直感的なインターフェースや簡単に操作できるティーチングペンダントを搭載しているため、専門的な教育を受けていないスタッフでも操作が可能です。
これにより、特別なエンジニアリングチームを組まなくても、現場スタッフが直接設定や調整を行うことができ、導入のハードルを低くできます。この柔軟さは特に中小企業にとってメリットとなり、技術的な負担を軽減するでしょう。
作業内容を柔軟に変更可能できる
作業内容のカスタマイズが可能な点も、産業ロボットと比較した際の、協働ロボットのメリットと言えます。
従来の産業ロボットは、特定の作業に特化して設計されていることが多く、作業内容を変更するためには、プログラミングや機器の再設定が必要でした。そのため、ラインの変更や新しい作業への対応に時間がかかることが多いです。
一方、協働ロボットは、プログラムを簡単に変更したり、ツールを交換することで異なる作業に対応できます。また、軽量で移動が簡単なため、作業場所やレイアウトを変更する場合にも柔軟に対応できます。
この柔軟性により、多品種少量生産やライン変更が頻繁な現場でもメリットを発揮します。
以上が協働ロボットのメリットです。導入前にはメリットだけではなく、デメリットや課題も知っておきたいですよね。
次章では、協働ロボットのデメリットや課題を解説します。導入後に「こんなデメリットもあるなんて」と後悔しないようにぜひご覧ください。
協働ロボットのデメリット・課題を解説

メリットの章でも解説しましたが、協働ロボットのデメリット・課題も2種類にわかれます。
まず、協働ロボットを導入する際に、そのデメリットや課題を知っておく必要があります。
また、自社で達成したいこと(自動化や品質向上など)を産業ロボットではなく、協働ロボットで解決する際に、どんな課題があるのかも知っておくと良いです。
本章では、協働ロボットを導入する際のデメリットから解説します。
導入前に確認したい協働ロボットのデメリット・課題
本節で解説する、協働ロボットのデメリット・課題は以下の6つです。
人材育成は必要になる
まず解説する協働ロボットのデメリット・課題は、人材育成が必要なことです。
協働ロボットは比較的簡単に操作できますが、その能力を最大限に引き出すためには、適切な人材育成が必要です。操作方法だけでなく、プログラミングやメンテナンス、トラブルシューティングなどの基本的な知識が求められます。
特に、安全性を確保するための教育は重要であり、労働安全衛生法に基づく教育を受ける必要がある場合もあります。
現場の反発がでる可能性
新しい技術を導入する際、現場の従業員から反発が起こることがあります。特に協働ロボットの導入により自分たちの仕事が奪われるのではないかと不安を感じる場合が多いでしょう。
また、ロボットとの協働に不安を抱く従業員もいるという課題もあり、適切なコミュニケーションと説明が必要です。具体的には、現場の従業員に新技術の意義や利点を理解してもらうことが重要と言えます。
システムトラブルは避けられない
協働ロボットも機械であるため、予期しないシステムトラブルが発生する可能性はゼロではないこともデメリットの一つです。
動作停止や誤作動、ソフトウェアのエラーなどが生じる場合があり、これが生産ラインに影響を及ぼすこともあります。したがって、トラブルが発生した場合の迅速な対応方法を事前に策定しておくと良いでしょう。
ここまでで解説した、人材育成や現場からの反発、システムトラブルに懸念がある方は、以下よりこれらの解決策を紹介している箇所に飛べます。他のデメリットより先に解決策を知りたい方は、ぜひご覧ください。
作業環境の変更を余儀なくされる
協働ロボットを導入するには、作業環境の整備が必要です。特に、既存の設備の配置や作業スペースを見直す必要が出てくるという課題があります。
また、協働ロボットを効率的に稼働させるためには周辺機器の追加や作業動線の変更も考慮する必要があるでしょう。環境設計を再構築することが求められるため、事前の準備が重要です。
協働ロボットでも安全面の確保は必須
協働ロボットは人と共に作業を行うことを前提に設計されていますが、事故のリスクを完全に排除することはできません。ロボットが適切に運用されなければ、予期せぬトラブルが発生するという課題があります。
したがって、導入前にはリスクアセスメントを実施し、潜在的な危険源を特定したうえで、適切な安全対策を講じることが求められます。
以下のボタンより、当記事内にある、作業環境の変更や安全面の確保に対する解決策を紹介した箇所をご覧いただけます。ご興味ある方はぜひクリックしてみてください。
導入にそれなりのコストがかかってしまう
協働ロボットの導入には、本体の購入費用に加え、周辺機器、ソフトウェア、設置費用、人材育成費用など、さまざまなコストがかかります。
特に中小企業にとっては、初期投資が大きな負担になることはデメリットになりうるでしょう。そのため、導入にかかる全体的なコストを事前に把握し、予算計画を立てることが大切です。
コストがネックで協働ロボットの導入ができない方向けに、以下のボタンから飛べる箇所では、協働ロボットの導入コストを下げる方法を提示しています。ぜひご一読ください。
産業ロボットと比較した際のデメリット・課題は?
本節で解説する、産業ロボットと比較した際のデメリット・課題は以下の3つです。
完全な自動化は達成できない
協働ロボットは、あくまで人間と協力して作業を行うことを前提に設計されています。そのため、完全な無人化や全自動化を目指す用途には不向きというデメリットがあります。
協働ロボットは生産ラインの効率を向上させ、人とロボットの役割を分担する形で最適に機能しますが、すべての作業を自動で完結させるためには、他の技術や装置との組み合わせが必要です。
完全な自動化が求められる場面では、産業ロボットといった他のソリューションがより適しています。
産業ロボットと比べて動作速度が遅い
協働ロボットは、作業員と直接協働するため、安全性を確保する必要があります。このため、協働ロボットの動作速度は制限されており、産業ロボットに比べて遅くなることも課題の一つです。
特に高速な動作が求められる用途では、協働ロボットの速度では十分に対応できないこともあるでしょう。
協働ロボットの中には、安全モードを解除し、作業者が近くにいない場合に速度を向上させる機能を備えた機種もありますが、完全な高速動作を実現するのであれば、産業ロボットの方が良いです。
産業ロボットを使わず、協働ロボットで動作速度を改善していく方法もあります。以下のボタンから飛べる個所では、その方法を解説しているので、ご興味ある方はぜひご覧ください。
産業ロボットと比較して可搬重量も小さい
続いて解説する、産業ロボットと比較した際の協働ロボットのデメリットは、可搬重量の小ささです。協働ロボットの可搬重量は一般的に4〜16kg程度です。
そのため、協働ロボットは軽量で取り扱いやすい部品をピックアップして、組み立て作業や検査業務を効率化するのには適していますが、重い部品を扱うような作業には向いていません。
重量物を取り扱う作業が求められるラインでは、産業ロボットの方がより適した選択となります。
以下のボタンから飛べる個所では、協働ロボットを使って重量物を扱う方法を紹介しています。可搬重量が懸念として残っている場合はぜひご覧ください。
以上が協働ロボットのデメリット・課題です。上記のようなデメリットや課題が導入のハードルになっている場合は、それらの解決策を知っておく必要があります。
次章では、上記のデメリットや課題に対する解決策を紹介します。こちらを読んで不安感なく協働ロボットの導入に進みましょう。
デメリット・課題に対する解決策を紹介
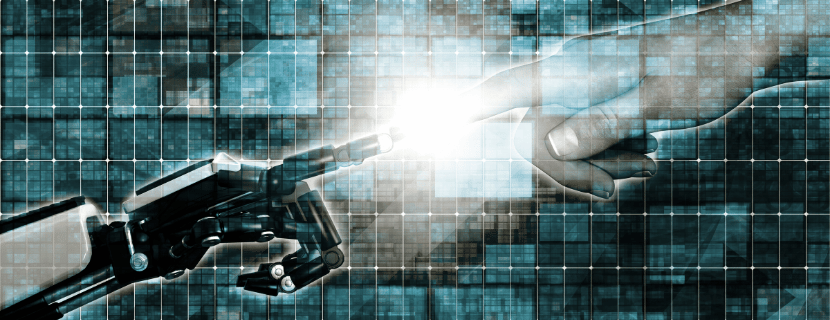
先述したように、協働ロボットの導入にはいくつかのデメリットや課題が存在しますが、それぞれに対する解決策を講じることで、導入後の効果を最大化することができます。
本節では、主要なデメリット・課題に対する実践的な解決策を紹介します。
人材育成や現場の反発、システムトラブルに対する解決策
協働ロボットの導入において、まず重要なのは人材育成です。ロボットメーカーやシステムインテグレーターが提供するトレーニングプログラムを活用することが有効でしょう。
また、政府や自治体の支援制度を活用することで、教育コストの軽減が可能です。
次に現場の反発に対しては、協働ロボットの導入目的やメリットを従業員に丁寧に説明することが大切です。透明性を持ちながら、彼らの意見を尊重して導入を進めましょう。
最後に、システムトラブルに対しては、定期的なメンテナンスを実施し、トラブルが発生した際の対応マニュアルを整備することが重要です。さらに、メーカーやインテグレーターと連携し、迅速なトラブルシューティング体制を構築しておくことが求められます。
作業環境の変更や安全面の確保に対する解決策
協働ロボットの導入においては、作業環境の変更が避けられない場合があります。そのため、事前に徹底的なレイアウト設計を行い、シミュレーションツールを活用して最適な配置を導き出すことが有効です。
また、安全面の確保には、導入前にリスクアセスメントを実施し、潜在的な危険の特定が必要です。その後、得られたデータをもとに適切な安全対策を講じます。
例えば、協働ロボットの動作速度制限、安全センサーの設置、必要に応じて保護柵の設置を行い、作業員の安全を確保しましょう。
導入コストがかかることへの解決策
協働ロボットの導入に伴うコストの削減方法としては、リースやレンタルを活用する方法があります。これにより、初期投資を抑えつつ、必要な機能を得ることができます。
また、政府や自治体の補助金制度を活用することで、さらなるコスト削減が可能です。
加えて、機能を絞り込んだ機種選定や、既存設備との連携を考慮することで、初期投資を抑えることもできます。こうした方法を検討することで、負担を軽減しながら協働ロボットの導入が実現できるでしょう。
実は、こちらで紹介したもの以外にも、協働ロボットを低価格で導入する方法は存在します。以下の記事では、協働ロボットを低価格で導入する8つの方法を徹底解説しています。
コストを抑える方法をより詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
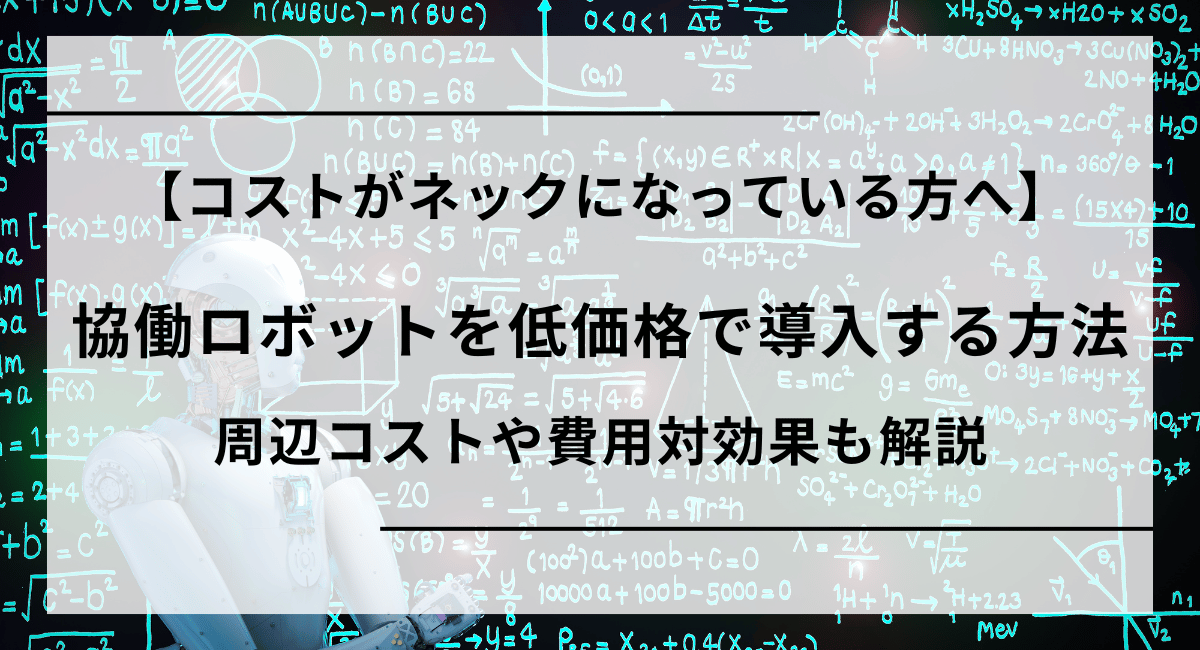
動作速度が遅いことへの解決策
協働ロボットの動作速度の遅さに対する解決策は、安全性を確保しながらも可能な範囲で速度を調整する方法があります。
また、複数の協働ロボットを連携させることで作業効率を向上させるやり方も有効でしょう。これにより、速度の制限を補い、全体の作業フローを最適化できます。
可搬重量が小さいことへの解決策
可搬重量が小さいという課題に対しては、より高可搬重量の協働ロボットの選定選定が一つの解決策です。
加えて、アシスト機能を持つ周辺機器(電動バランサーなど)と組み合わせることで、負荷を軽減し、協働ロボットの可搬重量を広げることもできます。
さらに、製品の設計段階で部品の軽量化を図ることも一つの解決策です。軽量化することで、協働ロボットがより多くの作業に対応できるようになり、可搬重量の制約を克服できます。
ここまで、協働ロボット導入におけるデメリットと、その対策について解説しました。
しかし、本来の業務と並行してこれら全てを自社で実行するには、専門的な知見と多くの工数を要するのが実情です。
そこで弊社では、協働ロボットの導入プロセスを一貫してご支援するサービスをご提供しております。経験豊富な専門家が、ロボットの選定から導入後の運用サポートまで、お客様のプロジェクトに責任をもって伴走いたします。
「まずは何から相談すればいいか分からない」という段階でも、専門家が丁寧にヒアリングいたします。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽に以下のサービス詳細をご覧ください。
まとめ|メリット・デメリットを整理したうえで協働ロボットの選定に入ろう
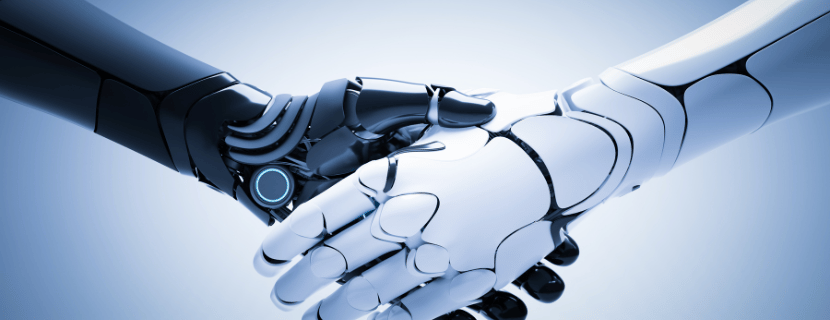
本記事では、協働ロボットのメリット・デメリットの解説に加えて、デメリットに対する解決策も紹介しました。
協働ロボットは、労働力不足や生産性向上を実現する強力な選択肢ですが、その導入には注意すべき点も多いことがわかりました。
メリットとしては、人手不足の解消、品質安定や生産性向上、労働環境の改善、コスト削減などが挙げられます。しかし、デメリット・課題としては、導入コストの高さやシステムトラブル、作業環境の変更、さらには現場の反発などが懸念材料となります。
ただ、これらの課題には解決策が存在し、適切な準備を行うことで、協働ロボットを効果的に活用できるはずです。特に、中小企業にとっては、その導入が競争力を高める鍵となる場合もあります。
以上より、協働ロボットの導入を検討する際は、メリットだけでなく、課題やデメリットに対する対策も十分に理解し、慎重に計画を立てていくことが重要です。
また、以下の記事では、おすすめ協働ロボットメーカーを比較して紹介しています。中国メーカーや世界シェアランキング上位のメーカーにも触れていますので、ぜひご覧ください。
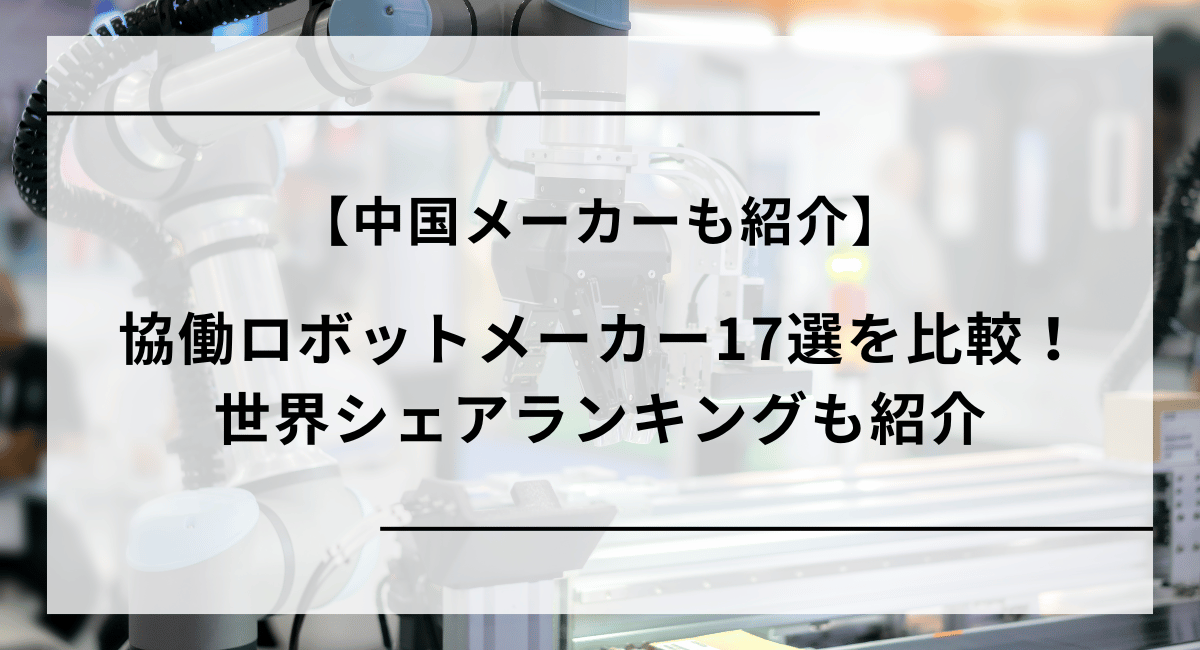
自社にぴったりの協働ロボットを探してみませんか?
実際の製品スペックや詳細な機能は、こちらからチェックしてみてください。