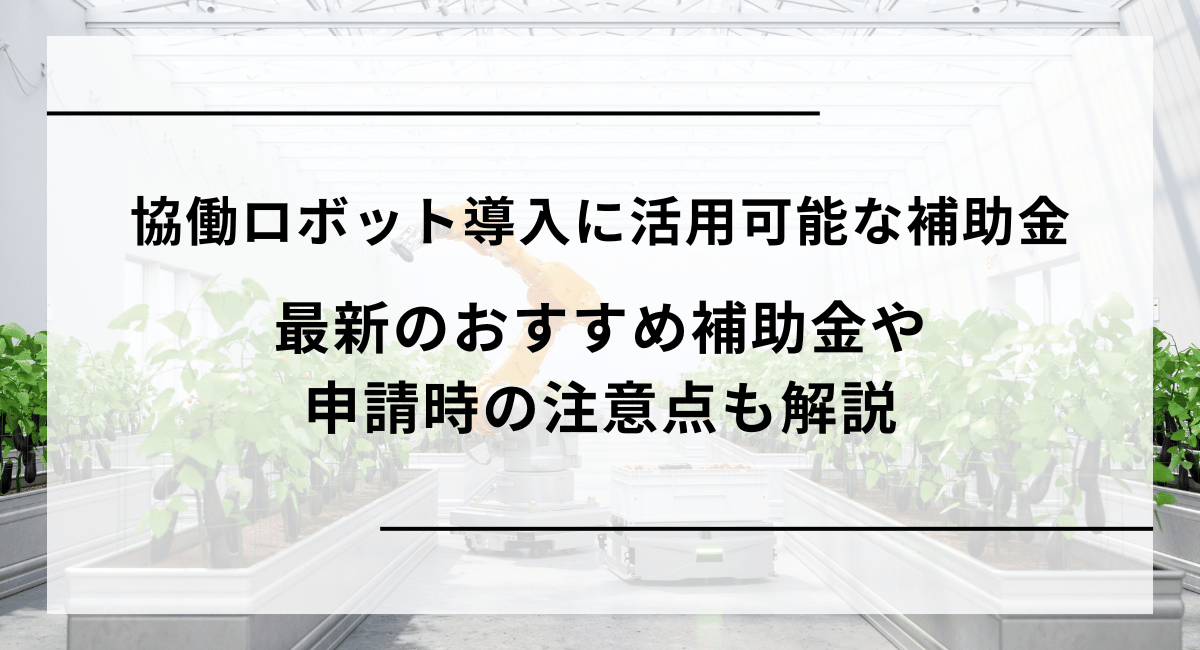
中小企業が協働ロボット導入時に活用できる、おすすめの補助金を解説!
「協働ロボットを導入したいと考えているが、コストが高そう。」や「協働ロボットの導入にどんな補助金が使えるのか気になる。」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、こうした悩みを解決するために、補助金の申請方法や条件、注意点などの基本情報をお伝えするとともに、当編集部が特におすすめする、省力化投資補助金も解説します。
補助金の基本的な情報を既に知っている方は、以下から、当編集部がおすすめする省力化補助金の解説をご確認ください。
協働ロボット導入を検討している方にとって、導入コストを抑えられる可能性がありますので、ぜひご一読ください。
また、JET-Roboticsでは実際に、協働ロボットの導入支援も行っております。
協働ロボットの専門家による製品の選定から補助金の活用、ロボット研修による社内人材の育成まで、協働ロボット導入をあらゆる面からサポートいたします。
「一度ロボットを触ってみたい」や「こんな自動化ができるか知りたい」などの軽い相談も可能です。
相談は無料ですので、関心のある方は以下のサービス詳細をご覧ください。
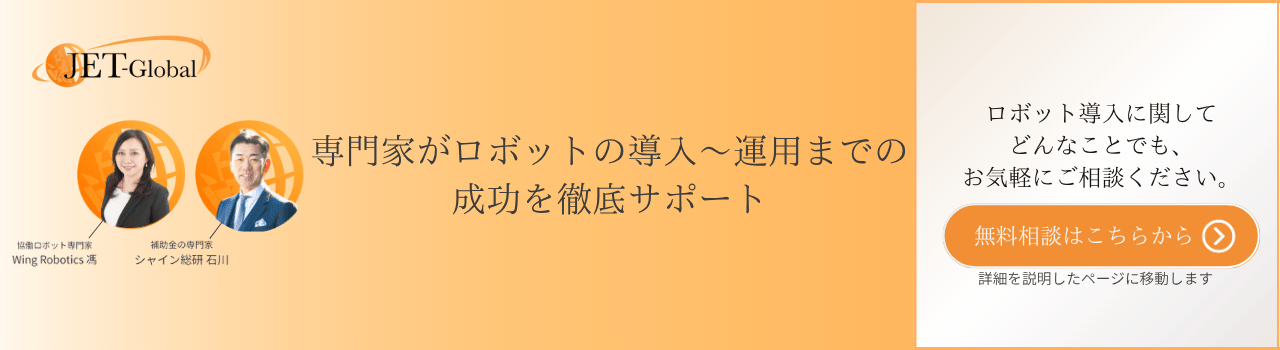
協働ロボットの導入に補助金は使えるの?
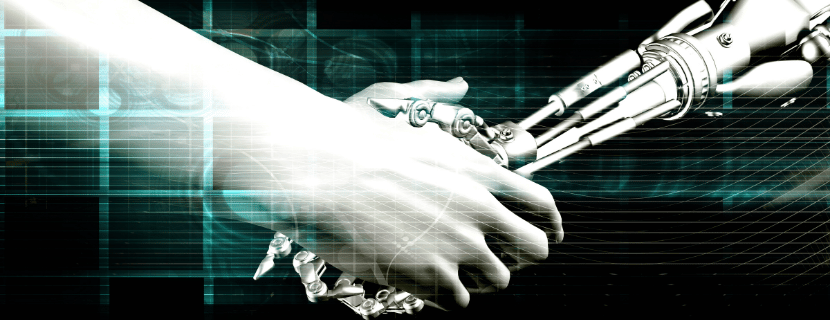
【結論】協働ロボットの導入に補助金は活用可能
結論から申し上げますと、協働ロボットの導入には補助金の活用が可能です。特に中小企業を対象とした補助金が存在し、初期投資を抑えつつ協働ロボットを導入する助けになります。これらの補助金により、省力化や効率化を図れる協働ロボットの導入が促進されます。
また、協働ロボットとはそもそもどのようなものなのか知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事
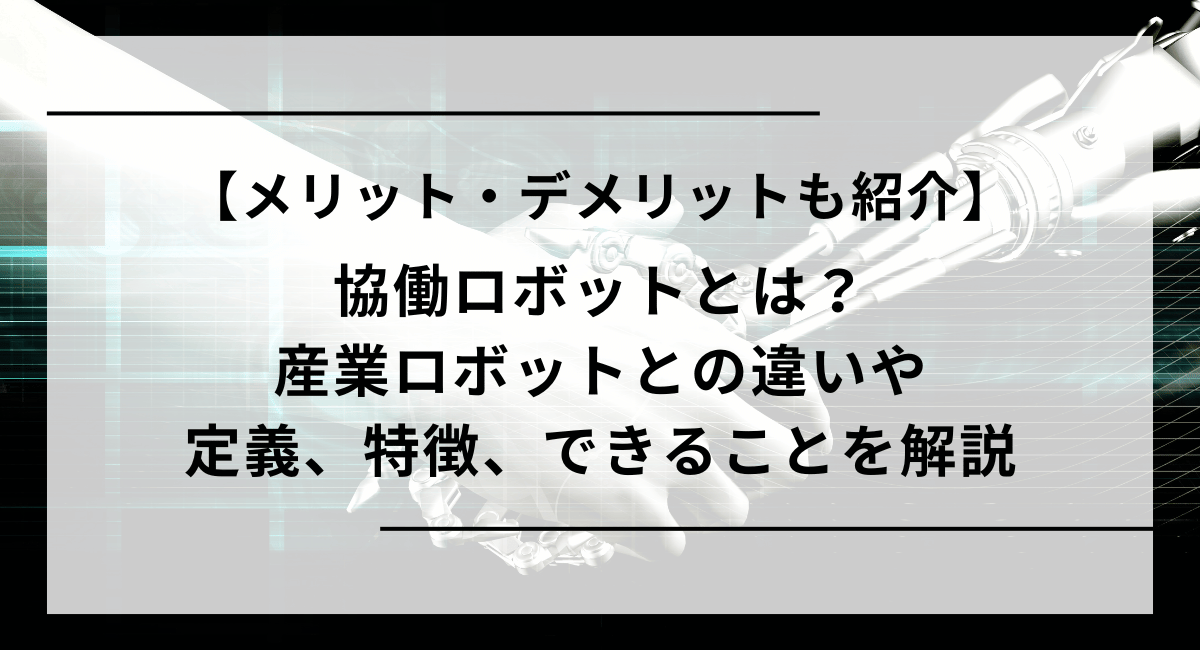
協働ロボットとは?産業ロボットとの違いや定義、特徴、できることを解説
協働ロボットの導入に活用できるおすすめの補助金の概要を紹介
協働ロボットを導入する際に活用できる補助金は以下の5つです。※補助金名をクリックすると、申し込み条件や給付金額、公募期間などを説明した箇所に画面が移動します。
省力化投資補助金(当編集部おすすめ)
IoTや協働ロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術等の導入全般に活用可能です。補助額も最大1億円と、協働ロボットの導入に活用できる補助金の中では高額な部類に入ります。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業が新技術や設備を導入する際に支援する制度です。また、協働ロボットは、工場の効率や製品の品質を向上させるだけでなく、新しい自動化の方法を実現したり、新しい製造方法や製品の開発を促進するため、この補助金の対象となります。
IT導入補助金
IT導入補助金は中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する際に活用できる補助金です。協働ロボット本体は対象外ですが、制御ソフトなどが IT ツールとして登録されている場合、そのソフトウェア部分に限り補助対象となります。
事業再構築補助金
中小企業等が事業再構築を行う際に活用できる補助金で、 協働ロボット導入による新事業展開なども対象となります。地域振興補助金・地方自治体独自の支援金
地域振興補助金は、地域の活性化や課題解決を目的とした補助金です。また、地方自治体によっては、協働ロボット導入を支援する独自の補助金制度を設けている場合があります。
この章では協働ロボットの導入に活用できる5つの補助金を紹介しました。
中でも、省力化投資補助金は、補助金額が高額な部類であるのに加え、柔軟な申請タイプがあるので、多様なニーズに対応できる点でおすすめです。
次の章では、おすすめの省力化投資補助金を詳しく解説します。
協働ロボットの導入におすすめの省力化投資補助金を解説
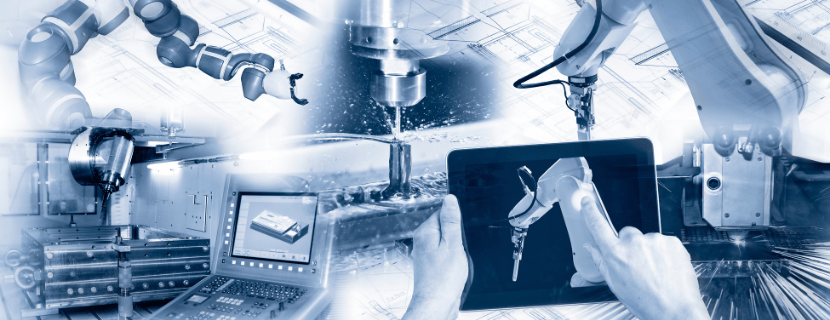
この章では、当編集部がおすすめする省力化投資補助金の基本情報を説明します。協働ロボットの導入に、どの補助金を活用するか考えている方は是非ご参考ください。
省力化投資補助金の目的と特長を解説
目的は?
省力化投資補助金は、中小企業が労働力不足の解消や生産性向上を図るために、ロボット技術や自動化設備の導入を支援するために設立されました。特長を解説
このパートでは省力化投資補助金の特長を3つ解説します。省力化投資補助金は、「一般型」と「カタログ注文型」という二つの異なるタイプを用意し、多様なニーズに対応しています。
「一般型」と「カタログ注文型」について詳しく知りたい方はカタログ注文型と一般型を解説から、両者の特長をご覧ください。
省力化補助金には一般型とカタログ注文型という2つの申請方法があります。カタログ注文型の場合、申請から交付決定まで最短1カ月で、採択後の導入スピードが早いので、事業を迅速に進めることができます。
他の補助金では、採択後に相見積もりや図面などの提出が必要となる場合があり、導入までに時間がかかることがあります。
しかし、省力化投資補助金のカタログ注文型なら、そのような手間をかける必要がなく、協働ロボットなどの製品を登録した販売事業者との連携、そしてオンラインでの申請のみで導入まで進めることが可能です。
省力化投資補助金は、既存事業の効率化や生産性向上、ひいては賃上げにつなげることを目的としています。
他にも既存事業に対しての補助金はありますが、省力化投資補助金は他の補助金と比較して、より既存の事業運営における効率化に特化しています。(表1)
(表1)
| 補助金名 | 目的 | ||||||
| 省力化投資補助金 | 中小企業等の人手不足解消のため、IoT・協働ロボット等の省力化製品導入を支援し、既存事業の効率化・生産性向上を図り、賃上げにつなげる。 | ||||||
| ものづくり補助金 | 中小企業等が革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援し、生産性向上を図る。 | ||||||
| IT導入補助金 | 中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的として、ITツール導入を支援し、業務効率化やDXを推進する。 | ||||||
| 事業再構築補助金 | ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築(新分野展開、業態転換など)を支援する。 | ||||||
| 地域振興補助金・地方自治体独自の支援金 | 地域経済の活性化や地域課題の解決を目的として、地方自治体等が独自に提供する支援金。目的や対象は地域により異なる。 | ||||||
このパートでは省力化投資補助金の目的や特長を解説しました。
上記に記載がある目的と特長から、協働ロボットを導入する際に、省力化投資補助金は十分効果的といえるでしょう。
次のパートでは、省力化投資補助金の2つのタイプ、一般型とカタログ注文型を解説します。
カタログ注文型と一般型を解説
省力化投資補助金には、カタログ注文型と一般型の2つのタイプがあります。まずは、2つのタイプの概要を解説します。カタログ注文型の基本情報を解説
カタログ注文型は、中小企業等の人手不足解消を目的とし、カタログに掲載された協働ロボット等の製品の導入を支援する補助金です。そして、省力化投資補助金(カタログ注文型)の最大の特徴は、中小企業庁が事前に選定した省力化設備やサービスが掲載されたカタログから製品を選ぶという点です。
この方式により、他の補助金と比較して申請手続きが容易になるという利点があるのに加えて、導入する協働ロボットなどの製品を販売・提供している、販売事業者と共同で申請を行うことができます。
なので、初めて補助金の申請をする企業や不安な点がある企業も、他の補助金と比較して安心して申請手続きを行いやすいでしょう。
一般型の基本情報を解説
一般型は、人手不足の中小企業等がオーダーメイドの省力化設備・システム導入で生産性向上を目指す事業を支援する補助金で、協働ロボット導入の際に活用することも可能です。また、一般型はカタログ注文型にない製品も導入できる、オーダーメイド制の導入形式なので、より多様なニーズに応えた協働ロボットや投資の導入を期待できます。
さらに一般型の補助上限額はカタログ注文型に比べて高いことも特長です。(表2)
次に、以下の表1で、両者の特徴を比較します。
(表1)
| 省力化投資補助金(一般型) | 省力化投資補助金(カタログ注文型) | ||||||||||||
| 導入形式 | オーダーメイドまたはセミオーダーメイド | カタログ掲載製品 | |||||||||||
| 対象設備の幅広さ | 幅広い | 限定的 | |||||||||||
| 申請の手間 | 詳細な事業計画書(10〜15ページ程度)が必要 | 販売事業者のサポート付きで比較的容易 | |||||||||||
| 交付決定までの期間 |
採択まで約3か月 (交付決定は採択後、交付申請・審査を経て数週間) |
最短1か月 | |||||||||||
| 対象事業者 | 中小企業等 | 中小企業等(小規模・個人事業者含む) | |||||||||||
| 補助率 |
中小企業 1/2(賃上げ特例 2/3)、1,500万円超部分は1/3 小規模企業者・再生事業者 2/3、1,500万円超部分は1/3 |
1/2 | |||||||||||
| 補助上限額 | 最大1億円 | 最大1,500万円 | |||||||||||
※()内は大幅な賃上げを行う場合の補助率 ※()内は大幅な賃上げを行う場合の補助率
また、カタログ注文型と一般型の補助上限額の比較は以下の表をご参照ください。
(表2)
| 従業員数 | カタログ注文型 標準補助上限額 |
カタログ注文型 大幅賃上げ時補助上限額※ |
一般型標準 補助上限額 |
一般型大幅賃上げ時 補助上限額※ |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5名以下 | 200万 | 300万 | 750万 | 1000万 | |||||||||||||||||||||
| 6~20名 | 500万 | 750万 | 1500万 | 2000万 | |||||||||||||||||||||
| 21~50名 | 1000万 | 1500万 | 3000万 | 4000万 | |||||||||||||||||||||
| 51~100名 | 5000万円 | 6500万円 | |||||||||||||||||||||||
| 101名以上 | 8000万 | 1億 | |||||||||||||||||||||||
このパートでは、省力化投資補助金の一般型とカタログ注文型の基本情報を説明し、比較しました。
協働ロボットの導入の際に活用できる補助金の一つとして、ご自身のニーズに合ったタイプはどちらなのか明確にした上でご参考にしてください。
次のパートでは、省力化投資補助金を受け取る際の条件を解説します。
省力化投資補助金の条件
一般型とカタログ注文型のそれぞれに労働生産性や賃上げ目標、対象設備などの条件があります。以下から一般型とカタログ注文型の条件をまとめたものをご確認ください。
一般型の条件
- 労働生産性年平均4.0%以上向上※1
- 給与支給総額年平均2.0%以上増加
- 事業場内最低賃金+30円以上
カタログ注文型の条件
- 労働生産性年平均3.0%以上向上※1
- 人手不足の状態であること※2
- カタログ掲載している協働ロボットの導入
【省力化補助金における労働生産性の定義】
労働生産性とは、労働者一人あたり、または労働時間あたりの産出量を指し、労働の効率性を示す指標として用いられます。
【労働生産性年平均率】
労働生産性を元に、一年間あたりの割合を算出することができます。
しかし、労働生産性年平均は複雑な計算が必要になるので、詳しい計算は専門家に相談するのがおすすめです。
しかし、労働生産性年平均は複雑な計算が必要になるので、詳しい計算は専門家に相談するのがおすすめです。
【人手不足の定義】
具体的に説明すると、以下の4つのいずれかの状況にあることを指します。
1. 直近の従業員の平均残業時間が月30時間を超えていること。
2. 整理解雇によらない離職・退職によって、前年度と比較して従業員数が5%以上減少していること。
3. 過去1年以内に求人媒体やハローワークを通じて採用活動を行ったにもかかわらず、必要な人材を確保できていないこと。
4. 上記のいずれにも該当しない場合でも、省力化を推し進める必要に迫られていると認められる場合があります。
※この場合は、より詳細な説明や省力化計画(省力化量計算書、機器配置予定図など)の提出が求められることがあります。
1. 直近の従業員の平均残業時間が月30時間を超えていること。
2. 整理解雇によらない離職・退職によって、前年度と比較して従業員数が5%以上減少していること。
3. 過去1年以内に求人媒体やハローワークを通じて採用活動を行ったにもかかわらず、必要な人材を確保できていないこと。
4. 上記のいずれにも該当しない場合でも、省力化を推し進める必要に迫られていると認められる場合があります。
※この場合は、より詳細な説明や省力化計画(省力化量計算書、機器配置予定図など)の提出が求められることがあります。
条件のうちの一つである労働生産性年平均率など、算出のプロセスが複雑なものがあります。詳しい計算方法は専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
次のパートでは交付期間と公募期間を解説します。
交付期間、公募期間を解説
申請から交付されるまでどのくらい時間がかかる?
ここでは、交付期間の確認のために、申請から補助金交付までにかかる期間も解説します。初めに一般型の交付期間の目安を解説します。
【一般型の交付までにかかる期間】
結論からいうと、一般型補助金の交付までにかかる期間は数ヶ月から最大2年程度です。以下でその内訳を説明します。まず、申請から採択までは約3ヶ月程度かかる見込みです。
そして採択発表後、交付決定まで1~2ヶ月程度、事業実施期間が最大18ヶ月、実績報告・確定検査後に補助金が支払われるため、採択から補助金交付までには数ヶ月から最大2年程度かかる可能性があります。
【カタログ注文型の交付までにかかる時間】
カタログ注文型補助金の交付までにかかる期間は2ヶ月から1年半程度です。以下でその内訳を説明します。まず、申請から採択・交付決定まで1~2ヶ月程度、事業実施期間が最大12ヶ月、実績報告後に補助金が支払われるため、申請から補助金交付までには2ヶ月から1年半程度かかる可能性があります。
このパートでは、一般型とカタログ注文型の申請から補助金の交付までどのくらいの時間が必要なのかを解説しました。
次に、申請の公募期間を解説します。
公募期間を確認
【一般型の公募期間】
一般型の公募は、特定の期間を定めて実施される回制となっています。以下の表から公募期間をご確認ください。| 公募回 | 公募開始日 | 申請受付開始日 | 公募締切日 | 採択発表日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2025年 1月30日 |
2025年3月19日 | 2025年3月31日 17:00 | 2025年6月16日 | |||||||||||||
| 第2回 | 2025年 4月15日 |
2025年4月25日 | 2025年5月30日 17:00 | 2025年8月中旬 (予定) |
|||||||||||||
| 第3回 | 2025年 6月27日 |
2025年8月4日 10:00 | 2025年8月29日 17:00 | 2025年11月下旬 (予定) |
|||||||||||||
公募回の追加・日程変更は事務局サイトで随時更新されるため、応募前に必ず最新の公募要領・スケジュールページをご確認ください。
なお、スケジュールの更新は中小企業省力化投資補助金から確認できます。
また、申請方法を確認したい方は一般型の申請方法から申請方法をご確認ください。
次にカタログ注文型の公募期間を確認します。
【カタログ注文型の公募期間】
カタログ注文型の公募は2024年8月9日から通年で随時受付されています。
上記のように、一般型は特定の公募期間がありますが、カタログ注文型はメンテナンス期間を除き、事業者が都合の良いタイミングで申請が可能です。
このパートでは、申請から交付までの期間と公募期間を解説しました。次のパートでは、省力化補助金を使う際の注意点を解説します。
省力化補助金の注意点
ここでは、省力化投資補助金を活用する際の注意点を一般型とカタログ注文型でそれぞれ解説します。補助金の活用をご検討されている方はご参考ください。まずは2つに共通した注意点を確認します。
- 申請時に全ての従業員の賃金が最低賃金を上回っている必要がある。
- 同一の事業に対して、他の補助金制度との重複受給は認められない。
- 申請は電子申請システムを通じて行われ、gBizIDプライムアカウントが必要。
- 補助金は原則として事業完了後の精算払いとなるため、初期投資に必要な資金を事前に準備する必要がある。
- 補助金の交付を受けた場合、事業完了後も一定期間、協働ロボットの稼働状況などを報告する義務がある。
次に一般型の注意点を確認します。
- 単価50万円(税抜)以上の機械装置等の設備投資が必須であり、「機械装置・システム構築費」以外の経費には上限がある。
- 申請は電子申請のみで受け付けられ、事前に gBizIDプライムアカウントの取得が必要。
- 交付決定前に契約や発注を行った経費は、原則として補助対象外となる。
- 補助金で購入した設備を一定期間内に処分する場合、事前の承認と補助金の返還が必要となることがある。
最後にカタログ注文型の注意点を確認します。
- 補助対象となるのは、中小企業庁が事前に選定したカタログに掲載されている協働ロボット等の製品のみです。
- 申請は、補助を受けたい事業者と協働ロボット等の製品を販売する事業者が共同で行うことが必要です。
- 補助率や補助上限額は従業員数によって異なり、大幅な賃上げを行う場合は上限額が引き上げられる特例があります。
- 申請事業者は、直近の残業時間、従業員数の減少、求人活動の状況などにより、人手不足であることを示すことが必要です。
- 交付決定前に協働ロボットを購入した場合、補助対象外となります。
このパートでは、協働ロボット導入のために省力化投資補助金を活用する際の注意点を解説しました。
2つに共通した注意点と、活用する補助金のタイプごとの注意点を確認した上で、自身のニーズに適したタイプを活用することをおすすめします。
次のパートでは申請方法を解説します。
補助金の申請方法
省力化投資補助金は電子申請システムを通じて申請することができます。まず、一般型の申請手順から解説します。一般型の申請方法
step1
事前準備
事業計画書の作成が必要です。導入する設備の詳細や業務効率化の効果を明確に記載します。
事業計画書の作成が必要です。導入する設備の詳細や業務効率化の効果を明確に記載します。
step2
必要書類の準備
見積書、発注書、直近の決算書・財務諸表などを準備します。
見積書、発注書、直近の決算書・財務諸表などを準備します。
step3
電子申請
gBizIDプライムアカウントを取得し、電子申請システムを通じて申請を行います。
gBizIDプライムアカウントを取得し、電子申請システムを通じて申請を行います。
次にカタログ注文型の申請手順を解説します。
カタログ注文型の申請方法
step1
事前準備
カタログに掲載されている協働ロボットを選定します。
カタログに掲載されている協働ロボットを選定します。
step2
販売事業者との共同申請
販売事業者と共同で申請を行います。
販売事業者と共同で申請を行います。
step3
電子申請
gBizIDプライムアカウントを使用し、専用フォームから申請します。
gBizIDプライムアカウントを使用し、専用フォームから申請します。
一般型は事業者が主体となって申請するのに対し、カタログ注文型は販売事業者との共同申請が必須となる点や、導入する設備に対してのアプローチが異なる点が特徴です。
ここまで、一般型とカタログ型の申請方法を解説しましたが「補助金を活用したいが、手続きが複雑で時間がない」「事業計画書の作成が難しく、採択されるか不安だ」
このようなお悩みはございませんか?
JET-Roboticsでは、補助金申請の専門家がお客様に代わり、事業計画の策定から申請書類の作成、採択後の手続きまで一貫してサポートいたします。
採択のポイントを熟知した専門家が伴走するため、お客様は本来の事業に集中しながら、採択率の向上を目指すことが可能です。
「そもそも、どの補助金が使えるのか分からない」という段階でも歓迎です。ご相談は無料ですので、まずは下記のサービス詳細をご覧ください。
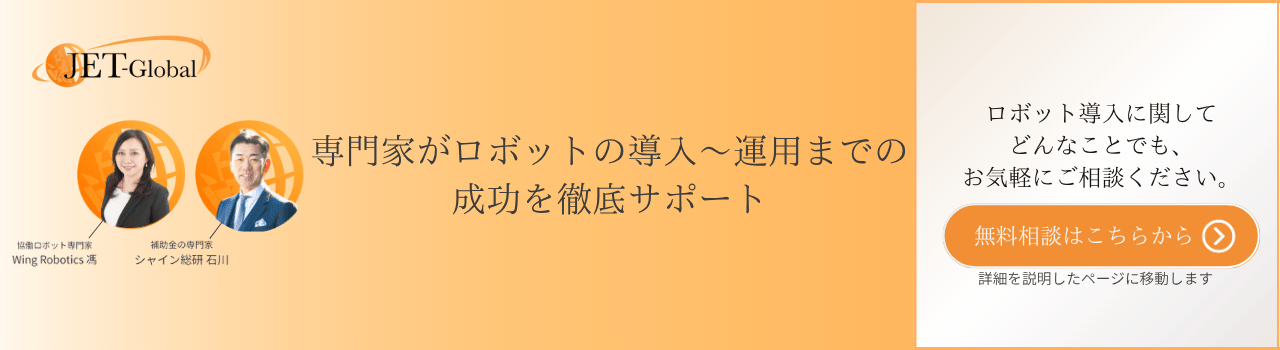 以上が当編集部がおすすめする省力化投資補助金の解説です。注意点や公募期間などを確認の上、協働ロボットを導入する際は是非ご活用ください。
以上が当編集部がおすすめする省力化投資補助金の解説です。注意点や公募期間などを確認の上、協働ロボットを導入する際は是非ご活用ください。その他の補助金の申し込み条件などを解説!助成金との違いは?
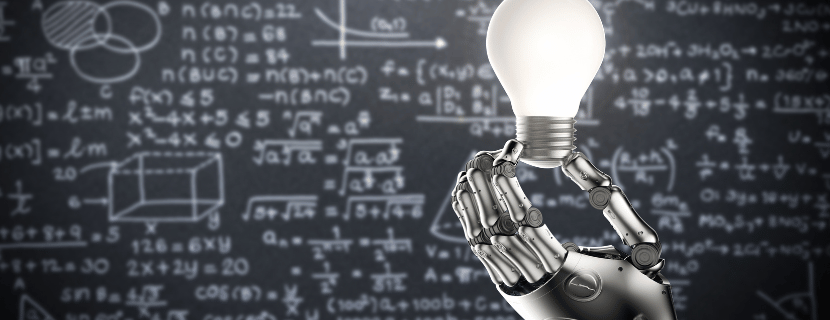
この章では、省力化投資補助金以外の補助金も解説します。申込条件や、給付金額等を確認して、生産性の向上やコストカットを目指しましょう。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、製造業の設備導入を支援するもので、協働ロボットの導入にも活用できます。申請条件には、企業の規模や事業内容が関連しており、補助金額や公募期間も定期的に変動しますので、注意が必要です。
申し込み条件や給付金額、公募期間を確認
- 申込条件: 中小企業・小規模事業者等。付加価値額、給与支給額、最低賃金の引上げ計画が必要
- 給付金額: 750万円~2,500万円(製品・サービス高付加価値化枠)/3,000万円(グローバル枠)
- 公募期間: 年間複数回。第19次は2025年2月~4月。最新情報は公式サイト確認
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールやサービスを導入する際の費用の一部を補助することで、業務効率化やDX推進、サイバーセキュリティ強化を目的としています。IT導入補助金は直接的に協働ロボットの導入を主要な支援対象とはしていませんが、導入するITツールの内容によっては、補助対象となる可能性があります。
申し込み条件や給付金額、公募期間を確認
- 申込条件: 中小企業・小規模事業者等。IT導入支援事業者と共同申請、生産性向上計画が必要
- 給付金額: 通常枠 5万円~450万円/複数社連携IT導入枠 最大3,000万円
補助率: 通常枠 1/2(条件付き 2/3)、複数社連携枠 50万円以下 3/4(小規模は4/5)、50万円超 2/3 - 公募期間: 年間複数回。2025年も継続予定
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等が意欲をもって行う大胆な事業再構築への挑戦を支援し、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。補助対象となる経費には、設備投資やシステム構築費が含まれており、これらは協働ロボットの導入費用にも該当します。
申し込み条件や給付金額、公募期間を確認
- 申込条件: 売上減少要件等あり。事業計画策定、認定支援機関の確認が必要
- 給付金額: 成長分野進出枠 1,500万円~6,000万円(大幅賃上げ時 2,000万円~7,000万円)
- 公募期間: 最終第13回は2025年1月~3月、今後の新規公募は未定
地域振興補助金・地方自治体独自の支援金
地域振興補助金や地方自治体独自の支援金も、協働ロボットの導入に利用できる場合があります。申し込み条件や給付金額、公募期間を確認
- 申込条件: 自治体や団体による。地域振興に資する事業であることなどが求められる
- 給付金額: 地方自治体によって大きく異なる
- 公募期間: 自治体ごとに異なる。各自治体の公式サイト等で要確認
ここまでは4種類の補助金を解説しました。
補助金を活用して協働ロボットの導入を考えている方は、ご自身のニーズに合った補助金を使うのがおすすめです。
次のパートでは、よく誤解される補助金と助成金との違いを解説します。
助成金と補助金の違いは?
「補助金」と「助成金」は、どちらも資金援助を目的としていますが、支給される目的や使い道に違いがあります。以下の表で助成金と補助金の違いを比較します。
| 項目 | 補助金 | 助成金 | |||||||||||
| 目的 | 政府が特定の政策目標を達成するために、企業や個人の事業活動を支援する | 労働環境の安定や改善、雇用促進といった、より社会的な側面に焦点を当てた支援策 | |||||||||||
| 管轄 | 経済産業省、文部科学省、その他の省庁および地方自治体 | 厚生労働省および都道府県労働局、ハローワーク | |||||||||||
| 給付額の範囲 | 数10万円から数10億円 | 数10万円から数100万円程 | |||||||||||
| 受給 のしやすさ |
採択率は比較的低い傾向 | 比較的容易に受給できる場合が多い | |||||||||||
| 申請期間 | 期間は比較的短い場合がある | 早期に受付終了となることもある。 | |||||||||||
| 主な対象分野・業種 | 製造業、IT、事業再構築、省力化投資、地域活性化、環境対策など | 幅広い業種における雇用・労働環境改善 | |||||||||||
両者の主な違いは、補助金は事業活動を支えるための資金であり、助成金は社会的な活動や公益的な目的を支援するための資金という点です。
補助金は使い道が制限されていることが多く、助成金はより自由に使える場合が多いです。
また、補助金の主な管轄は経済産業省で、助成金の主な管轄は厚生労働省や都道府県労働局、ハローワークが行っており、対象となる分野や業種も異なります。
この章では、4種類の補助金と助成金を解説しました。次の章では、補助金を活用する際の注意点を解説します。
協働ロボットの導入時に補助金を活用することを考えている方は、トラブル防止のためにも注意点をご確認ください。
協働ロボット導入で補助金を活用する際の注意点
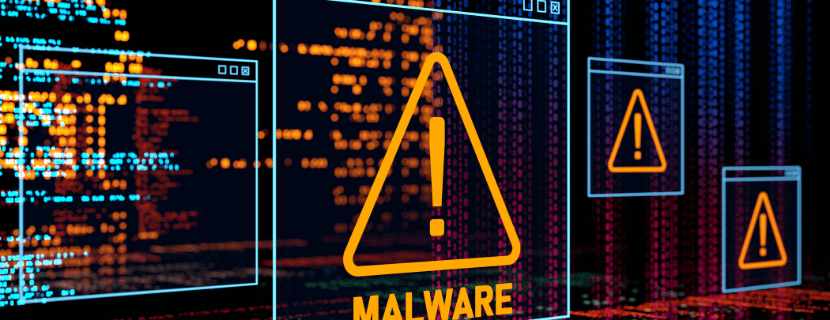
協働ロボットを導入するために補助金を申請する際は、注意点を把握しないまま進めると、思わぬリスクが生じる可能性があります。
協働ロボット導入時に補助金の活用を検討されている方は、ぜひ本章をご一読ください。
補助金を活用する際の3つの注意点を解説
1. 導入後の効果測定と報告義務
補助金を受けた企業には、導入した協働ロボットの効果を報告する義務があります。報告内容には、協働ロボットの稼働状況や生産性の向上、業務改善の成果などが含まれます。
協働ロボット効果測定をきちんと行い、必要な書類を提出しなければ、補助金の返還を求められる可能性もあります。
そのため、導入後は定期的に効果を確認し、報告義務をしっかりと果たすことが必要です。
2. 変更・中止の際の取り決めに注意
補助金を受けて事業を進める中で、計画に変更が生じたり、中止を余儀なくされる場合もあるかもしれません。その際は、事前に補助金の提供機関に承認を得る必要があります。
計画変更や中止が認められない場合もあるため、事業の進行に影響を与える変更がある場合には、速やかに担当者に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
3. 申請手続きが複雑
補助金申請には専門的な知識や手続きが求められます。初めて申請を行う企業の場合、書類の準備や事業計画の作成に困ることが多いでしょう。
そこで、申請に関する経験豊富な専門家に相談することを強くおすすめします。専門家のサポートを受けることで、手続きの漏れを防ぎ、スムーズに申請を進めることができます。
ここまで、補助金が協働ロボットの導入にかかる高い初期費用を抑えることができると説明してきましたが、他にも協働ロボットを低価格で導入する方法があります。他の方法も知りたい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事
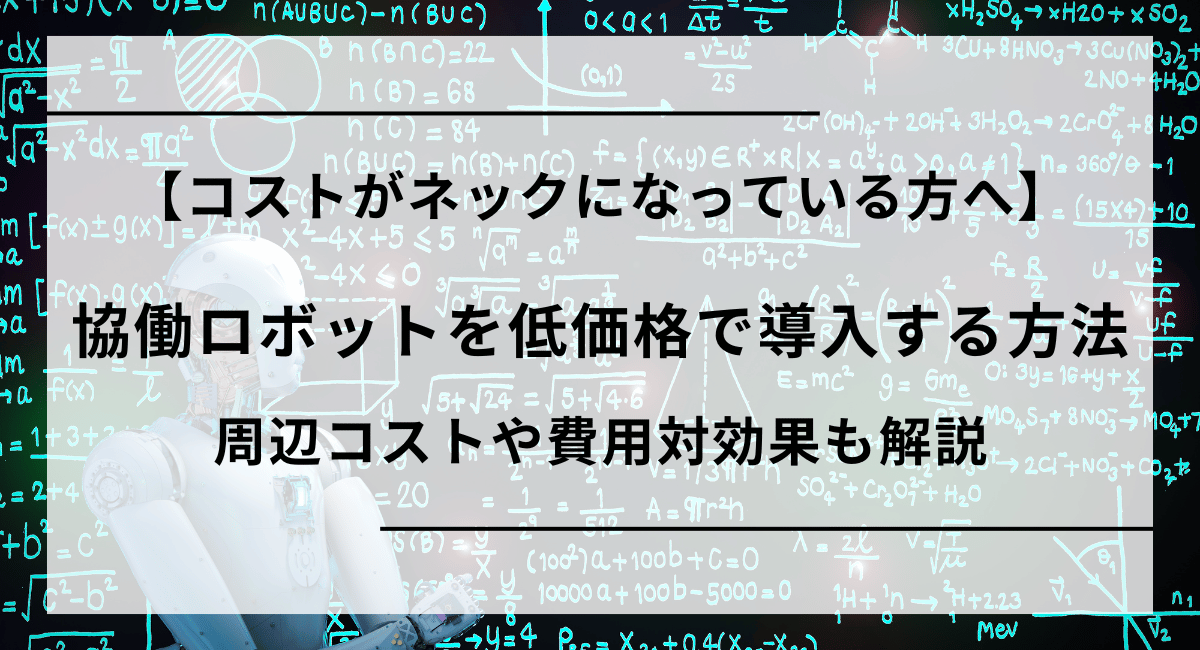
協働ロボットを低価格で導入する方法を8つ紹介!周辺コストや費用対効果も解説
本記事のまとめ
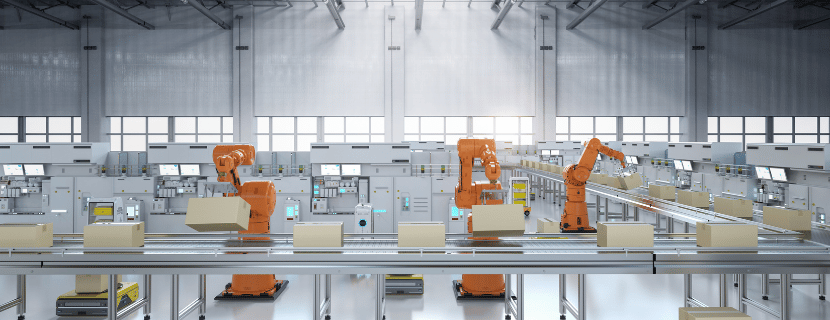
協働ロボットの導入における補助金は、企業の初期投資負担を軽減し、効率的な生産体制の構築をサポートする重要な手段です。
各種補助金には申請条件や期限、審査基準があるため、しっかりと確認し、準備を整えることが大切です。
また、申請手続きや計画変更の際には専門家のサポートを受けることで、スムーズな導入が可能になります。
補助金を活用することで、協働ロボット導入による業務改善や生産性向上が実現でき、長期的な競争力強化にも繋がります。
自社にぴったりの協働ロボットを探してみませんか?
実際の製品スペックや詳細な機能は、こちらからチェックしてみてください。
