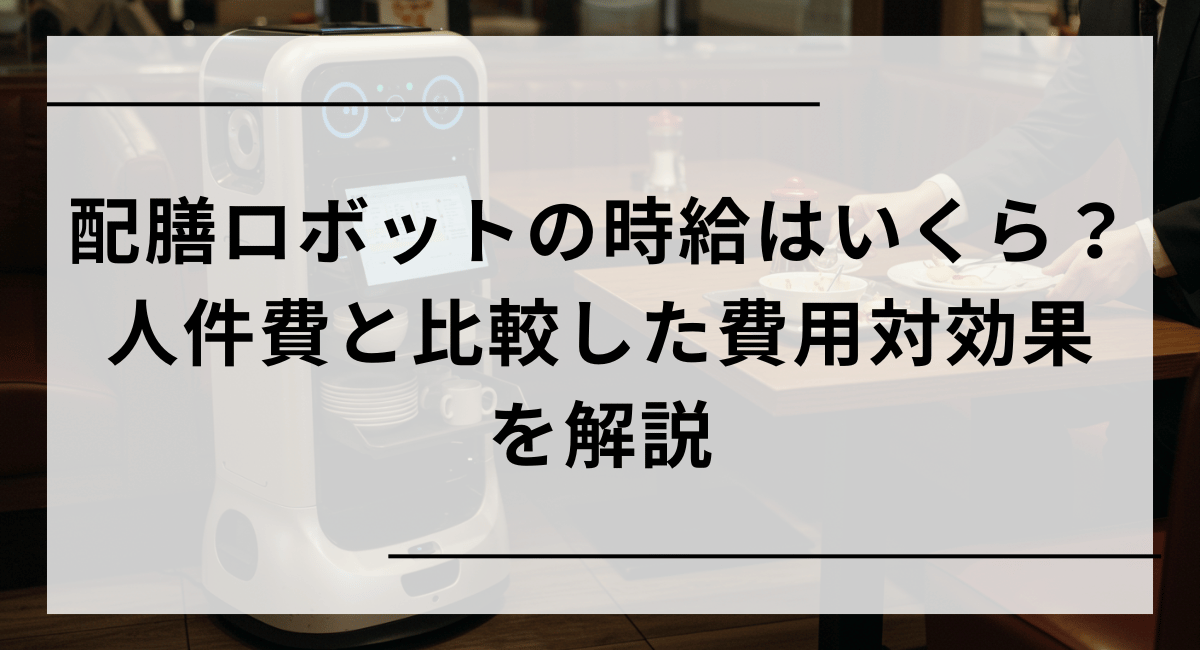
配膳ロボットの時給はいくら? 導入価格と人件費を比較した費用対効果を解説
「配膳ロボットの時給は100円台」——。一度はこのような魅力的な言葉を耳にしたことがあるかもしれません。深刻化する人手不足と高騰する人件費に悩む多くの店舗にとって、配膳ロボットの導入は効果的な手段の一つであると言えます。
しかし、この「時給100円台」という数字は本当なのでしょうか?そして、配膳ロボットの価格や、時給は、その耐用年数を通じて見ると、本当に人間のスタッフを雇用するよりコストパフォーマンスは高いのでしょうか?
この記事では、配膳ロボットの時給を解説します。また、人件費の「真のコスト」と配膳ロボットの価格を比較し、費用対効果を徹底的に分析します。
配膳ロボットの導入を悩まれている方は是非ご一読ください。
配膳ロボットの時給を構成する要素を解説

配膳ロボットの時給が「100円台」などと表現される場合、それは一般的に以下の計算式に基づいています。
ロボットの時給 = 導入・運用にかかる総コスト ÷ 総稼働時間
この計算式の各要素を詳しく見ていくと、「時給」が変動する要因が明らかになります。この章では配膳ロボットの時給がどのような要素から成り立っているのかを明確にします。
また、これらの情報をもとにモデルケースも紹介しますので、配膳ロボットの導入を考えている方は是非ご参考ください。
導入・運用にかかる「総コスト」の内訳
配膳ロボットのコストは、本体価格に加えて以下の費用を含め、総合的に考える必要があります。
導入費用(初期費用)
-
・購入
本体価格は1台あたり200万円台〜350万円程度が相場です。高機能な猫型ロボット「BellaBot」などは300万円を超えるケースもあります。
・リース・レンタル
月額3万円~10万円程度が一般的な価格帯であり、購入した場合に比べて、初期費用を抑えられます。
ソフトバンクロボティクスの「Servi」は月額99,800円(3年プラン) 、USENが扱うPudu社の「KettyBot Pro」は月額3万円台からのリースプランが提示されています。
※2025年7月時点での情報です。
次に運用費用を確認します。
運用費用(ランニングコスト)
-
・保守・サポート費用
リースプランには含まれていることが多いですが、購入の場合は別途契約が必要な場合があります。月額1万円から2万円程度が目安です。
・電気代
月額1,000円から3,000円程度と軽微ですが、継続的に発生します。
・その他
ソフトウェアのアップデート費用や、バッテリーなどの消耗品交換費用がかかる場合もあります。
※2025年7月時点での情報です。
ロボットの真のコストは、購入・リース費用といった初期費用だけでなく、保守・運用費まで含めた「総所有コスト(TCO)」で捉える必要があります。
購入(設備投資)とリース(運営費)のどちらを選ぶかは、キャッシュフローや技術陳腐化のリスクをどう考えるかという企業の財務戦略に関わる重要な判断です。
単純な価格比較だけでなく、長期的な視点でのコスト評価と、ベンダーが提供するサポート体制の内容まで含めて検討することが不可欠です。
次に、総労働時間を算出します。
「総稼働時間」を左右する2つの要素
計算式の分母となる「総稼働時間」は、主に以下の2つの要素で決まります。
耐用年数
これは配膳ロボットの価格を期間で割る際の重要な指標です。税法上の法定耐用年数は、ロボットの分類によって異なり、「機械及び装置」として7年から10年と見なされることが多い傾向にあります。
しかし、ベンダーがリース契約やROI計算で用いるのは、技術の陳腐化を考慮したより実用的な耐用年数である3年または5年という期間が一般的です。この期間設定が短いほど、月々の費用は高くなります。
店舗の稼働時間
ベンダーの時給計算では、1日12時間・月30日稼働といった、高い稼働率が前提とされることが多く、これが「時給100円台」という数値を算出する要因となっています。
これまでの分析をまとめ、具体的なモデルケースで配膳ロボットの現実的なコストを見てみましょう。
多くのベンダーが提供する一般的なリースプラン(例:保守費用込みで月額約11万円、3年契約)を基に、稼働時間による「実質的な時給」の変動を以下の表にまとめました。
【結論】モデルケースで見る、配膳ロボットの現実的なコスト
これまでの分析をまとめ、具体的なモデルケースで配膳ロボットの現実的な費用を見てみましょう。
多くのベンダーが提供する一般的なリースプラン(例:保守費用込みで月額約11万円、契約期間(実用的な耐用年数)3年)を基に、稼働時間による「実質的な時給」という価格の変動を以下の表にまとめました。
| モデルケース | 店舗タイプ | 月間総労働時間 | 実質時給(概算) | ||||||||||
| ケースA | 長時間営業の店舗 (1日12時間・月30日) | 360時間 | 約306円 | ||||||||||
| ケースB | 一般的なレストラン (1日10時間・月26日) | 260時間 | 約423円 | ||||||||||
| ケースC | ランチ限定営業のカフェ (1日6時間・月22日) | 132時間 | 約833円 | ||||||||||
【結論】
このように、配膳ロボットの「時給」は固定された価格ではなく、導入する店舗の「使い方」に依存する変動値です。
魅力的な広告の数字を鵜呑みにせず、自店の営業実態に合わせて「総所有費用」と「総稼働時間」から現実的なコストを算出することが、正確な費用対効果を測るための第一歩となります。
この章では、配膳ロボットの時給を構成する要素である、「導入・運用にかかる総コスト」と「総稼働時間」の2つ確認しました。
次の章では配膳ロボットの時給を正しく評価するために、比較対象である人件費について解説します。
人件費の「本当の」コストとは?

配膳ロボットの時給を評価するためには、比較対象である「人間のスタッフ」を一人雇用するために、企業が実際にどれだけの費用を負担しているかを知る必要があります。
このコストは、従業員に支払う時給だけではありません。
時給に上乗せされる社会保険料
企業は、従業員の給与に加えて、社会保険料の事業主負担分を支払う義務があります。これは法律で定められており、見過ごされがちですが人件費を占める要素の一つです。
令和6年度の料率(東京・飲食店の場合)を例に見ると、事業主が負担する社会保険料は、従業員に支払う給与額のおおよそ15%〜16.5%に相当します。
| 保険の種類 | 事業主負担割合(対賃金) | ||||||||
| 健康保険料 | 4.955% | ||||||||
| 介護保険料(40歳以上) | 0.80% | ||||||||
| 厚生年金保険料 | 9.15% | ||||||||
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | ||||||||
| 雇用保険料 | 0.95% | ||||||||
| 労災保険料 | 0.3% | ||||||||
| 合計(40歳以上の場合) | 約16.565% |
※2025年7月時点での情報です。
首都圏の飲食店、ホールの平均時給を1,303円とします。※¹ この時給をモデルケースとして、企業が負担する真のコストを計算してみましょう。
この従業員(40歳以上)を雇用する企業の実質的な時間当たりコストは以下のように計算されます。
1,303円(時給) + 1,303円 × 16.565%(社会保険料) = 約1,518円
つまり、時給1,303円のスタッフを一人雇用するための「本当のコスト」は、社会保険料を上乗せするだけで約1,518円になるのです。
この金額が、配膳ロボットの時給と比較する際の参考となります。
※1 参考:食ジョブ 【東京都】業態別/職種別 正社員・アルバイト・パートの平均月給・時給データ
給与明細に載らない「間接コスト」
さらに、採用活動や教育、日々の管理にも目に見えないコストが発生しています。
採用コスト
新しいスタッフを一人採用するまでにかかる費用です。これは「外部コスト」と「内部コスト」に分けられます。
-
外部コスト
求人サイトへの掲載料、人材紹介会社への成功報酬、合同説明会の出展料などが含まれます。
内部コスト
書類選考や面接に費やす採用担当者や店長の人件費、応募者への連絡業務にかかる時間などが含まれます。
上記から、飲食業界のアルバイト採用単価は、平均で一人あたり約5万円から7万円です。正社員や専門職(調理人など)の場合は数十万円に達することもあります。
研修コスト
新人スタッフのオンボーディングにかかる時間(研修担当者と研修生双方の時間)。
管理コスト
シフト作成、給与計算、労務管理などに費やす時間。
福利厚生費
交通費、制服の支給、食事補助など。
【結論】結局、総人件費はいくらになるのか?
では、社会保険料とこれらの間接コストを合わせると、従業員一人あたりの総人件費は最終的にいくらになるのでしょうか。
間接コストは企業の規模や採用方法、研修内容によって大きく変動するため、一概に算出することは困難です。しかし、一般的に直接人件費(給与+社会保険料)に加えて、さらにその10%〜20%程度の間接コストがかかると想定することで、より現実に近い数値を予測できます。
先ほどのモデルケースで考えてみましょう。
時給1,303円の場合は、社会保険料込みの実質時給約1,518円になるので、この値に間接コストとして15%を上乗せしてみます。
約1,518円 × 1.15(間接コスト分) = 1,745.7円
つまり、時給1,303円で募集しているスタッフ一人を雇用・維持するための「真のコスト」は、時給換算で1,700円を超える可能性があるということです。
これは、額面の時給の約1.33倍に相当します。採用難が続く昨今では、採用コストがさらにかさみ、この金額はさらに上昇する可能性も十分に考えられます。
この「総人件費」こそが、配膳ロボットの費用対効果を判断する上で、比較すべきベンチマークとなるのです。
この章では人件費を構成する要素を詳細に解説しました。次の章では、ここまで解説した配膳ロボットの時給と人件費を比較した結論を解説します。
コスト比較:配膳ロボットの時給と人件費を徹底検証
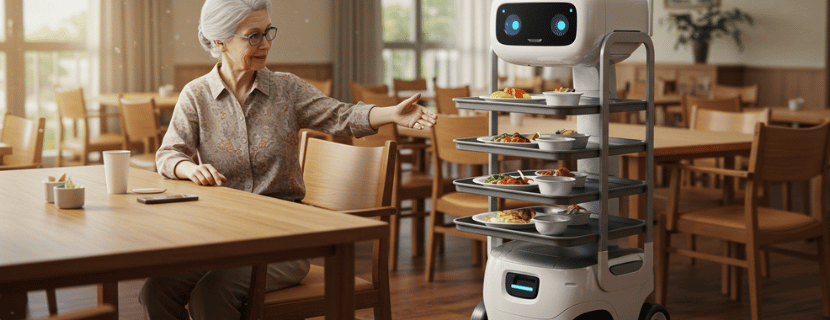
この章では、ここまで解説した配膳ロボット 1 台の実質時給(総所有コスト換算)と、スタッフ 1 名の総人件費(給与・法定福利費・間接コストを含む)を同一稼働条件で比較し、両者のコスト差と経営インパクトを定量的に示します。
- 人間の総人件費(時給換算): 約1,745円
- ロボットの実質時給(一般的なレストラン): 約423円
単純なコスト比較では、配膳ロボットの方が圧倒的に安いという結果になります。しかし、判断はまだ早計です。コストだけでなく「パフォーマンス」も比較する必要があります。
以下の表では、配膳ロボットの導入と人間のスタッフを雇った場合に想定されるパフォーマンスを比較します。
| 項目 | 配膳ロボット | 人間のスタッフ | |||||||
| 稼働時間 | 1日12時間以上、休憩不要で連続稼働可能 | 労働基準法に基づく(休憩必須) | |||||||
| 作業の一貫性 | 常にプログラム通りに動作し、品質が安定 | 体調や感情、習熟度により変動する可能性 | |||||||
| 運搬能力 | 一度に最大30〜40kg運搬可能 | 個人の体力に依存し、一度に運べる量に限界 | |||||||
| 衛生管理 | 料理に直接触れず衛生的 | 手指の接触機会が発生 | |||||||
| 柔軟性と接客 | 定型業務に特化。複雑な指示や対話は限定的 | 臨機応変な対応、おもてなし、メニュー推薦など高度な接客が可能 | |||||||
| 疲労と負担 | なし | 肉体的・精神的負担が大きい | |||||||
| 安全性 | 高性能センサーで障害物を回避 | 注意力に依存。疲労によるミスも | |||||||
この比較からわかるように、配膳ロボットは「単純・反復作業」において、人間を凌駕するパフォーマンスを発揮します。休憩なしで長時間稼働し、常に一定の品質で重いものを運び続ける持久力と安定性は、配膳ロボットならではの強みです。
一方で、人間のスタッフの強みは「柔軟性と創造性」にあります。お客様の表情を読み取ってサービスを変えたり、メニューについて詳しく説明したり、予期せぬトラブルに臨機応変に対応したりといった「おもてなし」の心は、現在のロボット技術では再現が困難です。
したがって、どちらか一方が優れているという二元論ではなく、「適材適所」で考えることが重要です。配膳ロボットに配膳・下げ膳などの体力を要する単純作業を任せ、人間は人間にしかできない高度な接客や店舗マネジメントに集中する。この「協働」こそが、パフォーマンスを向上する鍵となります。
まとめ:配膳ロボットの時給と人件費を比較してわかること

配膳ロボットの「時給」は、稼働時間によって変動するものの、社会保険料などを含めた人間の「総人件費」と比較すると、コスト面で優位性があることがわかります。
しかし、その真の価値は単なるコスト削減に留まりません。従業員の負担を軽減し、より付加価値の高い接客に集中させることで、サービス品質と顧客満足度を向上させ、結果的に売上アップや人材の定着といった、持続可能な店舗経営へと繋がるでしょう。
配膳ロボットの導入は、もはや単なる経費削減策ではなく、人手不足時代を乗り越え、競合と差別化を図るための重要な「経営戦略」の一つと言えるでしょう。
この記事を参考に、自店の状況に合わせた最適な配膳ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
配膳ロボットの導入についてお聞きしたいことがありましたら、以下からお気軽にご相談ください。
