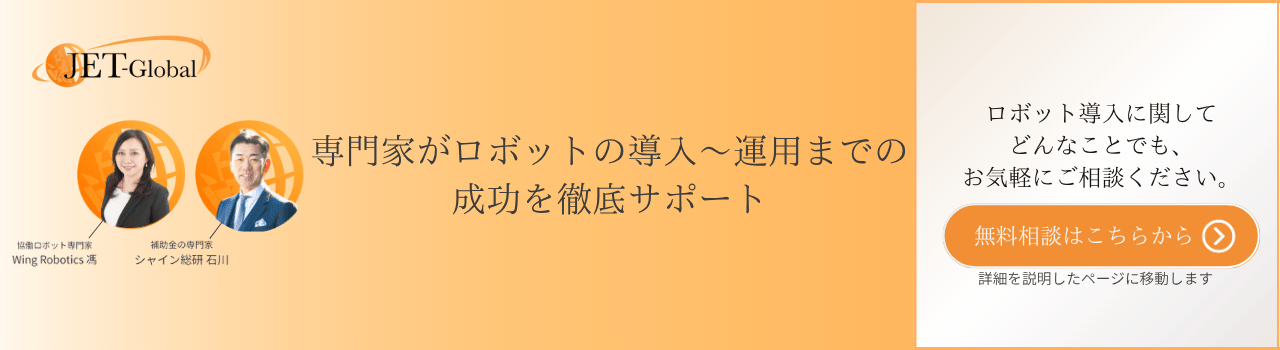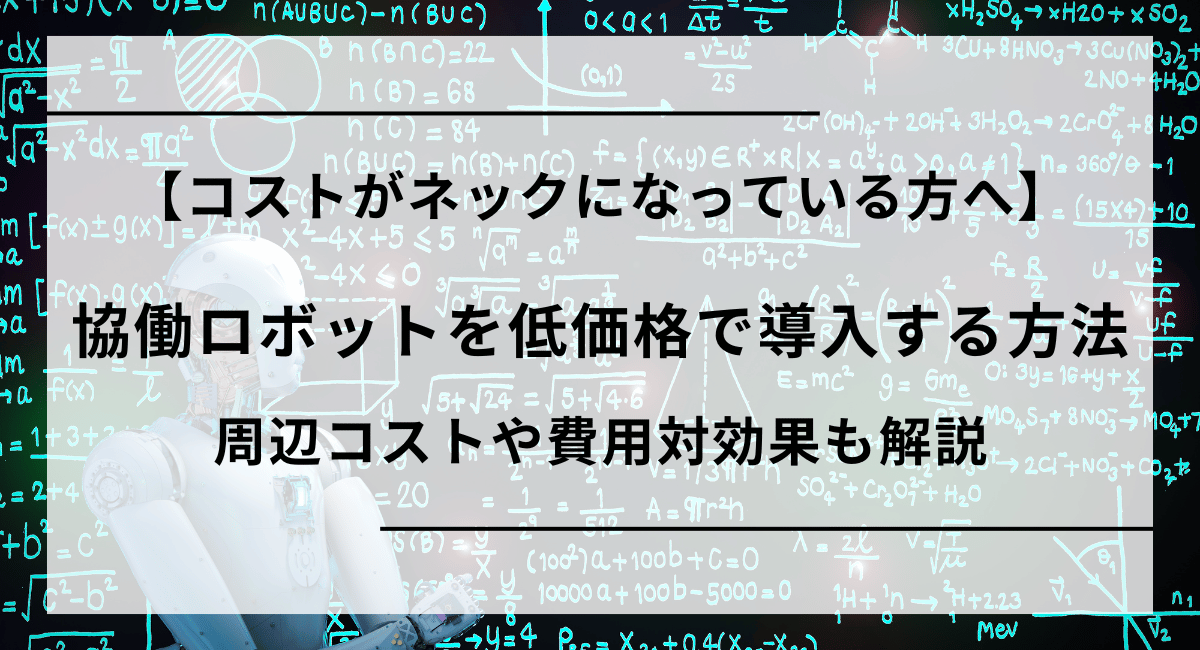
協働ロボットを低価格で導入する方法を8つ紹介!周辺コストや費用対効果も解説
「協働ロボットの導入に興味はあるけど、価格的に難しそう」とお考えではありませんか?やり方次第で、協働ロボットを低価格で導入する方法は多数あります。
本記事では、そんな協働ロボットを低価格で導入するための方法を、8つ紹介します。これらを実践することで、初期投資を抑えつつ自社のニーズに合った製品を導入できるでしょう。
また記事の後半では、協働ロボット導入にかかる費用の詳細や、ROI・費用対効果を高める方法も解説します。協働ロボットの価格を少しでも抑えたい方はぜひご覧ください。
協働ロボットを低価格で導入する方法8選を紹介
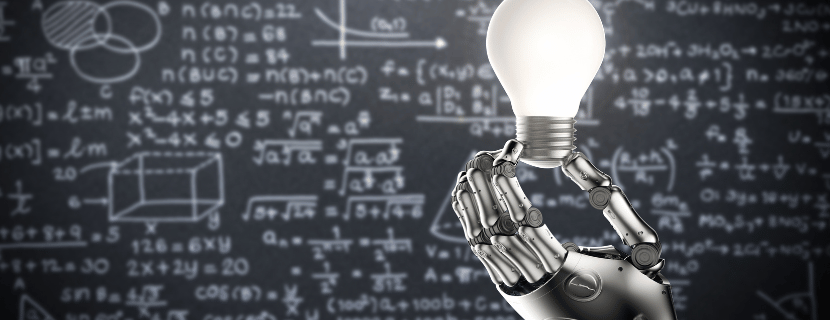
本章では、協働ロボットの導入を低価格で進めるための方法を8つ紹介します。自社のニーズや目的、状況から最適な方法を選んでコストを抑えましょう。
紹介する方法は以下の8つです。
補助金を活用する
補助金の活用も、協働ロボットを低価格で導入する有効な手段です。特に2025年現在、協働ロボットの導入に使えるさまざまな補助金が提供されているので、最大限活用することをおすすめします。
具体的には「中小企業省力化投資補助金」や「ものづくり補助金」等があり、協働ロボットをはじめ幅広い設備投資に活用できます。
その中でも特におすすめなのが「中小企業省力化投資補助金(一般型)」です。こちらは2025年3月からスタートした新しい補助金で、補助額は最大で1億円です。また、補助金が下りる事業の対象範囲も比較的広いと言えます。
ただ、中小企業省力化投資補助金は申請自体が煩雑であるというデメリットもあります。活用の際は、自身で詳しく調べるか、補助金導入の専門家に相談するのがおすすめです。
「補助金を活用したいが、手続きが複雑で時間がない」「事業計画書の作成が難しく、採択されるか不安だ」
このようなお悩みはございませんか?
JET-Roboticsは、補助金申請の専門家がお客様に代わり、事業計画の策定から申請書類の作成、採択後の手続きまで一貫してサポートいたします。
採択のポイントを熟知した専門家が伴走するため、お客様は本来の事業に集中しながら、採択率の向上を目指すことが可能です。
「そもそも、どの補助金が使えるのか分からない」という段階でも歓迎です。ご相談は無料ですので、まずは下記のサービス詳細をご覧ください。
以下の記事では、中小企業省力化投資補助金の特長や条件、注意点などを詳しく解説しています。協働ロボットの導入を考えている方は、補助金の活用で導入コストを抑えられる可能性がありますので、ぜひご一読ください。
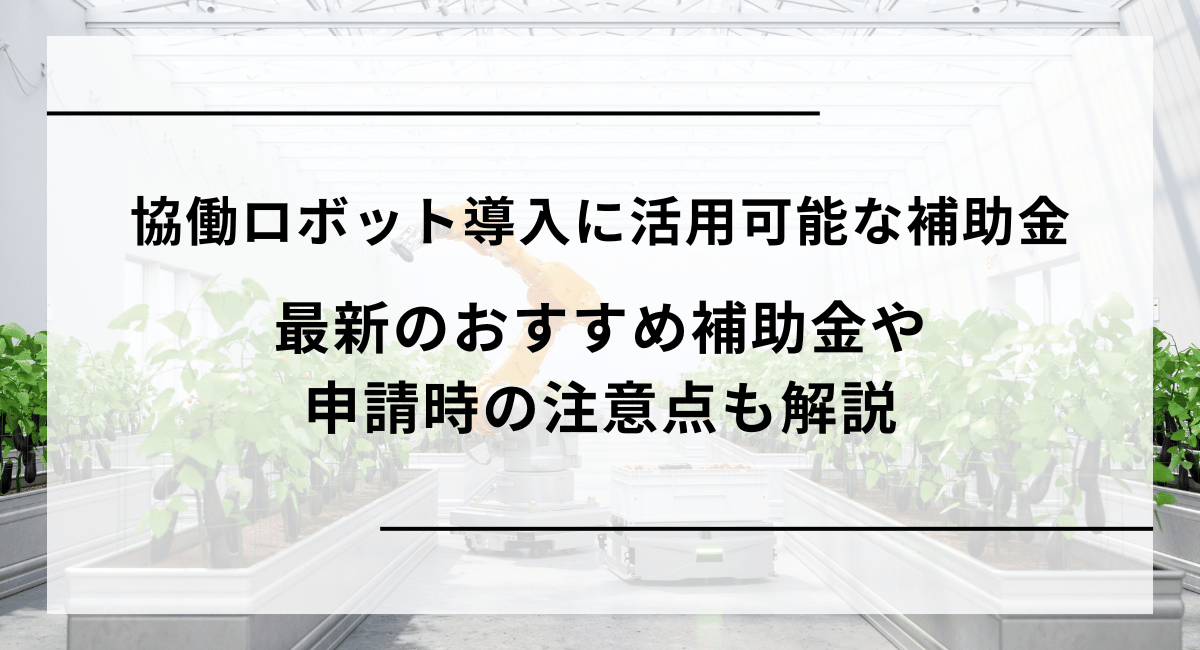
オプションを最小限にする
協働ロボットを低価格で導入する方法1つ目は、オプション機能を最小限にすることです。高度なセンサーや複雑なビジョンシステムなどのオプションは、導入コストを押し上げます。そのため、本当に必要な機能だけを選ぶことが重要です。
そのため、中小企業や多品種少量生産を行っている企業では、「製品・作業分析」を行い、導入する協働ロボットに必要な機能を厳選しましょう。
例えば、高性能な協働ロボットで一度に多くの工程を自動化するのではなく、最初は導入効果が高い作業や工程に焦点を当て、段階的に自動化を進める方法が有効です。
以上のように、自社の作業工程を改めて振り返ったうえで必要最小限のオプションに絞ることで、低価格での協働ロボット導入が実現します。また、事前分析と段階的導入はコスト削減だけでなく、費用対効果を最大化にもつながります。
分割払いの利用を検討する
協働ロボットの導入において、分割払いを利用することで初期投資の負担を軽減できます。高額な協働ロボット機器を一度に購入するのが難しい場合でも、分割払いを活用することで、月々の支払いを抑えて資金繰りを楽にできるでしょう。
多くのメーカーや代理店が分割払いサービスを提供しており、例えば、高島ロボットマーケティングは、SMBCファイナンスサービスと提携し、最大72回の分割払いを提供しています。また、セレンディップも最長6年の分割払いサービスを提供しています。
分割払いの条件や手数料はサービス提供者によって異なるため、企業は自社の資金状況に合わせて柔軟に支払い計画を立てることが大切です。
まとめると、分割払いを利用することで、初期投資を抑えつつ効率的に協働ロボットを導入でき、業務改善の技術を早期に取り入れられます。
レンタル・リースの選択肢もある
協働ロボットを低価格で導入したい企業にとって、レンタルやリースは有効な選択肢です。短期間の需要や試用を考えている企業にとっては、特にレンタル・リースは魅力的でしょう。
レンタル・リースの主なメリットは、初期投資の軽減、税金や保険料がかからないこと、不要になった場合の保管場所が不要と多岐にわたります。また、中小企業にとって、資金繰りを楽にしリスクを低減する手段としても最適です。
さらに、協働ロボットの管理やメンテナンスもレンタル・リース料金に含まれていることが多く、運用面でも安心感が強いでしょう。
例えば、ファナックの「CRXシリーズ」は6ヶ月のお試しレンタルで月額19万7000円から利用可能です。また、立花エレテックは最短1日からのレンタルプランも提供しています。
ただ、協働ロボットのレンタル・リースは初期費用を抑えられる一方で、長期的に活用していく場合には、購入してしまったほうが低価格で導入できるという注意点もあります。
そのため、自社の協働ロボット活用プランについて再度検討をしたうえで、必要であればレンタルやリースを使って初期費用を抑えましょう。
中古品の協働ロボットなら低価格で導入可能
中古品の協働ロボットを低価格で導入するのも、1つの方法です。中古市場では新品の半額以下で協働ロボットを購入できることもあり、特に、予算が限られている中小企業にとって魅力的でしょう。
ただし、中古の協働ロボットを購入する際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。業者によって協働ロボットの状態や品質が異なるため、アフターサポートや保証制度が整った業者から購入しましょう。
保証付きの中古協働ロボットを選ぶと、万が一の故障に備えることができ、安心して使用しやすいです。
プラグアンドプレイ形態で既存システムとの連携を最適化する
協働ロボットを低価格で導入するなら、既存のシステムとの連携も重要です。プラグアンドプレイ型の協働ロボットを選ぶことで、複雑な設定やインターフェース開発が不要になり、導入コストを抑えられます。
そもそもプラグアンドプレイ型製品とは、既存の生産ラインや作業環境に合わせた連携が可能な製品を指します。具体的なメリットは、設備やソフトウェアとすぐに接続できるため、導入が迅速に進み、コストも抑えられる点です。
以上より、プラグアンドプレイ型で協働ロボット導入したい場合は、まず、自社の既存システムや連携する予定のツールの接続を確認しましょう。それに合わせた協働ロボットを選定することで、低価格での導入を実現できます。
性能を吟味したうえで安いメーカーから購入する
協働ロボットは同じような性能を持っている製品でもメーカーによって価格が異なります。そのため、自社が求める性能があるかは十分に吟味したうえで、より低価格な協働ロボットを導入するのも1つの方法です。
一般的に、協働ロボットの価格は200万円から500万円程度ですが、最近では技術革新と競争の激化により、低価格で性能が高い製品も登場しています。
例えば、igusの「ReBeLシリーズ」やFAIR Innovationの「FAIRINO Robot」は、100万円程度の低価格から導入可能な協働ロボット提供しています。
一方で、ただ低価格であるという理由だけで協働ロボットを選んでしまうと、自社に必要な性能が付帯しておらず導入が失敗に終わってしまう可能性が高いです。そのため、機能面の吟味は必須になります。
また、確かに協働ロボットの導入は大きな投資なので、知名度のあるメーカーの製品を選びたくなるでしょう。しかし、日本での知名度こそまだ低いものの、高性能と低価格を実現している協働ロボットが出てきているので、一度検討してみてください。
以下の記事では、高性能と低価格を実現している企業を始め、世界的にシェアの高い企業や日本の有名企業など、おすすめの協働ロボットメーカーを多数紹介しています。各メーカーや製品の特徴・強みを知りたい方はぜひご覧ください。
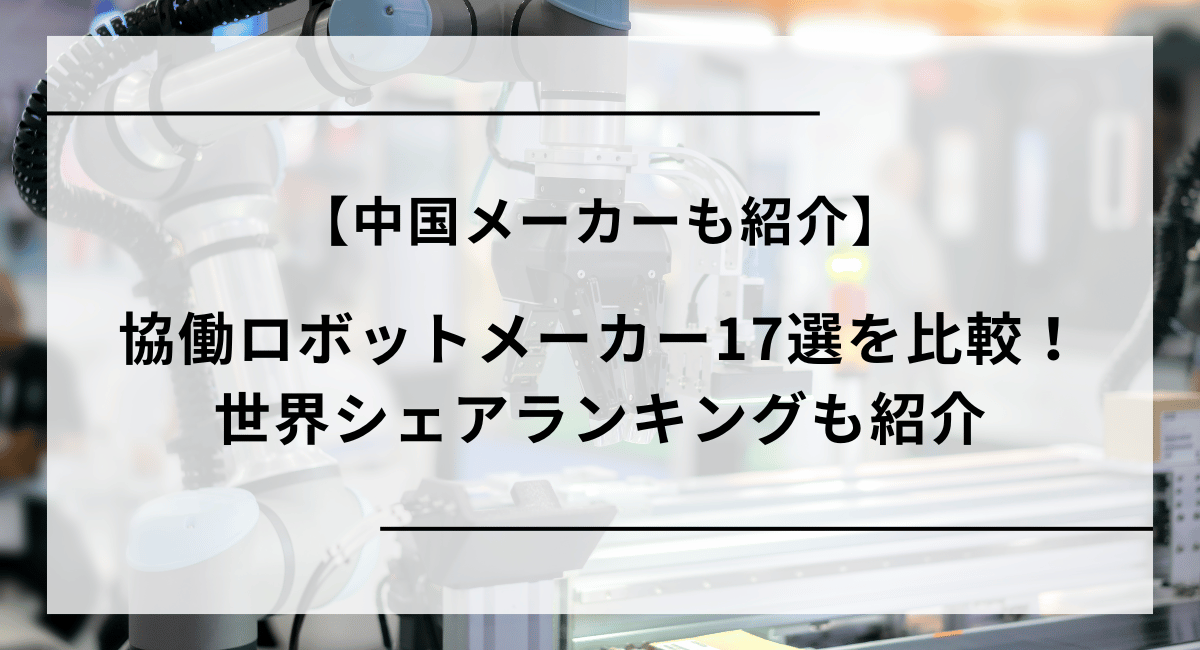
SIerを介さずに導入を行う
SIerを介さずに、協働ロボットを自社で導入することでも、コストを削減可能です。
SIerに依頼すると、協働ロボット本体の価格に加え、システム設計やプログラミング、周辺機器の手配などで高額な費用がかかります。一例ですが、協働ロボット本体が500万円でも、SIerによる費用が1,000万円に達する場合もあります。
一方、自社内の担当者がティーチングや操作を学習できれば、外部SIerに頼らずに協働ロボットを低価格で導入可能です。
最近の協働ロボットは、直感的に操作できるティーチング機能やAIを活用した自動ティーチングシステムが搭載されており、専門的な技術がなくても現場作業者が比較的簡単にプログラムできます。
また、操作トレーニングやティーチングに関する教育を一緒に提供しているメーカーや販売代理店もあるので、それらを活用することでも協働ロボットの導入コストを抑えられます。
以上が、協働ロボットを低価格で導入する8つの方法です。自社にとって一番よさそうな方法を見つけられたでしょうか?
次章では、そもそも協働ロボットを導入しようとするとどれくらいの費用がかかるのかを説明します。
そもそも協働ロボット導入にかかるコストはどれくらい?

本章では、協働ロボットを導入する際に発生するコストを解説します。協働ロボット導入には、ロボット自体の費用以外にも様々なお金がかかってきます。
これらをしっかりと理解しておくことが、最終的な低価格での導入にもつながってくるのでぜひご一読ください。
協働ロボットの導入にかかるコストは以下の5つです。
協働ロボット本体の価格
協働ロボット本体の価格相場は、一般的に200万円から500万円程度で、ロボットの可搬重量や性能、メーカーによって変動します。
例えば、可搬重量が大きく、リーチが長く、自由度が高い協働ロボットほど価格は高くなります。また、高度な安全機能やビジョンシステムなど、特別な機能を搭載している場合も価格が上昇します。
近年では、100万円以下の低価格協働ロボットも登場しており、中小企業でも導入しやすくなっています。例えば、igusの「ReBeLシリーズ」やFAIR
Innovationの「FAIRINO Robot」などがその例です。
関連装置や周辺機器の価格
協働ロボットを導入するには、本体の他にさまざまな関連装置や周辺機器が必要になります。
具体的には、ロボットハンド(グリッパー)、架台、安全センサー、カメラなどです。これらの周辺機器の価格は、実現したい自動化機能に応じて変動します。
例えば、簡単なワークの投入・取り出し作業であれば比較的安価なハンドで十分ですが、複雑な作業には高機能なビジョンシステムやハンドが必要となり、コストが増加する傾向にあります。
意外と変動が大きいSIer費用
システムインテグレーション(SI)とは、協働ロボットを既存のシステムや生産ラインに連携させるための設計や調整を行う作業です。システムインテグレーション費用は、依頼するSIer(システムインテグレーター)や導入規模によって異なります。
SIerに依頼した場合、費用は数百万円に達することもあります。特に、協働ロボット本体に加えて関連機器の調整やシステム全体の最適化を行う場合、コストは高くなるでしょう。
人材教育にかかるコスト
協働ロボットを安全かつ効率的に運用するためには、作業者への教育・トレーニングが必要です。教育には、協働ロボットの基本操作やティーチング方法、安全に関する知識などが含まれます。
メーカーや外部機関が提供する教育プログラムがありますが、これらの活用にも別途費用がかかる場合があります。
ただし、協働ロボットは産業用ロボットよりも操作が簡単であるため、教育の難易度は比較的低いです。それでも、業務の最適化やトラブルシューティングのためには、一定の専門知識を持った作業者の育成が重要でしょう。
ティーチングやメンテナンスにかかるその他の費用
協働ロボットの性能を維持するために、定期的にメンテナンスを行う必要があり、これにも一定のコストがかかります。メンテナンス費用の具体例は、定期的な点検、清掃、消耗品の交換などです。
また、協働ロボットで複雑な作業を自動化する場合や特殊な動作を記憶させる場合には、専門的な技術が求められ、そのための費用が発生することもあります。
総じて、協働ロボット導入にかかるコストは本体価格以外にも周辺機器やシステムインテグレーション費用、教育・メンテナンス費用など多岐にわたります。導入前にこれらの費用をしっかりと把握し、最適な予算を立てることが重要です。
以上が、協働ロボット導入にかかるコストの全体像です。
次章では、協働ロボット導入のROIの計算方法や、費用対効果を高めるためのポイントを解説します。協働ロボットへの投資効果を最大化したい方はぜひご覧ください。
ROI・費用対効果を計算して回収の見込みを立てよう

協働ロボットの導入において、投資の回収見込みを立てることは重要です。これにより、協働ロボットの導入が事業に与える影響を定量的に把握し、合理的な投資判断が可能になります。
ROI(投資収益率)や投資回収期間を計算することで、協働ロボット導入の効果を明確にし、最適な運用計画を立てることができるでしょう。
投資回収期間の計算式
投資回収期間は、協働ロボット導入にかかった費用を何年で回収できるかを示す指標です。計算式は以下の通りです。
例えば、協働ロボットの導入に800万円の投資が必要で、年間400万円の人件費削減が見込まれる場合、投資回収期間は以下のように計算されます。
この場合、2年で投資回収ができることになります。投資回収期間を把握することで、企業は協働ロボット導入に伴うリスクを評価し、適切な投資判断を下せます。
協働ロボット導入で生まれる利益は人件費の削減だけではない?
協働ロボットを導入することで得られる利益は、人件費の削減だけではありません。実際には以下のようなさまざまな利益が生まれます。
これらの利益を総合的に考慮することで、協働ロボット導入の費用対効果が一層明確になります。
ROIを高めて協働ロボットの投資回収を早める方法
ROIを高め、協働ロボットの投資回収期間を早めるためには、以下の方法が効果的です。
これらのポイントを抑えることで、ROIを最大化し、協働ロボット投資回収期間を短縮可能です。
産業ロボットとの価格比較もしておくのがおすすめ
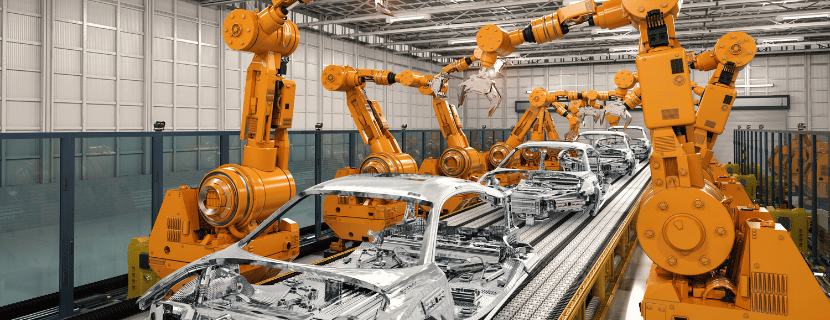
協働ロボットと産業用ロボットは、コストや導入方法に違いがあります。
産業用ロボットは高性能で大量生産向けに設計されており、安全柵や基礎工事が必要なため、初期費用や設置コストが高額になります。一方、協働ロボットは比較的低コストで導入でき、設置スペースも少なく、工事不要で移設も容易なため、特に中小企業に適した選択肢です。
また、操作やプログラミングにかかる費用についても協働ロボットに優位性があります。多くの協働ロボットはティーチングが簡単で、特別な専門知識が不要です。
対して産業用ロボットは、高度な技術者や専門的なサポートが必要で、導入後のメンテナンスコストもかかります。
しかし、産業ロボットは大量生産や高速動作に強みがあるので、導入目的によっては長期的に見ると、協働ロボットよりトータルコストが安くなる場合もあります。
そのため、改めて自社のニーズや達成したいことやその計画を整理したうえで、導入するロボットを選定しましょう。
まとめ|協働ロボットを低価格で導入するコツは自社のニーズを明確にすること
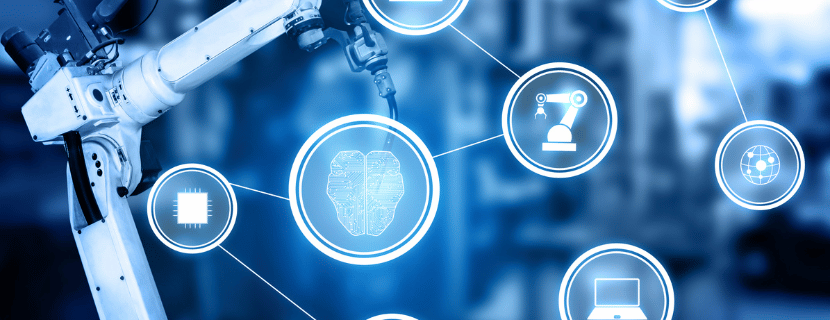
本記事では、協働ロボットを低価格で導入する方法を解説しました。
ただ、一つ一つの方法はただの手段なので、どんな目的でその手段を選ぶのかが肝心です。この目的が明確になっていないと、「協働ロボットを低価格で導入できたが、自社の現状は悪化した。」となりかねません。
そのため、まずは自社の現状を振り返り、協働ロボットを導入する目的を明確にしたうえで、どの方法を選ぶかを決めていくのがおすすめです。こうすることで、協働ロボットを低価格で導入しつつ、業務効率化や人手不足の解消を達成できるでしょう。
また、JET-Roboticsでは実際に、協働ロボットの導入支援も行っております。
ロボットの専門家による製品の選定から補助金の活用、ロボット研修による社内人材の育成まで、協働ロボット導入をあらゆる面からサポートいたします。
「一度ロボットを触ってみたい」や「こんな自動化ができるか知りたい」などの軽い相談も可能です。
相談は無料ですので、関心のある方は以下のサービス詳細をご覧ください。
自社にぴったりの協働ロボットを探してみませんか?
実際の製品スペックや詳細な機能は、こちらからチェックしてみてください。