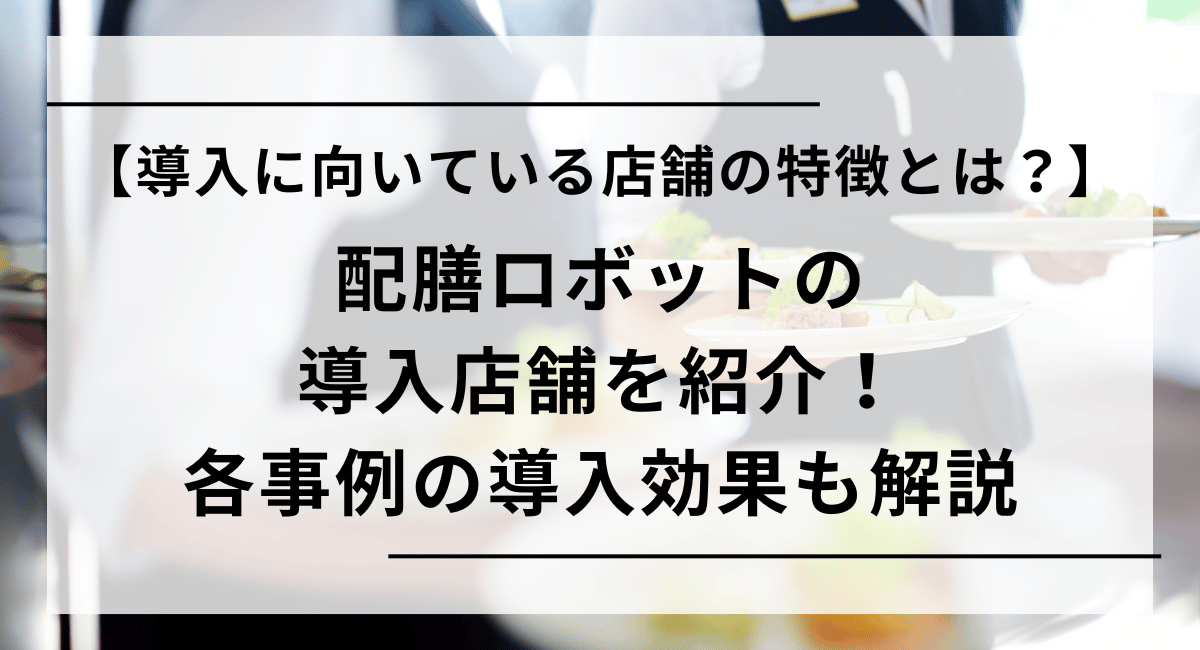
配膳ロボットの導入店舗を紹介! 各事例の効果や導入が向いている店舗の特徴まで解説
人手不足や業務効率化の課題を受けて、近年注目を集めている配膳ロボット。すでにファミリーレストランやホテル、介護施設など、さまざまな業態で導入が進んでおり、それぞれの現場に合った活用が広がっています。
この記事では、実際に配膳ロボットを導入している日本国内の5つの店舗・施設を取り上げ、それぞれが導入した製品や運用方法、得られた効果を詳しく紹介します。
また、導入が向いている店舗・向いていない店舗の特徴もあわせて解説しているため、これから導入を検討している方にとって、現場での活用イメージや判断材料として役立つ内容となっているでしょう。
配膳ロボットの導入店舗の事例を5つ紹介
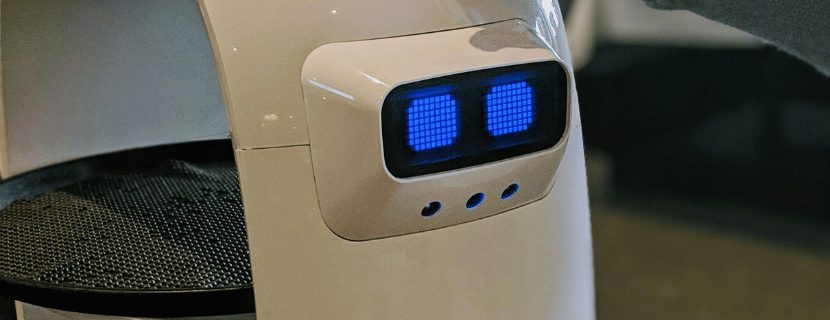
配膳ロボットは飲食店はもちろん、さまざまな業態の店舗に導入が進んでいます。
本章では、配膳ロボットの導入店舗の事例を5つ紹介します。各導入店舗の効果や活用方法も解説していますので、ぜひご覧ください。
ガスト|ファミリーレストラン
全国に2,000店舗以上を展開するファミリーレストラン「ガスト」では、慢性的な人手不足やホール業務の負担増を背景に、配膳ロボットの大規模な導入を進めています。
導入されたのは、中国Pudu Robotics社が開発した配膳ロボット「BellaBot(ベラボット)」です。
BellaBotは、タッチパネルでテーブルを指定するだけで、厨房から客席まで料理を自律走行で運ぶことができます。料理を配膳した後は、トレー上の空容器を検知し、自動で厨房へ戻る設計になっており、ホールスタッフの移動や回収の手間を減らしています。
2022年12月時点で、ガストを含むすかいらーくグループ全体で約2,100店舗に3,000台以上のBellaBotが導入されました。
導入効果としては、ホールスタッフの歩行数が平均で42%削減されたほか、離職率の低下にもつながっていると報告されています。
また、猫型の愛らしい外観を持つ配膳ロボットは、子ども連れのファミリー層を中心に人気が高く、店内での話題づくりや顧客体験の向上にも一役買っているようです。
ガストでは、こうした定量的な省力化効果と定性的な顧客満足度の向上の両面から、配膳ロボットの活用が進められています。
出典:ガストの「猫ロボット」成功のワケ わずか1年半で3000店導入 Watch|Impress Watch
出典:東洋経済オンライン
札幌ビューホテル|ホテル・旅館
札幌ビューホテル大通公園では、朝食ビュッフェ会場にBear Robotics社の配膳ロボット「Servi Plus」を導入しています。
宿泊客向けの朝食には毎朝300名から400名が来場するため、スタッフによる下膳業務が負担となっていました。
導入された「Servi Plus」は、トレーを複数同時に運べる大容量の配膳ロボットで、下膳専用として2台が稼働しています。お客様の使用済み食器を回収後、中間集積所まで自律走行で運搬することで、スタッフの移動距離と作業負荷を削減可能です。
同ホテルによると、配膳ロボット導入によってスタッフの移動距離が50%以上削減され、接客や清掃など他の業務に使える時間が確保できるようになったといいます。
加えて、従業員の業務効率向上だけでなく、宿泊客にとっても配膳ロボットの存在が話題となり、ホテル体験の付加価値にもつながっているようです。
出典:「Servi Plus」、『札幌ビューホテル 大通公園』へ導入 ゴルフ場・温浴施設にも導入拡大中|株式会社USEN-ALMEX
Greenガーデン南大分|介護施設
大分県にある特別養護老人ホーム「Greenガーデン南大分」では、介護スタッフの身体的負担軽減とケア業務への専念を目的として、Pudu Robotics社の配膳ロボット「BellaBot(ベラボット)」が導入されました。
施設内では、これまでスタッフが手押し台車で行っていた昼食約30人分の運搬業務を配膳ロボットが代替しています。厨房から食堂まで台車1台分の料理を一度に運べるため、従来3往復かかっていた搬送が1往復で済むようになりました。
また、来訪者が預けた荷物を玄関から各居室へ届ける業務にも配膳ロボットを活用することで、職員の移動回数を減らしながら、利用者対応の質を維持しています。こうした自動搬送の仕組みにより、スタッフが本来行うべきケア業務に集中しやすくなったと施設側は評価しています。
出典:【介護施設導入事例】Greenガーデン南大分さま|ネコ型配膳ロボット「BellaBot」|DFA Robotics
レストラン「オリーブ」|病院
香川大学医学部附属病院の敷地内にあるレストラン「オリーブ」では、病院DXの一環としてPudu Robotics社の配膳ロボット「BellaBot(ベラボット)」を導入しています。
省人化と非接触対応を目的に導入され、患者や職員が利用する飲食スペースでの新たな取り組みとして注目を集めています。
BellaBotは、配膳と下膳のセミセルフ化を実現し、スタッフが運搬業務から解放されることで、患者対応や店内サービスに注力できる体制が整えられました。特にランチタイムなどの混雑時においても、配膳ロボットが的確に動作することで、効率的な業務運営が可能になっています。
導入効果としては、1日あたり約4時間分の作業をロボットが代替しており、常勤スタッフ1名分に相当する業務量を吸収しているようです。
また、非接触での料理提供は感染対策にも寄与し、利用者に安心感を与えるだけでなく、猫型配膳ロボットの可愛らしい外観が話題性を呼び、顧客満足度の向上にもつながっています。
出典:SGST、日本国内初、大学病院内に配膳ロボットを導入|株式会社SGSTのプレスリリース
大竹カントリークラブ|ゴルフ場
大分県の大竹カントリークラブでは、ゴルフ場併設レストランにPudu Robotics社の配膳ロボット「BellaBot(ベラボット)」を導入しています。
当施設は、慢性的な採用難によるホール人員不足に加えて、団体利用によるパーティルームでの大量注文時に、配膳業務が追いつかないという課題を抱えていました。
BellaBotは、注文品の配膳から使用済み食器の下膳までを自律的に行うことで、人手による運搬作業を代替しています。これにより、人間のスタッフは、注文の確認や接客、セッティングといったサービスに専念できるようになりました。
導入後は、大量注文時の配膳ミスや抜け漏れがゼロになり、業務の正確性と効率が改善されたと報告されています。店長は「初めて本来業務に集中できた」と導入効果を高く評価しており、配膳ロボットの活用が現場の働き方を見直すきっかけにもなっています。
出典:サービスの質を問われやすいゴルフ場内レストランで人材不足を解消|DFA Robotics
以上が、当記事でピックアップした、配膳ロボットの導入店舗事例です。上記以外にも、さまざまな店舗で導入が進んでおり、今後ますます我々の生活で目にする機会が増えていくでしょう。
次章では、配膳ロボットの導入において知っておきたい、配膳ロボットの導入が向いている店舗の特徴を解説します。
配膳ロボットの導入が向いている店舗の特徴を解説

配膳ロボットはあらゆる飲食店に適しているわけではありません。実際に導入効果が出やすいのは、一定の条件を満たす店舗です。以下のような特徴を持つ店舗では、ロボットの活躍が期待できるでしょう。
- 店舗面積が広く、傾斜や段差も少ない
- 人手不足であり、配膳の負荷が高い
- 客層がファミリー層
- 標準的な業務マニュアルが整っている
これらの特徴について、以下で詳しく解説していきます。
店舗面積が広く、傾斜や段差も少ない
配膳ロボットは、センサーやカメラによって自律走行を行いますが、段差や傾斜、狭い通路が多い環境では誤動作や走行不能のリスクが高まります。そのため、店内が広くフラットで、動線が確保されている店舗は、ロボットの走行効率が良く、導入効果が出やすいです。
特にホール面積が広く、キッチンからテーブルまでの距離が長い店舗では、スタッフの歩行距離が大きな負担になります。そうした店舗では、配膳ロボットが運搬業務を担うことで業務効率化と省人化の両立が可能になるでしょう。
人手不足であり、配膳の負荷が高い
飲食業界は深刻な人手不足に直面しており、配膳や下膳の負担がスタッフの離職要因になるケースもあります。ホール業務の中でも、料理の運搬は単純ながらも体力を要する反復作業であり、業務時間の多くを占めているでしょう。
配膳ロボットを導入することで、スタッフは接客やオーダー対応など、より人間らしい業務に専念できるようになります。特にピークタイムの忙しい時間帯に、配膳をロボットに任せることで、人的リソースを柔軟に配分できるのがメリットです。
客層がファミリー層
ファミリーレストランなど、子ども連れの利用が多い店舗では、配膳ロボットの導入が顧客体験の向上にもつながります。特にPudu Roboticsの「BellaBot」のような、猫型の可愛らしい外観を持つ配膳ロボットは、子どもに人気があり、親子の会話のきっかけにもなるでしょう。
また、ファミリー層は配膳速度やスタッフの気配りなどにも敏感な場合もあり、ロボットが繰り返し正確に運ぶことで、サービス全体の安定感を高められます。そのため、省力化と顧客満足の両立を図る上で、効果的な活用が期待できます。
標準的な業務マニュアルが整っている
配膳ロボットの効果を最大限に引き出すには、スタッフがロボットの動作を正しく理解し、業務フローの中で適切に組み込める環境が必要です。そのためには、業務マニュアルが標準化され、誰が操作しても同じ動きができる状態であることが理想です。
マニュアルが整っていない店舗では、配膳ロボットの活用が属人化しやすく、結果としてうまく運用されずに現場に混乱を招くことがあります。
逆に、オペレーションが確立されている店舗であれば、配膳ロボット導入による業務改革がスムーズに進行するでしょう。
以上が、配膳ロボットの導入がおすすめできる店舗の特徴です。次章で、反対に配膳ロボットの導入が向いていない店舗の特徴も確認しておきましょう。
逆に配膳ロボットの導入に向いていない店舗の特徴
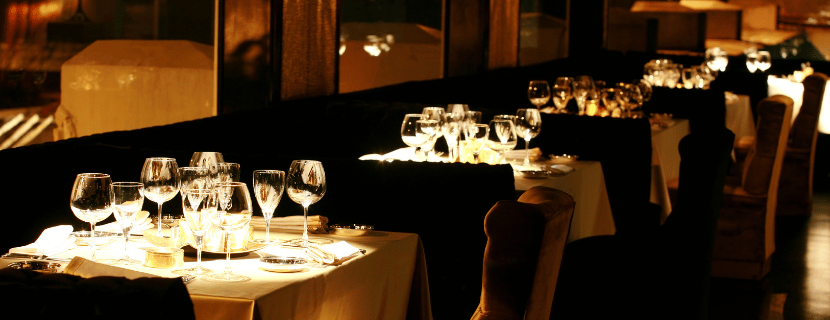
配膳ロボットは便利なツールですが、すべての店舗に適しているわけではありません。店舗のレイアウトや業態、求められるサービス水準によっては、かえって導入が業務効率を下げたり、顧客満足度を損ねる恐れもあります。
以下に、導入に向いていない代表的なケースを紹介します。
- 狭い店舗で椅子や机の位置も固定されていない
- 床が滑りやすかったり、傾斜や段差が多かったりする
- 高級業態や接待利用の店舗
これらの条件に当てはまる場合、配膳ロボットの導入は慎重に検討する必要があります。
狭い店舗で椅子や机の位置も固定されていない
配膳ロボットは事前にマッピングされた経路をもとに自律走行を行います。そのため、通路幅が狭かったり、席数が多くて椅子や机の配置が流動的だったりする店舗では、正確に走行することが難しくなります。
特に、椅子の位置が毎回異なるような店舗では、配膳ロボットが通路をふさがれたり、接触して停止するトラブルが頻発しやすくなるでしょう。
こういった店舗では、人の手で柔軟に動ける環境の方が効率的な場合も多いため、配膳ロボット導入は不向きと言えます。
床が滑りやすかったり、傾斜や段差が多かったりする
配膳ロボットの自律走行には、走行面の安定性が重要です。床が滑りやすい素材でできていたり、段差や傾斜が頻繁にある店舗では、スリップや走行不能といったリスクが高まります。
特に飲食店では、水や油が床にこぼれることも多いため、安全面への配慮が求められます。人間のスタッフなら即時に判断して回避できますが、配膳ロボットは一時停止や緊急停止になることが多く、結果として業務効率が下がる可能性もあるでしょう。
高級業態や接待利用の店舗
高価格帯のレストランや接待用の店舗では、料理の提供タイミングやプレゼンテーションが重要視されるため、ロボットによる配膳はブランド価値や顧客体験を損なう懸念があります。
また、静かで落ち着いた空間を重視する業態では、配膳ロボットの動作音や存在感そのものが場の雰囲気を乱す要因になり得ます。
そのため、人間による丁寧な所作や心配りがサービスの一環であるような店舗には、配膳ロボットはなじみにくいでしょう。
上記の条件と自店舗の状況を改めて見直し、配膳ロボットのを導入すべきか否かを慎重に検討してください。
まとめ

配膳ロボットは、スタッフの業務負担を軽減しながらサービス品質を向上させる手段として、多くの現場で成果を上げています。特に、面積が広く人手が不足しがちな店舗や、ファミリー層の来店が多い飲食店では、高い導入効果が確認されています。
一方で、店内の構造や業態によっては、導入が難しいケースもあるため、事前に現場環境をよく見極めることが重要です。
本記事で紹介した事例や導入の向き不向きの特徴を参考に、自店舗での活用可能性をぜひ検討してみてください。配膳ロボットの力を最大限に活かすことで、店舗運営の課題解決につながるでしょう。
